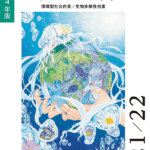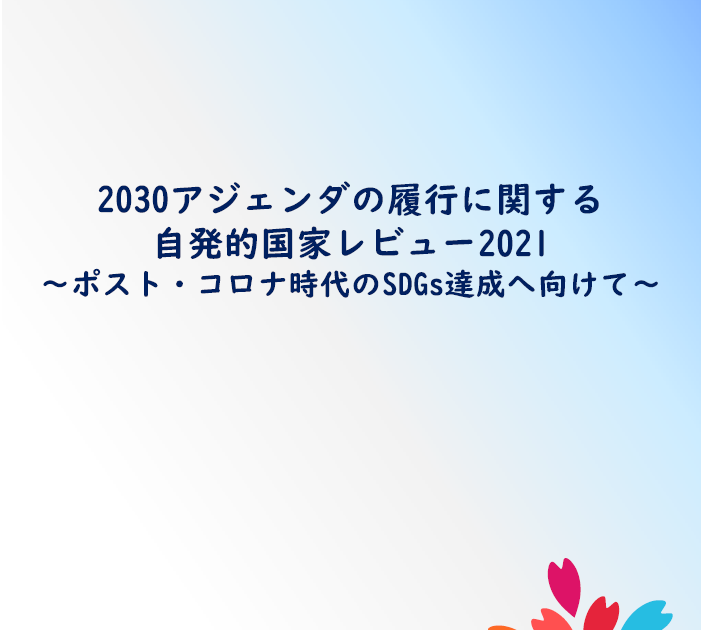
自発的国家レビュー(VNR)
「持続可能な開発のための2030アジェンダ」は、国連加盟国が、国及び地域レベルにおいて、各々の国のイニシアティブで、定期的にSDGsを巡る進捗に関する自発的国家レビュー(VNR: Voluntary National Review)を行うことを促しており、毎年7月に国連経済社会理事会の下で開催されるハイレベル政治フォーラム(HLPF)に提出される。日本は2017年のHLPFでVNRを発表。2021年度のHLPFで4年ぶり2回目のVNRを提出する。
自発的国家レビュー(VNR)の概要
巻頭メッセージ(菅前総理(SDGs推進本部長))
- 新型コロナウイルスの感染拡大により、人間の安全保障が脅かされており、持続可能な開発目標(SDGS)の達成に向けた取組を一層加速させることが求められています。2030年までに、このSDGSの達成を実現するためには、世界が団結して取り組むとともに、各国が、前例にとらわれない戦略を立てて、取組を拡大・加速していかなくてはなりません。多国間主義アプローチを重視する日本は、自らが率先して、こうした国際社会の努力をリードしていく決意です。
- 私はこれまで、人間の安全保障の理念に立脚し、「誰の健康も取り残さない」という考えの下、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジを推進すると共に、グリーン社会の実現やデジタル改革に向けた取組などを進めてきました。ポストコロナ時代におけるSDGSの達成に向けては、あらゆる分野において革新的なイノベーションを活用し、様々な政策を総動員し、未来を先取りする社会変革に取り組まなければなりません。
- 特に、気候変動問題は、人類全体で解決を目指すべき待ったなしの課題です。そのため、気候変動への対応が、日本、そして、世界経済を長期にわたり力強く成長させる原動力になるとの考えの下、日本は、2030年度において、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指し、更に、50%の高みに向けた挑戦を続け、2050年には、カーボンニュートラルの実現を目指します。
- 日本は、新型コロナからの「より良い回復」を遂げるため、この自発的国家レビュー(VNR)にとりまとめたビジョンや取組、現状を踏まえ、あらゆる国・地域、組織・団体、市民社会、そして個人との協力を深めながら、SDGS達成の実現に向けた取組を加速してまいります。
報告書作成方法
- SDGS推進本部の下、関係省庁の枠を超えて議論を行うだけではなく、様々な分野の代表者から構成される円卓会議や市民社会、ユース世代等との意見交換等を行い、報告書をパブリックコメントにかけることで、幅広い市民の声を取り入れることとした。
- 政府の自己評価だけではなく、円卓会議の民間構成員に政府の取組を評価してもらうこととした。
- 2017年に提出したVNRを基としつつ、日本が進めてきた幅広い取組を取り上げた。特に、日本各地で多くの地方自治体が持続可能なまちづくりや地域活性化に向けてSDGSを取り入れている例を紹介。
- 課題や反省点、今後留意すべき点を取り上げ、今後のSDGS推進に向けた進め方についても検討。
SDGs達成に向けたビジョン
(1)なぜ日本がSDGS達成に向けて取り組むのか
• SDGSは、日本が持続可能な形で発展する上で重要な指針となる。
(2)新型コロナウイルス感染症の拡大からの「よりよい回復」のためのSDGS
• SDGSを羅針盤として掲げつつ、あらゆる関係者を巻き込み、社会全体の行動変容を進めることが必要で
ある。
国内のSDGs推進体制・主な取組
(1)SDGS推進に向けた国内体制:2017年12月以来、「SDGSアクションプラン」を毎年策定。
(2)国内普及の動き:SDGS推進本部の下、「ジャパンSDGSアワード」、「SDGS未来都市」等の取組を
通じてSDGSの国内的な認知度向上や啓発、普及のための広報・啓発活動を積極的に実施。
(3)8つの優先課題と主な取組:国内の課題と取組や国際協力に関する主な取組を記載。
各目標の達成状況
政府による評価
- 再エネ比率は18%(2019年度)にまで拡大。導入量は再エネ全体で世界第6位(2018年)、太陽光発電は世界第3位(2018年)となり、再エネの導入は着実に進展している。温室効果ガスの総排出量は、2014年度以降、6年連続減少。
- 学習指導要領の改訂が行われ、持続可能な開発のための教育(ESD)の理念が盛り込まれた。
- 女性活躍は一定の前進が見られているが、日本のジェンダー・ギャップ指数の総合順位は156か国中120位。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が、女性に特に強く表れている。
- 2020年は11年ぶりに自殺者数が増加し、特に女性の自殺者数は前年と比べて935人増加。
- 2018年の「相対的貧困率」(貧困線に満たない世帯員の割合)は15.4%(対 2015年マイナス0.3 ポイント)。新型コロナウイルス感染症の拡大は、今後の状況変化を要注視。
円卓会議民間構成員による評価
- 経営陣のSDGs認知・定着率は85%(2020年、「SDGs実態調査」)となり企業経営にSDGsが浸透。一般のSDGs認知度は50%を初めて超えた(2021年、朝日新聞調査)
- 2020年初頭からコロナ克服のための国際協調に取り組み、COVAX、ACTアクセラレーターの創設や資金拠出にも積極的に取り組んだことは高い評価。
- 国内では300を超える自治体がゼロカーボンシティを表明。企業レベルにおいても、「SDGs実態調査」では90%以上の企業が脱炭素化に向けた取組を進めている。2050年に実質的排出をゼロにするという目標に鑑みると、再エネの大幅な増加には未だほど遠い。
- 京都コングレスを開催して国際的な役割を果たしており、司法・犯罪対策、途上国の法制度整備に取り組んでいる。
- 貧困率は2018年で15.4%、6人に1人が貧困。子どもの貧困率は13.5%で7人に1人の子どもが貧困。
- 外国籍の児童・生徒のうち、6人に1人(約16%)が小学校・中学校に通えていない。
- ジェンダーギャップが深刻化。新型コロナウイルス感染症の拡大で家賃延滞等が発生。「生理の貧困」問題も顕在化。女性の自殺率は、2020年10月の調査によれば前年比86%増。20代、40代では2倍に増加。
今後の進め方
VNRはあくまで「レビュー」であり、VNRを通じて明らかとなった進捗と課題を踏まえて、2030年のSDGs達成に向けた取組を今後いかに加速していくかが重要。今後以下のような点に留意しながら取組を進めていく。
- SDGs推進体制の強化
若者を含め、多くのステークホルダーの声を反映させる機会を設けるように努める。 - 目標や指標の整備を含めた進捗評価体制の整備
目標や指標の更なる整備、代替指標の活用可能性に向けて議論を進める。進捗評価体制の充実と透明性の向上に向け、各国の例も参考にしながら、今後の取組を検討する。
SDGsの配慮に関するPDCAサイクルを導入している省庁の例(例:環境省)も踏まえ、具体の評価のあり方について検討する。 - 日本の取組の国際展開
日本の取組を他国に共有し、SDGs達成に向けた更なる連携・取組を進める。自発的ローカルレビュー(VLR)の実施、国際的な自治体間協力を促す。 - 今後の国内啓発
一人ひとりがSDGsを自分事とし、行動変容を進めていくような国内啓発に努める。 - 今後のVNR実施
中長期的な進捗評価プロセスを踏まえつつ、望ましいタイミングで実施。
8つの優先課題と主な取組
- あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現
・男女共同参画基本計画に基づき、女性活躍推進に向けた取組を加速。
・ダイバーシティ・バリアフリーの推進。在留外国人との共生社会実現への取組。
・テレワークの普及、長時間労働の是正、柔軟な働き方がしやすい環境整備、女性・若者の活躍推進などを通じた働き方改革。
・子供の貧困対策やオンライン教育の推進。持続可能な開発のための教育(ESD)の推進を通じた次世代へのSDGs浸透。
・「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)の実施を通じた、持続可能で包摂的な社会の実現への寄与。 - 健康・長寿の達成
・利用者の視点に立った切れ目のない医療や介護の提供体制構築。
・「誰の健康も取り残さない」という考えの下、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成に向け、強靭かつ包摂的な保健システムの構築、感染症に強い環境整備。
・次なる健康危機に備え、機材の整備、人材育成など、国内外の保健医療システム強化。
・健康・長寿社会の達成を念頭に、食育や栄養政策を推進。 - 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション
・Society5.0の実現に向けた、スマートシティの推進。
・持続可能なまちづくりに資する優れた地方公共団体の取組を「SDGs未来都市」として選出し、成功事例の国内外への普及展開。「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」を通じた民間参画の促進と「地方創生SDGs金融」を通じた自律的好循環の形成等の取組促進。
・科学技術イノベーション(STI)を総動員し、戦略的に地球規模課題の解決に取り組んでいくことで、SDGs達成に向けた取組を加速。 - 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備
・過去の大規模自然災害の経験も踏まえ、防災・減災の取組を推進。「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会の構築に向けた「国土強靱化」を推進。国外に向けても日本の経験を普及。
・特に途上国の「質の高い成長」を実現するため、「質の高いインフラ投資に関するG20原則」を踏まえた質の高いインフラ投資を官民一体となって支援。 - 省・再生可能エネルギー、防災・気候変動対策、循環型社会
・2050年カーボンニュートラルの実現を目指すため、「グリーン成長戦略」を推進し、ESG投資の拡大を推進。経済と環境の好循環の創出。
・2020年3月に閣議決定された「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」に基づく施策の推進なども通じ、持続可能な生産・消費を促進。 - 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全
・海洋プラスチックごみによる新たな汚染を2050年までにゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」に関する取組。
・海洋資源の持続的利用や森林保全など、生物多様性の保全を推進。自然環境が提供する生態系サービスの維持・向上。 - 平和と安全・安心社会の実現
・人道・開発・平和の切れ目の無い支援を継続。人間の安全保障の考え方に基づいた、能力構築や人材育成等の取組。
・京都コングレス等を通じ、国内外で、法の支配の確立を推進。
・DVや性暴力、児童虐待への対策強化や、児童虐待や子供の性被害の防止のための取組を推進。 - SDGs 実施推進の体制と手段
・ESG投資推進も通じ、民間企業のSDGs推進に向けた取組を後押し。
・JICA債など民間資金を通じた資金調達を促進し、SDGs達成に向けた資金ギャップを埋める。
・「日メコンSDGsイニシアティブ」をはじめ、各国・機関との連携も通じて、SDGs達成に向けた取組強化。
政府による評価の概要
目標1:貧困をなくそう
当該目標の直接的な指標ではないが、「子供の貧困率」は、2014年に「子供の貧困対策大綱」が策定された時は16.3%だったが、2019年国民生活基礎調査同調査では、13.5%。生活保護の被保護者数は、2015年3月に過去最高を記録したが、以降減少に転じ、2020年12月には約205.0万人。ピーク時から約12万人減少。新型コロナの影響は今後も注視する必要。
目標3:すべての人に健康と福祉を
健康寿命の延伸と健康格差の縮小については改善がみられるが、循環器疾患や糖尿病など、更なる取組が必要とみられるものもある。体の健康だけでなく、心の健康も課題。新型コロナウイルス感染症の拡大後、2020年は11年ぶりに自殺者数が増加し、特に女性の自殺者数は前年と比べて935人増加。
目標4:質の高い教育をみんなに
2019年10月から幼児教育・保育の無償化。学習指導要領の改訂が行われ、持続可能な開発のための教育(ESD)の理念が盛り込まれ、小学校では2020年4月から、中学校では2021年4月から、高校では2022年4月から順次実施。
目標5:ジェンダー平等を実現しよう
上場企業の女性役員数は5年間で約2.2倍、民間企業の各役職段階に占める女性の割合も上昇するなど、女性活躍は一定の前進が見られているが、日本のジェンダー・ギャップ指数の総合順位は156か国中120位。新型コロナウイルス感染症拡大の影響が、女性に特に強く表れている(非正規雇用労働者を中心に、女性の雇用者数が昨年4月には対前月比で男性の約2倍減少、昨年4月から12月までのDVの相談件数は前年同期と比べて約1.5倍、昨年の女性の自殺者数は前年と比べて935人増加)
目標7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに
2012年にFIT制度を導入し、10%(2012年度)であった再エネ比率は18%(2019年度)にまで拡大。導入量は再エネ全体で世界第6位(2018年)、太陽光発電は世界第3位(2018年)となり、発電電力量の伸びは、2012年以降、約3倍に増加というペースで、欧州や世界平均を上回る等、再エネの導入は着実に進展している。
目標8:働きがいも経済成長も
非正規雇用労働者は全体として増加傾向にあり、2019年には2,165万人と、雇用者の約4割を占める。非正規雇用労働者の待遇の改善に向けては、最低賃金の引上げや同一労働同一賃金の実現等を進めており、2010年と2019年で比較すると、「正社員・正職員」に比べて「正社員・正職員以外」の伸びの方が大きい。
目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう
「Global Innovation Index: GII」では、2010年代前半には20位圏内を推移していたが、近年少しずつ順位を上げており、2019年には15位となった。日本は、①公的機関、③インフラストラクチャー、④市場の成熟度、⑤ビジネスの高度化、⑥知識と技術アウトプットの指標については総じて10位圏内に入る実力を示している。
目標10:人や国の不平等をなくそう
2019年国民生活基礎調査に基づけば、2018年の「相対的貧困率」(貧困線に満たない世帯員の割合)は15.4%(対 2015年マイナス0.3 ポイント)。新型コロナウイルス感染症の拡大は、今後の状況変化を要注視。
目標13:気候変動に具体的な対策を
温室効果ガスの総排出量は、2014年度以降、6年連続で減少し、排出量を算定している1990年度以降、最小値を更新。実質GDP当たりの温室効果ガスの排出量は、2013年度以降7年連続で減少。
円卓会議民間構成員による評価の概要
目標1:貧困をなくそう
貧困率は2018年で15.4%、6人に1人が貧困。子どもの貧困率は13.5%で7人に1人の子どもが貧困。「貧困率を半減させること(1.2)」には程遠い。
目標3:すべての人に健康と福祉を
日本が2020年初頭からコロナ克服のための国際協調に取り組み、COVAX、ACTアクセラレーターの創設や資金拠出にも積極的に取り組んだことは高い評価に値する。
目標4:質の高い教育をみんなに
外国籍の児童・生徒のうち、6人に1人(約16%)が小学校・中学校に通えていない不就学状態。コロナの影響でさらに悪化する可能性。
目標5:ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダーギャップが深刻化。新型コロナウイルス感染症の拡大で、短期契約や細切れ雇用も枯渇し、家賃延滞などの深刻な問題が生じている。「生理の貧困」問題も顕在化。女性の自殺率は、2020年10月の調査によれば前年比86%増。20代、40代では2倍に増加。
目標7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに
2050年に実質的排出をゼロにするという目標にかんがみると、再生可能エネルギーの大幅な増加には未だほど遠い。
目標8:働きがいも経済成長も
新型コロナウイルス感染症の拡大で、パートタイマー、アルバイト、派遣社員を含む非正規労働者の雇用者数が100万人を超えて減少した。
目標11:住み続けられるまちづくりを
また、地域住民の発案による地域の問題解決や新たな価値創造を参加型で一定の予算をつける形で行政政策に導入する「住民提案型事業」のパイオニア自治体が「SDGs未来都市」に名を連ねていることは高く評価できる。
目標13:気候変動に具体的な対策を
国内では300を超える自治体がゼロカーボンシティを表明。企業レベルにおいても、「SDGs実態調査」では90%以上の企業が脱炭素化に向けた取組を進めている。
目標16.平和と公正をすべての人に
京都コングレスを開催して国際的な役割を果たしており、司法・犯罪対策、途上国の法制度整備に取り組んでいる。
課題と変革へ向けた提言
- SDGs達成に向けた総体的で客観的な目標、科学に基づくターゲットや指標の整備が重要になるが、現状遅れている。
- 毎年発表されるアクションプランも定量化すべき。アクションプランではベースラインデータとターゲット及びその達成期限を明確にし、これに基づいて、ギャップ分析を行うべき。
- 指標についてはグローバル指標の整備を進め、現在、出せるデータが存在しない場合は、「出す時期」を表明すべき。
- 目標毎のレビューのみならず、マルチベネフィット創出・複数目標間のシナジーの観点でも評価すべき。(クリーンエネルギー(SDG7)、産業と技術革新(SDG9)、都市防災(SDG11)、生物多様性(SDG15)など)
- 2025年ごろに次のVNRを提出すべき。
出典:首相官邸