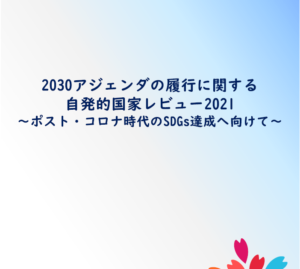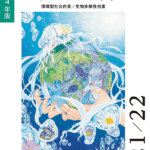2022年4月23日(土)24日(日)
熊本城ホール(熊本市中央区桜町)
全体テーマ 持続可能な発展のための水~実践と継承~
アジア・太平洋水サミット
アジア・太平洋水サミット(APWS)とは、開催国政府・開催地の都市とAPWFが共催する、アジア太平洋地域の首脳級が、地域、及び、各国が抱える水問題に対する認識を深め、その課題解決に向け、強いリーダーシップの発揮や資源の動員を促すことを目的とした国際会議である。
第4回APWSの円滑な実施のため、2019年3月26日、外務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣の共同による閣議請議が行われ、関係行政機関が必要な協力を行うことについて、閣議了解を得て、日本の水分野に携わる多様な関係者と開催の準備に着手することができた。
第4回APWS当日には、天皇皇后両陛下のオンラインによるご臨席を賜った。また、天皇陛下より開会式で、おことばを賜るとともに、「人の心と水~信仰の中の水に触れる~」と題した記念講演を賜わった。
また、開催国代表として、岸田文雄内閣総理大臣には、熊本城ホールで第4回APWSに参加頂き、開会挨拶に加え、首脳級会合において、基調演説をして頂いた。他国からは、17カ国の首脳級、22カ国の閣僚級、9カ国の大使等、及び、アントニオ・グテーレス国連事務総長をはじめ、26の国際機関の長等に参加頂き、水課題解決や質の高い成長に関するステートメント等を述べて頂いた。そして、第4回APWSに参加をした首脳級による、水問題の解決と質の高い社会への変革に向けた共同決意声明である「熊本宣言文書」を全会一致で採択した。さらに、「熊本宣言」の趣旨に沿い首脳級から受けた問いに答えるべく、国内外の専門家や実務者等の協力・協働を得て、9つの分科会、4つの統合セッション、2つの特別セッションを開催した。これらの議論の成果として、アジア太平洋地域の質の高い成長に向けた明確な道筋を示し、熊本宣言の一部でもある、「第4回APWS議長サマリー」をとりまとめた。
第4回APWSにおける議論、プログラム構成、及び各成果
アジア太平洋地域が新型コロナウィルス感染症からの復興の過程で、水問題および複雑に入り組んだ関連諸問題を解決し、次世代に渡って持続可能な発展を可能にしていくためには、健全な水循環を維持または回復しつつ、気候の変化によって激甚化する気象現象と洪水や渇水などの水災害に対する強靭性(Resilience)、安全な水、衛生施設や食料・栄養等へのアクセス、水災害対策、水資源管理などにおける、ジェンダーにとらわれず、貧困層や社会的弱者を含み、誰も取り残されない包摂性(Inclusiveness)、社会活動や環境を保全、維持する持続可能性(Sustainability)のすべてを満足する「質の高い成長」を実現していくことが不可欠である。そこで、第4回APWSでは、アジア太平洋地域において質の高い成長を実現していくために必要なことを科学技術、ガバナンス、ファイナンスの観点から提示すること、及び「質の高い成長」を下支えする「質の高いインフラ」をハード・ソフトの両面から促進するための議論の枠組みを構築した。各プログラムの開催結果を報告する。
「熊本宣言」
コロナ禍と回復における水問題
新型コロナウィルス感染症の世界的な蔓延(パンデミック)は、世界中の国々の社会経済に深刻な影響を与え、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ(SDGs)」達成を阻害している。このパンデミックにより、災害対応や水供給に支障が生じた。他方、安全で安価な水と衛生のアクセスの欠如や水害・干ばつにより、パンデミックへの対応が世界的に困難となった。こうした被害は地域や属性で違いがあり、島嶼国や内陸地域、脆弱層が特に厳しい影響を被っている。
我々、第 4 回アジア・太平洋サミットの参加国のリーダーは、これまでのサミット宣言を踏まえ、新型コロナにより広がる被害、その危機に対処する中で、水の重要性と意義を改めて認識した。コロナ禍からの回復において、水分野が重要な役割を果たすことを確認した。また、気候変動により、台風などの気象現象および高潮、洪水・渇水の水災害の激甚化、土壌や水質の悪化、海面上昇、氷河の溶解といった連鎖する複合的な脅威が発生し、深刻化し続ける。しかし、健全な水循環を取り戻すことで、災害に備え、多角的な SDGs を達成し、さらには国際河川での協力を強化できる。
質の高い社会への変革
我々は、コロナ禍からの回復において、強靭性、持続可能性、包摂性を兼ね備えた質の高い社会への変革が必要である、との共通の認識を持つに至った。これは、持続可能な水利用のための取組みの強化により実現可能である。この変革は、オープンで、透明性があり、協調的な参加プロセスを通じて、多くの関係者により進められるべきものである。
強靱性のために、水関連災害に流域全体で分野横断的に取組む。水の安全保障と、感染症への基本的な公衆衛生対策である水と衛生へのアクセスを強化していく。
持続可能性のために、水を政治課題の中心に据える。気候変動対策について、低炭素エネルギーを活用した緩和策と、災害対策・インフラ整備の適応策を併せて進める。また、自然共生社会、生物多様性の保全と調和したカーボンニュートラル社会の実現に向けて、緩和・適応の効果が期待できるグリーンインフラを推進する。
包摂性のために、アジア太平洋地域でのこれまでの SDG 達成のトレンドを維持し、2030 年を待たずに女性、若年者、高齢者を含むすべての人々に対して、安全で安価な水と衛生へのアクセスを達成し、野外排泄をなくし、災害対策を進め、水に関連する SDG を達成するよう努力する。水と衛生へのアクセスと災害からの保護において格差を是正する。また、質の高い社会に向けて、水問題に対応するための活動に、官民分野が共に関与し協働することを奨励する。
水問題は食料問題やエネルギー問題と密接不可分である。様々な水の価値を検討し、災害リスク軽減や環境改善、水の利用効率の向上も含めた、氷河・水源から海までの水資源のより統合的な管理を通じて、持続的に解決する。
取組みの加速に向けて
我々は、「質の高い社会」を実現するために、水データ・インフラや知識・情報を含めた、水分野でのハード・ソフトを総合した、質の高いインフラ整備を強化していくことを決意する。
「従来の手法」を打破し、取組みを加速するために
-
ガバナンスを整える:水に関わる多くの機関・市民社会が、分野及び世代を超えて連携するよう指導していく。各流域において、ともに発展していくために、問題を解決し繁栄を分かち合ってきた良き事例を、国際的な合意や国内法に応じて、共有していきたい。
-
資金ギャップを埋める:水投資がもたらす成長への貢献を認識し、第 3 回アジア・太平洋水サミットで採択されたヤンゴン宣言を踏まえ、流域毎に公的部門のみならず、国際機関、地域機関、援助機関、自治体、地域社会、民間が資金を動員する重要性を認識した。
(ヤンゴン宣言では、アジア太平洋地域の投資の倍増を目指すこととした) -
科学技術へ要望する:地域の自然環境、地理的特性や歴史的経過を尊重し、発展段階に応じた水問題解決の科学技術の提供を強く望む。また、水循環を保全、改善するために、次の世代の水の専門家への教育や能力強化は重要である。
第 4 回アジア・太平洋水サミットの成果
我々は、水問題の解決策の一つとして日本政府より発表された日本のイニシアティブを評価し、支持する。我々は本サミットの参加者とともに、この宣言と前述の観点における、サミットでの議論をボン水対話、世界水フォーラム、ドゥシャンベ・プロセスなど主要な準備プロセスと連携しつつ、2023 年 3 月に開催される「水の
国際行動の 10 年」の国連中間レビュー会議をはじめ、第 2 回ドゥシャンベ水の国際行動の10年会合、ハイレベル政治フォーラム、防災グローバルプラットフォーム、国連気候変動枠組条約第 27 回締約国会議、国連生物多様性条約第 15 回締約国会議、G7、G20 等の水に関係するグローバルな議論プロセスにて報告し、この宣言が反映・活用されるよう働きかけを行う。
第 4 回アジア・太平洋水サミットを成功裏に開催した熊本市とアジア・太平洋水フォーラムに心より感謝する。
首脳級からサミット参加者への問い
すべての水関連分野において、ガバナンス、ファイナンス、科学技術の 3 つの分野で変革と改善を行うための障壁、突破口、機会、推進方法を特定し、徹底的に議論する必要がある。特に、科学技術については、リーダーの分野横断的な意思決定において、どのような役割を果たすべきか答えを導くことが非常に重要である。第 4 回 APWS に集まったリーダー、専門家、科学者、そして、すべての関係者に、上記宣言の趣旨を踏まえて議論し、実質的な、その答えを導き出し、このサミットの成果にしていただきたい。
出典:熊本市