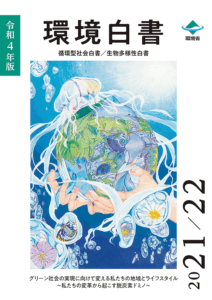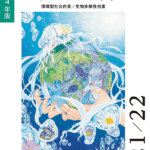問題1 (No.5)
SDGsゴール1 「貧困をなくそう」 に関連する次の文章のうち、 その内容が最も誤っているものを選択してください。
-
日本の子どもの貧困率は現在、OECD加盟国の中で最悪の水準にあって、 1980年代から上昇傾向にあり、 現在7人に1人の子どもが貧困状態に あるとされている。 ここで定義されている 「子どもの貧困率」 とは、相対的貧困の状態にある18歳未満の子どもの割合を指す。
⇒〇 -
SDGsターゲット1.1は 「極度の貧困」 を1日1.25ドル未満で生活する人びとと定義し、貧困をゼロにすることを目指している。
⇒〇 -
SDGsには17のゴールが設定されており、いずれのゴールも等しく価値を持つものの、 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」 において 貧困の撲滅が優先的に取り上げられている。 ゴール1の達成は、持続可能な開発のための不可欠な条件であると認識されている。
⇒△誰ひとり取り残さない -
貧困にも多様なものがあり、 経済的な理由で生理用品を購入できない女性や女の子がいるという 「生理の貧困」 というものがある。 この解決 はSDGsゴールやゴール3などを実現するものとして、 様々な取り組みがなされている。
⇒〇5.6と5.cも関わる -
ターゲット1.2においては、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態 (相対的貧困) にある、 全ての年齢の男性、女性、 子供の割合を半減させ るとしている。 厚生労働省が発表する2019年 「国民生活基礎調査」によると、 日本の相対的貧困率は相当程度改善しており、 2018年の相対 的貧困率はリーマンショックが発生した直後の2009年と比較しておよそ半減している。
⇒×半減はしていない
問題2 (No.14)
SDGsゴール9 「産業と技術革新の基盤をつくろう」 に関する以下の文章の中で、 誤っているものの個数を選択してください。
-
2014年のアフリカインフラ開発プログラム (PDA) のレポートによれば、 移動に利用できる道路の割合は、他の地域の開発途上国では50%な のに対し、 アフリカでは34%に過ぎないとされている。
⇒〇 -
インフラの不備は生産性に影響を与え、生産コスト・取引コストを上昇させ、 企業の競争力と政府の経済社会開発政策の遂行能力を低下させる ことにより成長を阻害する。 2014年のアフリカインフラ開発プログラム (PDA) のレポートによれば、 今日のアフリカにおける不十分なインフラ は、成長率を2%奪っているとされている。
⇒〇 -
日本政府は、 現在インフラが整っていない国に対しての支援や取り組みとして、 2015年5月には 「質の高いインフラパートナーシップ」、 2016 年5月には 「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」 をそれぞれ発表し、 世界の需要に対して質の高いインフラ整備推進を行っている。
⇒〇 -
日本国内における社会資本ストックは高度経済成長期に集中的に整備され、 今後急速に老朽化することが懸念されている。 国土交通省によれ ば、今後20年間で、 建設後50年以上経過する施設の割合は加速度的に高くなる見込みであり、 このように一斉に老朽化するインフラを戦略的に維持 管理・更新することが求められている。
⇒〇
問題3 (No.6)
SDGsゴール2 「飢餓をゼロに」 のターゲットに関連する次の文章のうち、その内容が最も誤っているものを選択してください。
-
国際連合食糧農業機関(FAO) の発表した「世界の食料安全保障と栄養の現状 2021年版」 によると、 世界で約10人に1人が栄養不足に陥っ ている状況にあり、 その半数はアジア地域であることが指摘されている。
⇒〇南アジア -
国連世界食糧計画 (WFP) の発表した 「食料危機に関するグローバル報告書」 では、2021年に53の国や地域で1億9300万人が危機的、 もし くはより深刻な急性食料不安であったことが示されている。 新型コロナウイルスの影響が減少したことにより、2020年よりも改善傾向にある ことが指摘されている。
⇒×24の国と地域で1億3900万人が食料不安 -
国連世界食糧計画 (WFP) の発表した 「食料危機に関するグローバル報告書」 は、 食料危機の原因として、 貧困、 環境、 気候変動などの他に 紛争をあげている。 同報告書では、 すでに世界の食料システムが相互に繋がっていることから、 紛争により世界の食料、 栄養安全保障に深刻 な結果をもたらすことを指摘している。
⇒〇 -
国際連合食糧農業機関(FAO) の発表した 「世界の食料安全保障と栄養の現状: 2021年版」 によると、 飢餓人口は2019年から2020年までに 約1億1800万人増加しており、 SDGsゴール2の目標から遠のいている状況にあることが指摘されている。
⇒〇
問題4 (No.8)
SDGsゴール3 「すべての人に健康と福祉を」のターゲット3.1では、 「2030年までに、 世界の妊産婦の死亡率を出生10万人当たり70人未満に削減す る。」とされています。 次の 「妊産婦死亡率」 に関する文章のうち、その内容が最も誤っているものを選択してください。
※妊産婦死亡率とは、 「妊娠中または妊娠終了後満42日未満の女性の死亡で、 妊娠の期間および部位には関係しないが、 妊娠もしくはその管理に関 連したまたはそれらによって悪化したすべての原因」 によって死亡した妊産婦の割合を示す数値である
- 日本の妊産婦死亡率は1900年では約 「400」 であったが、その後順調に減少を続け、1990年代から現在に至るまで 「10」 を超えたことはな い。
⇒〇 -
2017年の世界保健機関(WHO) の報告によると、 妊産婦の死亡原因として、 重度の出血、 妊娠中の高血圧、 安全でない中絶のほか、出産後 の感染症、合併症があげられており、 また妊産婦死亡のリスクは15歳未満の女性で最も高いことが指摘されている。
⇒× -
ユニセフが発表する 「世界子ども白書2019」 によると、 妊産婦死亡率の世界の平均値は約「157」 であった。 最も妊産婦死亡率が高かったの は南スーダンの 「1150」 であり、 最も妊産婦死亡率が低かったのは日本、イタリアなどの 「2」 であった。
⇒○日本「2.2」 -
2017年の世界保健機関(WHO) の報告によると、 妊産婦が必要な医療ケアを受けることができない原因として、貧困、 病院等の施設への物 理的なアクセスの困難性、 熟練した医療従事者の絶対数が少ないことなどがあげられている。
⇒〇
問題5 (No.18)
以下は、 「2030アジェンダの履行に関する自発的国家レビュー2021」 におけるSDGsゴール11 「住み続けられるまちづくりを」 の達成状況に関する 一部の記載です。 次の文章の中から最も誤っているものを選択してください。
-
公共交通サービスの維持・確保が厳しさを増している一方、 高齢者の運転免許の返納が年々増加し、 受け皿としての移動手段を確保すること が益々重要な課題になっている。こうしたことを踏まえ、 地域のニーズにきめ細やかに対応できる市町村等が、 地域交通に関するマスタープ ランである地域公共交通計画を策定した上で、 公共交通の改善や移動手段の確保に取り組むことができる仕組みを盛り込んだ 「持続可能な運 送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」 が2020年11 月に施行された。
⇒〇 -
日本は自然災害が多いことから、 平常時には堤防等のハード整備やハザードマップの作成等のソフト対策を実施している。 災害時には被災府 県からの要請があった場合に限り、 災害時における救急救命、 職員の現地派遣による人的支援、 避難所避難者へ必要不可欠と見込まれる物資 を緊急輸送するプッシュ型物資支援、 激甚災害指定や被災者生活再建支援法等による資金的支援等、 「公助」 による取組をしているのが現状 である。
⇒×災害時には被災府 県からの要請があった場合に限り -
2050年における人口推計を見ると、全国の居住地域の約半数で2015年時点に比べて人口が50%以上減少し、 人口規模が小さい市区町村ほど 人口減少率が高くなる傾向がある。 特に人口が1万人未満の市区町村では人口が約半分になるなど、 地方で更なる人口減少が起こると見込まれ ている。その結果、 小規模な市町村においては公共交通の利用者が一層減少することから、交通事業者の経営はこれまで以上に厳しくなり サービスが維持できなくなる可能性がある。
⇒〇 -
「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」により、 例えば過疎地等で市町村等が行う自家用有償旅客運送において、 バス・タクシー事業者がノウハウを活用して協力し、地域の輸 送資源を最大限活用する取組を推進するための制度を創設し、継続的な輸送サービスを提供することが可能となる。
⇒〇
問題6 (No.17)
SDGsゴール10 「人や国の不平等をなくそう」 に関する以下の文章の中で、 その内容が誤っているものの個数を選択してください。
-
国際NGOのオックスファムが発表した2020年版レポートによれば、世界の約2100人強の富豪の富が、 世界人口の60%の富をしのぐほどの額に 達している。
⇒〇 -
ゴール10のターゲットには、状態としての不平等を少なくするものや政治的、 税制面から不平等を是正することを目指すものが定められている が、民間の金融機関への働きかけを想定したものは規定されていない。
⇒× -
先進国内でも貧困の問題がある一方で、「フォーブズ」 誌が発表する世界長者番付にメキシコ、インド、 中国といった発展途上国の富豪が名前 を連ねるなど、国ごとではなく国境を越えて一人ひとりの格差が増大しており、 国際的な格差をなくす仕組みを導入していくことがゴール達成に重 要である。
⇒〇 -
リオの地球サミットで決定された「環境と開発に関するリオ宣言」 の第7原則では 「共通だが差異ある責任」 原則が定められており、この内容は 「2030アジェンダ」 に明記されているほか、 SDGsゴール10のターゲットにも明記されている。
⇒△明記なし -
ターゲット10.1は、各国での所得下位40%の所得の伸び率が国内平均を上回ることを目指しており、 相対的貧困率を下げるうえで具体的に必要 な方策が掲げられているといえる。
⇒〇
問題7 (No.12)
SDGsゴール7 「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」 に関連する次の文章のうち、 その内容が誤っているものの個数を選択してください。
- 経済産業省 資源エネルギー庁によれば、2019年度の日本の一次エネルギー自給率は約12%となっており、 OECDに加盟する36カ国 (当時) の うち35位となっている。
⇒×日本は42位 - 経済産業省 資源エネルギー庁によれば、2019年度の日本の化石燃料依存度は約85%となっており、 第一次オイルショックがあった1973年度よ りも化石燃料依存度は上昇している。
⇒×低下している - 経済産業省 資源エネルギー庁によれば、 リチウムイオン電池に使われているリチウム、 コバルト、 ニッケルなどのレアメタルの日本における調達のほとんど100%を輸入に頼っている
⇒〇 - 経済産業省 資源エネルギー庁によれば、 日本の再生エネルギー電力比率は2019年度で18%となっており、 再生エネルギー発電設備容量は世界 第6位で、 そのうち太陽光発電は世界第3位となっている。
⇒〇 - 経済産業省 資源エネルギー庁によれば、 日本の火山の地下深部にはマグマが存在し、 膨大な地熱エネルギーが眠っているため、 純国産の再生可 能なエネルギーとして貴重な資源であり、エネルギー資源に恵まれない日本にとって利用価値の高いエネルギーとされる。
⇒〇
問題8 (No.13)
SDGsゴール8 『働きがいも経済成長も』 に関連する記述です。 次の文章のうち、 その内容が最も誤っているものを選択してください。
-
日本においては、 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、 希望者全員が65歳まで働ける制度の導入が企業に義務づけられている。
⇒〇 -
移住労働者の権利を保護し、 安全・安心な労働環境を促進することは世界共通の目標でありSDGsゴール8のターゲットにも明記されている。
⇒〇 -
厚生労働省が発表している 「令和3年版厚生労働白書 – 新型コロナウイルス感染症と社会保障」 によると、 正規雇用を希望しながらそれがかな わず非正規雇用で働く人 (不本意非正規雇用労働者) の非正規雇用者全体における割合は10%を超えており、 特に25歳から34歳の若年層で は16%と高くなっている。
⇒〇 -
日本政府は、働く人びとの置かれた個々の事情に応じ、 多様な働き方を選択できる社会を実現し、 一人ひとりがより良い将来の展望を持てる ようにすることを目標に掲げて働き方改革を推進している。 具体的には、長時間労働の是正、 多様で柔軟な働き方の実現、 雇用形態にかかわ らない公正な待遇の確保を3本柱として定めている。
⇒△①長時間労働の是正 ②正規、非正規の格差解消 ③多様な働き方の実現 -
厚生労働省が発表している 「令和3年版厚生労働白書 – 新型コロナウイルス感染症と社会保障」 によると、 民間企業において雇用されている障 害者数は2010年以降、 過去最高を更新し続けており、 法定雇用率を達成した企業の割合は60%を超えている。
⇒×法定雇用率を達成した企業の割合は、48.6%(対前年比0.6ポイント増)となった。
問題9 (No.15)
SDGsゴール9 「産業と技術革新の基盤をつくろう」 に関する以下の文章の中で、その内容が最も誤っているものを選択してください。
-
ユニセフによれば、2050年までに世界の人口の3分の2以上が都市で暮らすようになるといわれている。 都市は農村とくらべると、 経済的に も発展していて、 様々な施設も整っているため、 都市の人口が増えるとより質の高い教育や医療を受けられる人が増える、ともいえる。
⇒△しかし、清潔な水、電気、および保健ケアなどの必須サービス を受けられない子どもたちの方が、圧倒的に多いのである。それが近くにあったとしてもだ。 圧倒的に多くの数の子どもたちが学校に通うかわりに危険で搾取的な労働を強いられている。 -
2018年にユニセフが発表したところによれば、 1996年に世界で7億5000万人だったスラムの人口は6億人と減少傾向にあるものの、 そのう ち3億人は子どもとされている。
⇒×2030年には20億人を突破 -
多くの人が密集して住んでいるスラムは、国が認めた居住区ではないため行政の手もなかなか届かない。 水やトイレ、ごみの処理などの生活 に必要な設備が不十分で衛生状態も悪く、 感染症がまん延するという課題がある。 ユニセフによれば、 保健や教育などの公共サービスから置 き去りにされた子どもたちの5歳未満死亡率は、 時に農村よりも悪く、 さらに小学校を修了できる割合も低いことがある。
⇒〇 -
2017年にユニセフとWHOが発表した水と衛生に関する報告書によれば、 世界では、 21億人 (世界人口の約10人に3人) が安全な水を自宅で 入手できず、 45億人 (同10人に6人) が安全に管理されたトイレを使うことができないとされている。
⇒〇 -
日本の厚生労働省によれば、 2018年時点で日本の水道普及率は98%であり、高いようにも見えるものの、残りの2%、 約230万人は日常的に 水道が利用できない状態にある。
⇒〇
問題10 (No.30)
以下は、児童婚 (18歳未満での結婚、 またはそれに相当する状態にあること) に関するユニセフの記述です。 次の文章のうち、 その内容が最も誤っ ているものを選択してください。
-
アメリカの州のなかには例外的に18歳未満の子どもの結婚を認める法律が存在する。 欧州連合 (EU) に加盟している国のなかでいかなる場合 においても18歳未満の結婚を禁止している国は2017年時点で10か国に満たない。
-
2030年までに 「持続可能な開発目標」 のとおりに児童婚をなくすためには、現状の減少傾向を維持することが必要である。
⇒×減少はしていない -
南アジアでは、女性が子どものうちに結婚させられてしまう可能性は20年前の約50%から約30%へと減少している。 これはインドで児童婚 の慣習が大幅に減っていることが大きく影響している。
-
南アジアは児童婚がもっとも広く行われている地域であり、 世界の児童婚の約44% (2億8500万人) を占めている。
⇒〇 -
教育を受ける女性の割合が増えたこと、各国政府が10代の女性に対する様々な投資を積極的に行うようになってきたこと、 児童婚が違法であ り児童婚によって女性の身に起こる様々な負の影響が広く知られるようになってきたことから児童婚は減少傾向にある。
⇒×減少はしていない
問題11 (No.28)
SDGsゴール17 「パートナーシップで目標を達成しよう」 に関する次の文章の中で、その内容が最も誤っているものを選択してください。
-
新型コロナウイルスの大流行により、貧しい国も豊かな国も同様に経済がマヒしている。 多くの低所得国では送金の減少に伴い経済ショック が増幅されることになる。 送金とは、 外国に出稼ぎに行く移民労働者が母国に送るお金のことである。 持続可能な開発目標(SDGs報告) 2021によると、2020年の送金フローは2019年に比べ20%程度減少した。
⇒△「持続可能な開発目標(SDGs報告) 2021」によれば、具体的な数値については記載されていませんが、2020年においては世界的なCOVID-19パンデミックの影響により多くの国々で送金フローが減少したとされています。日本においても同様であり、2020年の送金フローは2019年に比べて減少したと考えられています。この減少は、経済政策の影響や経済状況の悪化などが原因となっていると考えられています。 -
「持続可能な開発目標 (SDGs報告) 2021」 によると、2020年の正味政府開発援助(ODA) 総額は過去最大の1610億ドルであった。 これ は、ドナー国の国民総所得 (GNI) の 0.32%に相当し、 目標であるGNIの0.7%には届いていない。
⇒☓「持続台可能な開発目標(SDGs報告) 2021」には、2020年の正味政府開発援助(ODA)の総額に関する具体的な数値は記載されていません。ODAに関連する情報や統計は、多様な国際機関によって提供されており、最新の情報は各国の政府や関連機関にお問い合わせいただくか、ODAに関連する専門サイトなどで確認することができます。 -
SDGsターゲット17.6で触れられている科学技術イノベーション 「STI」 とはSaience, Technology and Innovation を指す。
⇒〇 -
国連貿易開発会議 (UNCTAD) が発表した 「世界投資報告2021」 によると、 新型コロナウイルスの影響で、 2020年の世界の直接投資は、金 融危機下の2009年を約20%割り込む水準に縮小した。 この理由についてUNCTADは、 新型コロナウイルスへの対応として世界中でロックダ ウンが実施されたことで既存の投資プロジェクトに遅れが生じたことや、 景気後退の見通しが多国籍企業に新規投資プロジェクトの見直しを 促したことにより対内直接投資額が減少したことを指摘している。
⇒〇
問題12 (No.2)
2021年6月14日、SDSN (国連持続可能な開発ソリューションネットワーク)は、世界165カ国のSDGsに関連する取り組み状況を分析した年次報告 書 「SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2021」 を発表しました。 これに関連する次の文章のうち、 その内容が最も適切なものを選択してくだ さい。
なお、当該REPORTは、各国におけるSDGsのゴール別の達成度を、 SDG achievement (目標達成) Challenges remain (課題が残っている)、 Significant challenges remain (重要な課題が残っている)、Major challenges remain (主要な課題が残っている) に区別している。 順に深刻なも のとなっている。
- 日本において Major challenges remainに区分されているゴールは、ゴール5 (ジェンダーの平等)、ゴール13(気候変動)、ゴール14(海 の豊かさ)、ゴール17 (パートナーシップ) の4つであった。
⇒× - 2021年度のSDGsの達成度において日本のランキングは過去最高位であり、年々上昇している。
⇒× - 当該REPORTはSDGsインジケーター(指標) ごとの達成度を公表していない。
⇒× - SDGsの達成度の2021年度の世界ランキングは1位フィンランド、 2位スウェーデン、3位デンマークと北欧が占め、 日本は18位であった。
⇒〇 - 日本においてSDG achievementに区分されているゴールは、ゴール1 (貧困)、ゴール4 (教育)ゴール9(産業と技術革新)、ゴール16 (公正) の4つであった。
⇒×
問題13 (No.26)
SDGsゴール15 「陸の豊かさも守ろう」 のうち、 環境省 「令和3年版 環境 循環型社会・生物多様性白書」 にある生物多様性に関連する次の文章の うち、その内容が最も誤っているものを選択してください。
-
2019年5月に生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム (IPBES) が公表した 「生物多様性と生態系サービス に関する地球規模評価報告書」 は非常に厳しい現実を世界に突き付けた。 自然の保全と持続可能な管理の取組は進んでいるものの、それらは 不十分であること、 生物多様性が人類史上これまでにない速度で減少し、 生態系から得られる恵みが世界的に劣化していることが示された。
⇒〇 -
愛知目標に続く2021年以降の世界目標となる 「ポスト2020生物多様性枠組」 は、 2020年10月に中国昆明で開催される生物多様性条約第 15回締約国会議(COP15) で採択される予定だったが、 新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を受けてCOP15 は延期された。
⇒〇 -
2020年は、 生物多様性の保全と持続可能な利用に関する国際目標である 「愛知目標」 の最終年であった。 愛知目標は、2050年までの長期目 標 (ビジョン) である 「自然と共生する世界」 を実現するための17の行動目標であり、 2010年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条 約第10回締約国会議 (COP10) で採択された。
⇒×2050年までに「自然と共生する世界」を実現することをめざし、2020年までに生物多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急の行動を実施するという20の個別目標です。 -
2020年9月に生物多様性条約事務局がまとめた 「地球規模生物多様性概況第5版 (GBO5) 」 では、 愛知目標の最終評価として、ほとんどの目 標に進捗が見られたものの、 完全に達成できたものはないとされた。
⇒〇
問題14 (No.10)
SDGsゴール5 「ジェンダーの平等を実現しよう」 に関する記述です。 次の文章のうち、その内容が最も誤っているものを選択してください。
-
日本の上場企業内の女性の役員数は着実に増加しており2012年からの9年間で約4.8倍に増えているが、 OECDの調査によれば上場企業役員に 占める女性の割合は2020年時点でG7では最下位、 OECD加盟国全37カ国中32位と国際的に見ると低い水準となっている。
⇒〇 -
OECDの2021年版 「図表でみる教育」 によれば2019年の高等教育機関の教員に占める女性の割合はOECD平均が44%であるのに対し、 日本 は28%となっており比較可能な34カ国で最下位である。
⇒〇 -
2016年に総務省が行った調査によると、日本では6歳未満の子どもを持つ家庭で夫が1日に家事・育児などに費やす時間は妻が費やす時間の5 分の1以下となっており他の先進国と比較しても少ない。
-
OECD(経済協力開発機構) が公表している2018年度における男女間の賃金格差の統計によると、 日本はOECD諸国の平均よりも賃金格差が 小さい。
⇒×世界で3位 -
世界経済フォーラムが公表している2021年のジェンダーギャップ指数では日本は極めて低い順位にあるが、これは政治分野においてスコアが 低調となっていることが大きな要因となっている。
⇒〇120位。日本は、特に、「経済」及び「政治」における順位が低くなっており、「経済」の順位は156か国中117位(前回は115位)、「政治」の順位は156か国中147位(前回は144位)となっています。政治分野では、スコアは上がっているものの、順位は下がっています。これは、各国がジェンダー平等に向けた努力を加速している中で、日本が遅れを取っていることを示しています。
問題15 (No.24)
SDGsゴール14 「海の豊かさを守ろう」 のうち、 環境省 「令和3年版 環境 循環型社会・生物多様性白書」 にある国の循環経済に向けた政策に関連 する次の文章のうち、 その内容が最も誤っているものを選択してください。
-
プラスチックの資源循環については、大きく三つの施策の検討を進めている。 第一に、 「プラスチック資源循環戦略」の具体化で、 2021年3 月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」を閣議決定し、 第204回国会に提出した。 第二に、 バイオプラスチック導入口 ードマップの策定で、 2021年1月に「バイオプラスチック導入ロードマップ」 が策定された。 第三に、 プラスチック資源循環分野のESGガイ ダンスの策定で、 2021年1月に 「サーキュラーエコノミーに係るサステナブル ファイナンス促進のための開示 対話ガイダンス」 が策定された。
⇒×2022年1月に 「サーキュラーエコノミーに係るサステナブル ファイナンス促進のための開示 対話ガイダンス」 -
循環経済 (サーキュラーエコノミー)とは、従来の3Rの取組に加え、 資源投入量消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、 サービ ス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、 資源 製品の価値の最大化、 資源消費の最小化、 廃棄物の発生抑止等を目指すものである。
⇒〇 -
日本においては、循環型社会形成推進に関する各種制度の下、 行政 経済界 国民等の各主体の協同により3R及び循環経済の実績を積み上げ ている。 また、2021年1月、 環境省と経団連は、 循環経済の取組の加速化に向けた官民連携による 「循環経済パートナーシップ」を立ち上げ ることに合意し、 3月に同パートナーシップが発足した。 さらに、 2021年3月、 環境省は世界経済フォーラム (WEF) と共に 「循環経済ラウ ンドテーブル会合」 を開催し、日本企業の循環経済に関する技術や取組を世界に発信した。
⇒〇 -
2019年6月に開催されたG20大阪サミットにおいて、日本は2050年までに海洋プラスチックごみをゼロにまで削減し、 海洋汚染を無くすこと を目指す 「大阪ブルーオーシャン・ビジョン」 を提案し、 首脳間で共有された。 他国や国際機関等にもビジョンの共有を呼びかけ、2021年 5月現在、 87の国と地域が共有している。
⇒〇
問題16 (No.11)
SDGsゴール6 「安全な水とトイレを世界中に」 について述べた次の文章のうち、 その内容が誤っているものの個数を選択してください。
- 水資源として利用可能な水量は、 降水量の変動等により絶えず変化するものであり、 また、 地域的には、毎年のように発生する大雨・干ばつ等 の異常気象が、 水の利用可能量に大きな影響を及ぼす。 将来的に懸念される問題点として、 例えば人為的な要因による酸性雨や地球温暖化等の気候 変動が水資源に与える影響が挙げられる。
⇒〇 -
国連食糧農業機関(FAO) のデータベース 『AQUASTAT』 によると、 2017年頃の世界の水使用量は約4,000km/年となっており、地域別にみる と、ヨーロッパでの使用量が最も多く、 続いてアメリカ、アジアの順となっている。
⇒×国連食糧農業機関(FAO) のデータベース『AQUASTAT』によれば、世界で最も水使用量の多い地域は中東・北アフリカ地域です。この地域は、砂漠地帯が多いため、農業などの用途に向けて人工的に灌漑された水を使用する必要があり、水使用量が多いという特徴があります。また、この地域は、石油資源などの豊富なエネルギー資源からも多くの金を生み出しているため、水使用施設の整備なども進んでおり、水使用量の増加に貢献しています。 -
『OECD Environmental Outlook to 2050』 によれば、 世界の水需要は、 製造業、 火力発電、 生活用水などに起因する需要増により、 2050年ま でに55%程度の増加が見込まれている。
⇒〇 -
ゴール6には2030年までに、 汚染の減少、 投棄の廃絶と有害な化学物質の放出の最小化、 未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用を 世界的規模で大幅に増加させることにより、 水質を改善することと定められている。
⇒〇