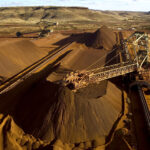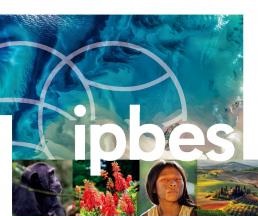
A. 自然とその人々への重要な寄与(生物多様性と生態系の機能やサービスとも表現される)は、世界的に悪化している。
自然(Nature)は、生物多様性や生態系、母なる地球(Mother Earth)、生命システムなど、人それぞれに違う捉え方をされている概念を包含する。自然の寄与(nature’s contribution to people:NCP)は、生態系の財やサービス、自然の恵みのような概念を包含する。自然と自然の寄与(NCP)は、人間の存在と良質な生活(人間の福利、自然との共生、母なる地球と調和した豊かな生活など)に欠かせない。今日、世界各地に過去に例をみないくらい大量の食料、エネルギーや物資が供給されている反面、多くの場合、自然が将来にわたって同様の寄与を提供し続ける能力、ならびに水質浄化から場所性(sense of place、人にとって場所がもつ重要性のこと)に至るまで、他の多くの寄与が損なわれている。人類にとって欠かすことのできない生物圏は、あらゆる空間規模で、これまでにない程に改変されている。生物多様性、すなわち同一種内の(遺伝的)多様性、種の多様性、生態系の多様性は、人類史上これまでにない速度で減少している。
A1 自然は、人類の生存と良質な生活に欠かせない。
自然の寄与(NCP)の大部分は完全に代替することは不可能で、全く代替できないものもある。自然は、食料や飼料、エネルギー、薬品や遺伝資源、ならびに人々の身体的健康と文化の維持に欠かせないさまざまな資源を供給するという極めて重要な役割を担っている。例えば、20 億人を超える人々が 1 次エネルギーを木質燃料に依存し、推計 40 億人が医療・健康のために主に自然由来の薬を利用し、がん治療薬のおよそ 70% は自然由来または自然界から着想を得た合成製品である。自然は、その生態学的プロセスや進化のプロセスを通じて、人類にとって欠かせない大気、淡水と土壌の質を保ち、淡水を供給し、気候を調節し、授粉と害虫抑制に貢献し、自然災害の影響を緩和する。例えば、世界の食料作物の種類のうち 75% 以上は動物による花粉媒介に依存している。これには果物と野菜、コーヒー、カカオ豆、アーモンドといったいくつかの重要な換金作物が含まれている。海域と陸域の生態系は人類が排出する炭素の唯一の吸収源であり、その量は年間 56 億トンにのぼる(世界全体の人為的排出量のおよそ 60% に相当)。自然は人の健康をあらゆる面で支え、非物的側面でも良質な生活に寄与している。こうした寄与には、生活の質や文化的一体性に欠かせない発想(インスピレーション)や学習、身体的・心理的経験、アイデンティティ形成が含まれるが、これらの総合的な価値の定量評価は容易ではない。自然の寄与の多くは人間と共同生産されていて、知識と制度、技術インフラおよび金融資本といった人為的資産によって増幅または部分的に代替できるものもあるが、中には一部たりとも代替できないものもある。自然の多様性は人類の不確実な未来に複数の選択肢を与えている。
A2 自然の寄与(NCP)は、多くの場合、空間的、時間的、そしてさまざまな社会階層の間に偏在している。
また、自然の寄与(NCP)の生産と利用との間にはしばしば相反性(トレードオフ)が生じる。自然の寄与の生産と利用に関わる利益や負担は、社会集団、国や地域の間でさまざまな分配や捉え方をされる。例えば食料生産など、1 つの自然の寄与(NCP)を優先すると、他の寄与を低下させる生態系の変化が起こりうる。生態系のこうした変化は、一部の人々に利益をもたらすために他の人々、特に最も脆弱な人々を犠牲にしたり、技術や制度の変化をもたらしたりする可能性がある。例えば、世界全体でみると今日の食料生産量は十分に需要を満たしているが、世界人口の約 11%は栄養不良状態にある。若年死亡の原因の 20% は食に由来する疾病で、これには栄養不良と肥満の両方が関与している。食料、飼料、繊維、バイオエネルギーの生産が飛躍的に増大した反面、大気質、水質や気候の調節、生息地の提供など、他の種類の自然から生活の質への寄与の多くが低下している。一方では、持続可能な農法によって土壌が改善し、生産性向上のみならず炭素貯留や水質調節のような他の生態系機能とサービスが向上するような相乗性(シナジー)もある。
A3 農業、漁獲漁業、バイオマスエネルギーおよび材料の生産量は 1970 年以降増加傾向にあるが、本評価報告書で評価した 18 項目の自然の寄与 2 のうち、調節的寄与や非物的寄与を中心に 14 項目は減少傾向にある。
農作物生産額は 1970 年比で 3 倍(2016 年に 2.6兆ドル)に増加、原木の生産量は 45% 増加して 2017年には約 40 億㎥に達し、森林産業に約 1,320 万人の雇用を生んだ。一方で土壌有機炭素や花粉媒介者の多様性といった調節的寄与の指標は低下した。これは物的寄与の増加がしばしば非持続的であることを示している。現在、土地劣化により世界の陸地面積の 23% では生産性が低下し、花粉媒介者の減少によって世界の年間作物生産額の 2,350 億ドルから 5,770 億ドル相当 3の損失リスクがある。さらに、沿岸の生息地とサンゴ礁の減少により沿岸保護機能が低下し、100 年に 1 度確率の洪水リスクのある沿岸部に住む 1 億人から 3 億人の生命と財産への洪水やハリケーンの脅威が高まっている。
A4 複数の人為的な要因によって、地球上のほとんどの場所で自然が大きく改変されている。
大多数の生態系と生物多様性の指標の急速な低下がこれを裏付けている。世界の陸地の 75% が著しく改変され、海洋の 66%は累積的な影響下にあり、湿地の 85% 以上が消失した。世界全体でみると 2000 年以降森林の消滅が減速したが、その増減は場所によって異なる。豊かな生物多様性を擁する熱帯では、2010 年から 2015 年までの間に3,200 万ヘクタールの原生林や 2 次林が消滅した。熱帯林や亜熱帯林の面積が拡大している国もある。温帯林や寒帯林の面積は総計で拡大している。自然林の再生から単一種の植林に至るまで、さまざまな努力が森林面積の増大に貢献しているが、これによる生物多様性とその人々への寄与への影響は場合によって大きく異なる。1870 年代以降、生きているサンゴ礁の約半分が失われ、ここ数 10 年では気候変動によって他の要因も悪化して、サンゴの減少が加速している。陸域の主要な生物群系(バイオーム)のほぼ全てで、在来種の平均個体群が少なくとも 20% 減少し、生態系のプロセスと自然の寄与(NCP)に影響を与えている可能性がある。この減少傾向の多くは 1900 年以降に始まったもので、加速している可能性がある。固有種が豊富な地域の多くでは、在来の生物多様性が侵略的外来種による深刻な脅威に晒されている。陸域、淡水域および海洋に生息する野生の脊椎動物種の個体群はここ半世紀の間で縮小傾向にある。昆虫類の個体群の世界的な傾向はわかっていないが、いくつかの場所で急速な減少が報告されている。
A5 人間活動の影響により、地球全体でかつてない規模で多量の種が絶滅の危機に瀕している。
本評価報告書で評価した動物と植物の種群のうち平均約 25%(図 SPM.3)が絶滅の危機にある。これは推計 100 万種が既に絶滅の危機に瀕していることを示唆している。生物多様性への脅威を取り除く行動をとらなければ、今後数十年でこれらの種の多くが絶滅する恐れがある。地球上の種の現在の絶滅速度は過去 1,000 万年平均の少なくとも数 10 倍、あるいは数 100 倍に達していて、適切な対策を講じなければ、今後さらに加速するであろう。
A6 栽培植物と家畜の在来種が全世界で失われつつある。
遺伝的多様性を含む多様性の消失は、多くの農業システムの害虫、病原体、気候変動などの脅威に対する強靭性(レジリエンス)を損ない、世界の食料安全保障にとって重大な脅威になる。先住民や地域コミュニティによる保全などの局所的な取り組みはあるが、世界全体でみると栽培、育成、取引、維持されている動物や植物の品種が減少している。食料や農業に利用されている家畜哺乳動物 6,190 品種のうち 559 品種(9% 超)が 2016年までに絶滅した。さらに、少なくとも 1,000 品種が絶滅の危機に瀕している。加えて、長期的な食料安全保障に重要な作物の近縁野生種の多くは十分に保護されておらず、家畜哺乳類・鳥類の近縁野生種の保全状態は悪化している。栽培作物、作物の近縁野生種および家畜品種の多様性の減少は、今後の気候変動、害虫や病原体に対する農業生態系の強靭性(レジリエンス)の低下を意味する。
A7 管理下にある生態系と管理下にない生態系の両方で、生物群集が地域内および地域間で均質化しつつある。
この人為的な変化により、固有種、生態系機能、自然の寄与(NCP)を含む地域固有の生物多様性が減少している。
A8 人間が引き起こした変化は、急速な生物学的進化の条件を生み出している。
その変化の影響はほんの数年、あるいはより短い期間で現れる可能性がある。こうした進化は生物多様性と生態系に正または負の影響を与えることがあり、種、生態系機能および自然の寄与(NCP)の維持に不確実性を生じさせる可能性がある。最新の情報に基づく政策決定のためには、生態学的な変化の理解とモニタリングに加えて、生物学的な進化による変化を考慮することが重要である。そのような情報は、進化の過程を考慮した脆弱な種の保護、ならびに雑草、害虫や病原体などの望まれない種の影響を軽減する持続可能な管理戦略づくりに欠かせない。多くの種の広範囲にわたる地理分布と個体群サイズの縮小は、人為的変化への種の進化的適応がいくら速いとはいっても、種の地理分布や個体群サイズの縮小が完全に食い止められるわけでないことを明示している
B. 直接的、間接的な変化要因が過去 50年で増大している
過去 50 年の間、人類史上かつてない速度で地球全体の自然が変化している。この変化の直接要因は、影響が大きい順に、土地と海の利用の変化、生物の直接採取(漁獲、狩猟含む)、気候変動、汚染、外来種の侵入である。これら 5 つの直接要因は、さまざまな根本的な原因(間接的な変化要因)によって引き起こされる。さらに根本的な原因の背景には、生産・消費パターン、人口の動態と推移、貿易、技術革新および現地(ローカル)から全世界にかけてのガバナンスなどといった社会の価値観や行動がある。直接要因と間接要因の変化の速度は地域や国によって異なる
B1 陸域と淡水域の生態系では、1970 年以降土地利用変化の影響が最も大きく、次いで収穫や狩猟、伐採、漁獲漁業などによる動物、植物やその他の生物の乱獲のような直接採取の影響が大きい。
海洋生態系では、漁獲漁業に代表される生物の直接採取の影響が最も大きく、次いで土地や海域の利用変化の影響が大きい。最も顕著な土地利用変化は農地拡大によるもので、陸地の 3 分の 1 以上が作物栽培か畜産に利用されている。このほとんどは森林(多くが熱帯の老齢林)、湿地や草地から転換されたもので、1992 年以降の都市面積の倍増、および人口と消費の増加に伴う今までになく急速なインフラの拡大と同時並行で進んでいる。淡水生態系の多くは、水利用を含む土地利用変化、漁獲漁業、汚染、気候変動や侵略的外来種といった一連の要因の複合的な影響下にある。人間活動は、世界の海洋に広く深刻な影響を及ぼしている。その例には、魚介類の直接採取(特に乱獲)、河川水系を含む陸域と海洋の汚染、ならびにインフラや養殖のための沿岸開発などの土地利用、海域利用の変化が挙げられる。
B2 気候変動は直接要因の 1 つであるだけでなく、他の直接要因の影響を増幅して自然と人間の福利への影響をさらに悪化させている。
産業革命前から 2017 年までの間に起こった 1.0℃の気温上昇は人間活動に由来すると推定されている。ここ 30 年では、平均気温が 10年に 0.2℃の速度で上昇している。極端気象現象やこれに伴う火災、洪水や干ばつの頻度と強度は過去 50 年間で増加傾向にある。世界の平均海面は 1900 年以降 16~ 21cm 上昇し、最近 20 年間では年間 3mm を超える速度で上昇している。これが種の分布、生物季節、個体群動態、群集構造、生態系機能といった生物多様性の多くの側面に影響している。観測結果によると、その影響は海洋生態系、陸域生態系および淡水生態系で増加傾向にあり、すでに農業、養殖業、漁業および自然の寄与(NCP)に影響している。気候変動、土地と海域の利用変化、資源の乱獲、汚染および侵略的外来種といった変化要因の複合的影響は自然への悪影響をさらに深刻化させる可能性があり、こうした影響は既にサンゴ礁、北極システムやサバンナのようなさまざまな生態系で顕在化している。
B3 多くの種類の汚染と侵略的外来種が増加傾向にあり、自然に悪影響を及ぼしている。
世界全体ではさまざまに異なる傾向がみられるが、一部の地域で大気、水、土壌の汚染が悪化し続けている。特に海洋プラスチック汚染が 1980 年から 10 倍に増加し、ウミガメの 86%、海鳥の 44%、海洋哺乳類の 43% の種を含む少なくとも267 種に影響を与えている。さらに、これは食物連鎖を通じて人にも影響する可能性がある。温室効果ガス排出、都市や農村から出る未処理の廃棄物、製造業、鉱山採掘および農業から排出される汚染物質、石油の流出、ならびに有害物質の投棄は、土壌、淡水、海水の質と地球の大気に著しい悪影響を与えている。外来種の累計数は、貿易量の増加および人口の動態と推移に伴って、1980年以降 40% 増加した。地球の表面の 5 分の 1 近くは植物や動物による侵略の危機に晒されていて、経済や人々の健康だけでなく、在来種、生態系機能と自然の寄与(NCP)にも影響を与えている。新たな侵略的外来種の拡大はこれまでにない速さで進んでいて、悪化の一途を辿っている。
B4 この 50 年間で世界人口は倍増、世界経済は 4 倍近く成長、世界貿易は 10 倍に増加し、これらが組み合わさってエネルギーと物資の需要を増大させている。
国際貿易および生産地と消費地の距離拡大を含むさまざまな経済、政治、社会要因が、生産と消費に伴う経済、環境面の利益と負担の分配を変化させた。これが新たな経済機会を生むだけでなく、自然と自然の寄与(NCP)に影響している。食料、飼料、木材や繊維などの物的な財の消費量は非常に多様で、物的な財へのアクセスの偏りが不平等を生み、社会紛争の原因を生む恐れがある。経済的な取引は全体的な経済発展に寄与するが、多くの場合、力関係が対等でない主体や組織の間の交渉が利益分配や長期的な効果に影響する。国の発展の程度によって、経済成長によって得られる利益と引き換えに生じる自然劣化の程度には差がある。自然の寄与(NCP)へのアクセスからの排除、不足や不平等な分配が他の要素と複雑に相互作用して、社会不安や紛争を助長する可能性がある。武力衝突は、社会不安を引き起こすだけでなく生態系にも直接影響を与える。さらに人々や活動の移転を含むさまざまな間接要因を生むことで生態系に影響する。
B5 経済的インセンティブの多くは環境の保全や再生よりも経済活動の拡大を優先し、環境を損ねている。
生態系の機能と自然の寄与(NCP)がもつ多様な価値を考慮した経済的インセンティブが、生態学的、経済的および社会的な側面でより良い結果をもたらすことがわかっている。地方、国、地域や世界のガバナンスとこれに支えられた政策、革新、環境に有害な補助金の廃止、自然の寄与(NCP)の価値を考慮したインセンティブの導入、持続可能な土地と海域の利用の管理強化、規制の遵守執行などがこのような良い成果を生んでいる。持続不可能な漁獲漁業、水産養殖、農業(肥料や農薬の使用など)、畜産業、林業、鉱山採掘やエネルギー(化石燃料やバイオ燃料など)を助長する有害な経済的インセンティブや政策の多くは、非効率な生産と廃棄物管理の原因となるだけでなく、土地と海域の利用変化、自然資源の過剰採取の原因にもなっている。既得権者は補助金の廃止や別の政策の導入に反対するかもしれない。しかし、自然の寄与(NCP)の多様な価値のよりよい理解に基づいた政策のような、環境への害の原因を解消する政策改革によって、自然の保全と経済的利益を両立できる可能性がある。
B6 先住民や地域コミュニティが管理する自然への脅威が高まっている。
先住民の土地では他の土地に比べて自然の減少が緩やかな傾向があるが、こうした土地においても、自然を管理する知識とともに自然が失われつつある。世界の土地面積の少なくとも 4 分の 1 は古くから先住民が所有、管理、使用または占有する土地である。このような土地は保護区面積の約 35%、保護区外で人為的影響が極めて小さい陸地面積の約 35%を占めている。さらに、農民、漁民、遊牧民、狩猟民、牧場経営者や森林利用者を含む多様な地域コミュニティは、さまざまな財産制度や利用制度の下、広大な土地や海域を管理している。先住民や地域コミュニティが開発、使用する局所的な指標の 72% は、地域の生計と人間の福利の基盤となる自然の劣化を示している。先住民や地域コミュニティがさまざまな形の所有・利用制度の下で管理する土地や海域では、資源採取、商品の生産、鉱山採掘、および輸送やエネルギーのインフラ整備が拡大していて、地域の人々の生計と健康にさまざまな影響を与えている。気候変動緩和事業の中には、先住民や地域コミュニティに悪影響を与えたものもある。これらの悪影響には、森林減少、湿地の消滅、鉱山採掘および持続不可能な農業、林業、漁業の拡大による生産手段や伝統的な生計手段の継続的な喪失、ならびに汚染と水不足による人々の健康と福利への影響などが含まれる。このような影響はまた、伝統的な管理、先住民や地域住民の知識の継承、ならびにより広い社会に関わりのある野生または栽培・飼育下にある生物多様性を先住民や地域コミュニティが保全し持続的に管理する能力とその利用による利益分配の可能性を損なう。
C. 自然の保全と持続可能な利用、および持続可能な社会の実現に向けた目標は、このままでは達成できない。
2030年以降の目標の達成に向けて、経済、社会、政治、技術すべてにおける変革(transformative change) が求められる過去から現在にかけて生物多様性、生態系機能および自然の寄与(NCP)が急速に減少しており、このままでは愛知目標や SDGs が掲げる社会や環境に関する国際的な目標の大方は達成できない。この減少傾向は、国連気候変動枠組条約のパリ協定や生物多様性条約の 2050 年ビジョンなど、他の目標の達成も阻む。急速な人口増加、持続不可能な生産 ・ 消費とこれらを助長する技術開発といった間接要因を想定した将来シナリオの多くで、生物多様性と生態系機能の減少傾向が悪化することが予測されている。一方、低から中程度の人口増加、エネルギー、食料、飼料、繊維および水の生産と消費の変革、持続可能な利用と公平な利益分配、自然にやさしい気候変動適応策や緩和策の導入を想定した将来シナリオは、社会と環境の将来目標を達成できる可能性があることを示している。
C1 自然の保全と持続可能な管理のための政策の実施や行動は前進しており、行動を起こさなかった場合のシナリオに比べると成果は出ている。
しかし自然の劣化を引き起こす直接、間接の要因を大幅に減らすには不十分で、愛知目標の大部分は達成できない可能性が高い。愛知目標のうち、陸域と海域の保護区面積、侵略的外来種の特定と優先度の設定、生物多様性国家戦略、ならびに生物多様性条約の遺伝資源の取得の機会およびその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書といった政策対応に関するものを含むいくつかの目標は部分的に達成される見込みである。しかし、保護区によって現在陸域と淡水域の 15% と海域の 7% が保護されているにも関わらず、生物多様性に重要な場所の保護は非常に限定的で、さまざまな重要な生態系を網羅するには不十分であり、管理の効果や公平性も十分ではない。生物多様性条約を支援する政府開発援助と地球環境ファシリティ(Global Environment Facility)による資金供与は大幅に増加し、生物多様性への資金協力は合わせて年間 87 億米ドル近くに達している。しかしながら、現在ある資源を総動員しても、愛知目標の達成には足りない。さらに、自然や地球環境の保護に関する 6 つの国際条約 6が掲げる 5 つの戦略目標のうち、達成が見込まれるのは 1 つの目標だけである。これらの条約が掲げる目標の 3 分の 1 近くについては、進捗がないかあってもほんのわずか、あるいは目標達成から遠ざかっている。
C2 SDGs の達成には自然が欠かせない。
しかし、SDGs は統合的で個別に切り離せない、国ごとに実施される目標であることを考慮すると、現在の生物多様性と生態系の悪化傾向は、貧困や飢餓、健康、水、都市、気候、海洋と陸地に関連する目標(目標 1、2、3、6、11、13、14、15)の 80%(44 のうち 35)のターゲットの達成に向けた前進を妨げている。教育、ジェンダー平等、不平等の是正および平和と正義の促進(SDGs 4、5、10、16)の目標と自然との間には重要な相乗性がある。自然の劣化とともに、土地や資源の所有権が保障されていないことが、しばしば脆弱な立場にある女性や女児に大きな影響を与える。しかし、これに関連するSDGs の目標やターゲットの今ある記述には女性や女児と自然との関わりについて言及がない、あるいはあっても曖昧なため、この関係について評価できない。SDGs達成に自然の変化がどう影響するのかを効果的に追跡するためには、自然とその人間の福利との関係をより明示的に説明する将来の政策目標、指標とデータが特に必要である。エネルギー、経済成長、産業とインフラおよび持続可能な消費と生産(SDGs 7、8、9、12)に関する目標、ならびに貧困、食料安全保障および都市(SDGs 1、2、11)に関するターゲットの達成に向けた経路の中には、自然に正または負の大きな影響を与え、従って他のSDGs の達成を左右しかねないものもある。
C3 地球全体の気候、生物多様性、生態系機能および自然の寄与(NCP)の変化による深刻な悪影響を受けると予測されている地域には、先住民や最貧層のコミュニティが集中している。
こうした人々の生活、生計と健康は自然と自然の寄与に大きく依存しているため、特に悪影響を受けやすい。このような悪影響はまた、先住民や地域コミュニティが野生または栽培・飼育下にある生物多様性と自然の寄与を管理・保全する能力にも影響を与える。こうした課題を克服するために、先住民や地域コミュニティは、住民同士または他のさまざまな関係者との協力に基づく共同管理体制、現地または地域のモニタリングネットワーク、現地の管理体制の再生と順応に積極的に取り組んできた。地域や世界レベルのシナリオには、先住民や地域コミュニティのもつ視点、捉え方や権利、広範囲の地域や生態系についての知識や理解、ならびに将来望む発展経路が明示的に考慮されていない。
C4 社会変革(transformative change)を想定しない将来シナリオでは、陸域と海洋の利用変化、生物の直接採取および気候変動が進み、その影響で自然、生態系機能および多くの自然の寄与(NCP)の悪化傾向が2050 年以降も継続すると予測されている。
汚染と侵略的外来種の影響はこの傾向をさらに悪化させると予想されている。将来予想される生物多様性と生態系機能の分布、ならびに自然の寄与(NCP)の消失や変化は地域によって大きく異なる。こうした地域差は、直接、間接の変化要因がそれぞれの地域に異なった形で影響するために生じる。今後、世界中の地域で生物多様性がさらに減少することが予測されているが、特に熱帯地域は、気候変動、土地利用変化と漁業資源利用の相互作用による複合的リスクに晒される。北方、亜極および極地域では、主に気温上昇、海氷後退と海洋酸性化によって海洋と陸域の生物多様性が減少すると予測されている。消費または人口の急増を想定したシナリオでは、持続可能なシナリオに比べてこうした影響の強度や地域差が大きい。複数の間接・直接要因に対して直ちに、そして同時に行動を起こすことで、複数の側面で生物多様性と生態系の減少を緩和または防止する、あるいは増加に反転させる可能性がある。
C5 気候変動が、自然と自然の寄与(NCP)の変化の直接要因として今後数 10 年でますます重要になることが予測されている。
SDGs と生物多様性に関する2050 年ビジョンの達成のために、将来の目標や目的の設定に気候変動の影響を考慮することが欠かせないことを、シナリオ分析の結果が示している。シナリオや地域によって相対的な差はあるが、気候変動の影響が今後数十年でますます顕著になることが予測されている。どのシナリオも、気候変動が生物多様性と生態系機能に概して負の影響を及ぼすと予測している。このような影響は地球温暖化の進行に伴って、または場合によって、急激に悪化する。地球上の気温上昇が 1.5℃から 2℃の範囲であっても、大半の陸上生物の分布域が大幅に縮小すると予測されている。種の分布域が変化すると保護区による保全が難しくなり、局所的な種の入れ替わりが顕著になり、ひいては地球規模で絶滅リスクを大幅に高める可能性がある。多数の研究結果を総合分析した結果によると、気候が原因の絶滅リスクに晒される種の割合は、2℃上昇で 5%、4.3℃上昇で 16% にのぼると予測されている。サンゴ礁は特に気候変動の影響に脆弱で、1.5℃上昇で従来の 10% ~ 30%、2℃上昇シナリオでは 1% 未満の面積にまで縮小することが予測されている。シナリオはこのように、地球温暖化を 2℃より大幅に低く抑えることが、自然と自然の寄与(NCP)を大きく損なわないために決定的に重要であることを示している。
D. 自然の保全、再生、持続的可能な利用と世界的な社会目標
自然の保全、再生、持続的可能な利用と世界的な社会目標は、社会変革に向けた緊急で協調した努力によって同時に達成することができる既にある政策手段の改良と迅速な導入、および社会変革に求められる個人と集団の行動をより効果的に促す新たなイニシアティブにより、食料、水、エネルギー、人間の健康と福利、気候変動の緩和と適応、自然の保全と持続可能な利用を含む社会目標を持続可能な経路で達成することができる。現在の構造は持続可能な発展を阻み、それ自体が生物多様性減少の間接要因になっている。従ってこの根本的、構造的変化が求められている。社会変革には既得権者からの反対がつきものであるが、これはより広い公益のために克服できる。このような障壁を克服できれば、相互補完的な国際目標とターゲットへの取り組み、現地での先住民や地域コミュニティの協力、民間部門投資と技術革新の新たな枠組、包摂的で順応的なガバナンスのアプローチと体制、部門横断的な計画および戦略的な政策を組み合わせることで、現地、国、世界の規模で持続可能性を実現するための公共部門と民間部門の変革を促すことができる。
D1 国際協力の強化と、これに協調して現地の状況に即した対策によって、地球環境を守ることができる。
その実践の鍵となるのが、入手可能な最高の科学的知見にもとづく環境関連の国際目標やターゲットの評価と更新、ならびに個人を含むあらゆる主体による保全、生態系再生および持続可能な利用に向けた行動と資金協力の拡大である。こうした行動と資金協力の拡大はすなわち、持続可能性に向けた現地、国および国際の取り組みの前進と協調、ならびに鉱業、漁業、林業や農業を含むすべての採取・生産セクターへの生物多様性と持続可能性の主流化を意味している。これらに加えて、個人と集団が行動することで、世界全体の生態系サービスの劣化傾向を反転させることができる。しかし、自然劣化の直接要因をこのように大胆に変化させるためには、間接要因にも働きかける社会変革(transformative change)が求められる。
D2 社会変革は、自然劣化を引き起こす間接要因に作用する 5 つの主な介入(レバー)によって引き起こせる。
これらは、(1)インセンティブと能力構築、(2)部門横断的な協力、(3)先制行動、(4)強靭性(レジリエンス)と不確実性を考慮した意思決定、(5)環境法とその執行である。これらの介入の実施には次のような取り組みが必要である:(1)環境責任のためのインセンティブと幅広い能力の開発ならびに逆効果をもたらすインセンティブ(perverse incentives)の廃止、(2)部門や管轄を超えた統合を促進するための、部門ごとに分断された意思決定の見直し、(3)自然の劣化を回避、緩和、改善するための規制や管理の制度と事業における先制的、予防的な行動と、それらのモニタリング、(4)さまざまな状況(シナリオ)下にも通じる意思決定をするための、不確実性と複雑さの中でも強靭(レジリエント)な社会生態システムの管理、(5)環境法、政策とその推進、ならびに法の支配一般の強化。特に多くの途上国にあるような能力不足の状況では、これら 5 つの介入の全てに新たな資源が求められるであろう。
D3 努力が非常に大きな効果を生む次のような重要な介入点(レバレッジ・ポイント)に注力することで、持続可能性への転換がより起こりやすくなる
(1)豊かな暮らしのビジョン、(2)消費と廃棄の総量、(3)価値観と行動、(4)不平等、(5)保全における正義と包摂性、(6)外部性とテレカップリング、(7)技術、革新と投資、(8)教育および知識の形成と共有。特に、以下のような変化は相互補完的である:(1)物の消費増大を伴わない良質な生活のビジョンを持てるようにすること、(2)消費量と廃棄物の総量の削減(人口増加と 1 人当たり消費量の両方に、状況に応じた適切な方法で対応することを含む)、(3)人々が普通に持っている「責任」感の及ぶ範囲を推し広げ、持続可能性に資する新たな社会規範を形成する(特に消費に伴う影響に対する責任の考え方の拡張)、(4)持続可能性を阻む不平等の解消(特に所得とジェンダーに関わる不平等)、(5)包摂的な意思決定ならびに保全意思決定における人権の行使と遵守から生じる利益の公正で平等な分配の確保、(6)地域における経済活動や距離を隔てた社会経済と環境の相互作用(テレカップリング、たとえば国際貿易により引き起こされる影響)の考慮、(7)再発(リバウンド効果)の可能性や投資環境を考慮した環境にやさしい技術と社会の革新の確保、(8)多様な知識体系の教育や知識生産、維持の推進(自然と自然の保全と持続可能な利用に関する科学や先住民や地域住民の知識を含む)。
D4 直面する課題やニーズの違いに応じて、変革の性質や経路は異なる。
とりわけ途上国と先進国との間で大きな違いがある。持続可能性への変革は不確実性と複雑さに起因するリスクを伴うが、このリスクは統合的、包摂的で情報に基づく順応的なガバナンスアプローチにより軽減できる。そのようなアプローチは通常、複数の社会目標や経路の相乗性(シナジー)と相反性(トレードオフ)、ならびに社会における価値観の多様性、経済状況の違い、不公平、権力の不均衡、既得権益を考慮している。リスクを軽減するための戦略には、予防策と新旧の知識を組み合せた実践の経験からの学習が含まれる。またこのようなアプローチでは、関係者部門を越えた政策の協調、ならびに戦略的で地域に合った有効な政策手段の組み合わせづくりに関係者(ステークホルダー)が参加する。民間部門は、国や地方政府、市民社会といった他の主体と連携して重要な役割を果たすことができる。水部門での官民連携が SDGs 達成のための資金調達に果たす役割はその良い例である。有効な政策手段には、さまざまな生態系を網羅して効果的につながっている保護区ネットワークと保護区以外の効果的な空間的保全策(other effective area-based conservation measures : OECM)の拡大と強化、流域の保護、および汚染を減らすインセンティブと制裁が含まれる。
D5 先住民や地域コミュニティの知識、革新、慣習、制度と価値観を評価すること、および環境ガバナンスへの受け入れや参加を保障することが、先住民や地域コミュニティの生活の質の向上、さらには広く社会に関係する自然の保全、再生と持続可能な利用に貢献することが多い。
先住民や地域コミュニティが参加する、慣習的な自然管理の制度やシステムを含むガバナンスや共同管理体制(co-management regime)は、現地に即した自然管理のシステムと先住民や地域住民の知識を取り入れることによって、自然と自然の寄与(NCP)を守るための効果的な方法になりうる。国による国内法に則った土地所有権、アクセスおよび資源の権利の保障、自由意思による事前の十分な情報に基づく同意(free, prior and informed consent : FPIC)の実行、連携の強化、資源利用から生じる利益の公平で公正な分配、および地域コミュニティとの共同管理体制により、持続可能性に向けた先住民や地域コミュニティの積極的な貢献を促すことができる。
D6 人類の食料を確保することと自然を保全して持続的に利用することは補完的で密接に相互依存する目標であり、持続可能な農業、水産養殖および畜産のシステム、在来の種、品種、系統および生息地の保護、ならびに生態系の再生によって実現できる。
具体的な行動には、ランドスケープの多機能性を考慮したランドスケーププランニングと部門横断の統合的管理のような、持続可能な農業や農業生態学的手法の促進が挙げられる。このような行動は、遺伝的多様性やそれと関わる農業生物多様性の保全に貢献する。この他、状況に応じた適切な気候変動緩和・適応策、科学と先住民や地域に根差した持続可能な手法を含む多様な知識体系の活用、食品廃棄の防止、サプライチェーンの変革に向けた生産者と消費者の権利強化、ならびに持続可能で健康な食品選択の促進により、食料安全保障および生物多様性の保護と持続可能な利用を両立できる。統合的なランドスケーププランニングと管理の一環で、在来種利用を重視した生態系再生を直ちに行うことで、劣化した状態から回復させ、多くの絶滅危惧種を守ることができるが、遅れるとその効果は弱まる。
D7 公海の利用に関する利害関係者の階層を越えた協力を含む、陸域、淡水域および海洋への対策の効果的な組み合わせによって、漁業および海洋の生物種と生態系を維持、保全できる。
具体的な行動には、生態系を基盤とする漁業管理手法、空間計画、効果的な漁獲割当(クォータ)、海洋保護区、海洋生物多様性保全の鍵になる地域の保護と管理、海へ流出する汚染の削減、ならびに生産者と消費者との緊密な協力が含まれる(表 SPM.1)。最良の漁業管理手法実践の能力強化、保全への 資 金 提 供 と 企 業 の 社 会 責 任(corporate social responsibility : CSR)を促す手段の実践、新たな法的かつ拘束力のある手段の策定、責任ある漁業に関する国際合意の実施と遵守執行、ならびに未報告で規制の及ばない違法漁業の防止、抑止と廃絶に必要な全ての措置を緊急に講じることが重要である。
D8 土地を基盤とする気候変動緩和策は効果的で生物多様性保全に貢献する
しかし、バイオエネルギー作物栽培の大規模展開や森林以外の生態系への植林は、生物多様性と生態系機能に負の影響をもたらす可能性がある。保護措置(セーフガード)を伴う自然を基盤とする解決策(Nature-based solutions)により、2℃目標に向けて 2030 年までに必要な炭素吸収量の 37%が吸収され、同時に生物多様性保全の効果もあると予測されている。そのため、化石燃料の使用やその他の産業や農業活動に由来する温室効果ガス排出削減に向けた積極的な取り組みに加えて、土地利用に関する対策が欠かせない。しかしながら、自然林や自給用農地の転換による、単一作物栽培を含む集約的なバイオエネルギー作物栽培の大規模展開は、生物多様性に負の影響を及ぼし、社会紛争の助長を含め、食料と水の安全保障や地域住民の生計を脅かすことがある。
D9 都市に関する SDGs の達成に向けて、自然を基盤とする解決策(Nature-based solutions)は費用対効果に優れており、従って地球全体の持続可能性に極めて重要である。
グリーンインフラや生態系を基盤としたアプローチの実施拡大により、気候変動の緩和・適応策の強化と持続可能な都市開発を同時に進めることができる。都市部の生物多様性保全の鍵になる地域を保護する必要があり、その手段には既存の都市や都市近郊、新たな開発における緑地や生物多様性にやさしい水辺の創出、都市農業、屋上庭園や緑地の拡大などのグリーン・ブルーインフラの整備がある。都市と周辺の農山漁村地域のグリーンインフラは、洪水防止、気温調節、大気と水の浄化、排水処理、エネルギー供給、食品の地産や自然とのふれあいによる健康増進効果といった面で、大規模な「グレーインフラ」を補完できる。
D10 持続可能な経路の鍵は、現在の限定的な経済成長のパラダイムから脱却し、持続可能な世界経済の構築に向けて金融と経済のシステムを進化させることにある。
これには、局所から地球全体に至るあらゆる規模の不平等を削減する発展経路、過剰消費と廃棄物の削減、経済活動から外部化されているような環境影響への対処を含む。そのような金融・経済システムの進化は、インセンティブプログラムや認証、パフォーマンス基準のような政策と手段の組み合わせや、今より国際的な整合性の高い税制、ならびにこれらを支える多国間合意や環境モニタリングと評価の強化により可能になる。これはさらに、国内総生産(Gross Domestic Product: GDP)のような標準的な経済指標を超えて、より総合的かつ長期的観点で経済と生活をとらえる指標への移行をも意味する。
出典:環境省