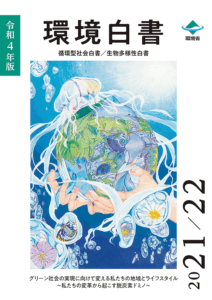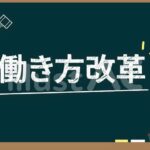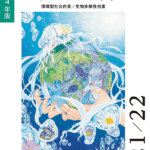第1章 地球環境の保全
第1節 地球温暖化対策
1 研究の推進、監視・観測体制の強化による科学的知見の充実
気候変動問題の解決には、最新の科学的知見に基づいて対策を実施することが必要不可欠です。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の各種報告書が提供する科学的知見は、世界全体の気候変動対策に大きく貢献しています。この活動を拠出金等により支援するとともに、国内の科学者の研究活動や、関連する会合への参加を支援することにより、我が国の科学的知見をIPCCが策定する各種報告書に反映させ、国内の議論に活用していきます。また、イベントの実施や啓発資料の作成を通じて、気候変動に関する科学的知見についての国内の理解を深めていきます。IPCCは、現在第6次評価サイクルにあり、2018年10月には「1.5℃の地球温暖化:気候変動の脅威への世界的な対応の強化、持続可能な開発及び貧困撲滅への努力の文脈における、工業化以前の水準から1.5℃の地球温暖化による影響及び関連する地球全体での温室効果ガス(GHG)排出経路に関するIPCC 特別報告書(1.5℃特別報告書)」、2019年8月に「気候変動と土地:気候変動、砂漠化、土地の劣化、持続可能な土地管理、食料安全保障及び陸域生態系における温室効果ガスフラックスに関するIPCC特別報告書(土地関係特別報告書)」、同年9月に「変化する気候下での海洋・雪氷圏に関するIPCC特別報告書(海洋・雪氷圏特別報告書)」が公表されました。さらに、2019年5月のIPCC第49回総会は日本の京都府京都市で開催され、パリ協定の実施に不可欠な「IPCC温室効果ガス排出・吸収量算定ガイドライン(2006)の2019年改良(2019年方法論報告書)」が公表され、衛星データの有用性が示されました。今後はこれらの特別報告書等の内容も踏まえ、2021年から2022年にかけて予定されている、第6次評価報告書の公表へ向けた執筆活動が引き続き進められる予定です。我が国の研究を始め、最新の科学的知見が各種報告書に適切に反映されるよう、執筆者を支援し、IPCCの活動に貢献していきます。
温室効果ガス観測技術衛星1号機(GOSAT)や2018年10月に打ち上げた2号機(GOSAT-2)による継続的な全球の温室効果ガス濃度の観測を行います。また、パリ協定に基づき世界各国が温室効果ガス排出量を報告する際に衛星観測データを利活用できるよう、GOSATシリーズの観測データからの推計結果と、インベントリからの推定結果の比較・評価を行い、信頼性向上を図るとともに、各国を技術的に支援していきます。3号機に当たる温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW)は2023年度打ち上げを目指して開発し、継続的な観測体制の維持を図ります。また、環境省はGOSATの事業主体として、GOSATがスペースデブリとして滞留することがないように引き続き検討を行い、必要な措置を行います。急速に温暖化が進む北極域の環境変動等に関する観測研究を行うための国際研究プラットフォームとして、砕氷機能を有し、北極海海氷域の観測が可能な北極域研究船の建造を着実に進めます。さらに、環境研究総合推進費等を用いた他の衛星や航空機・船舶・地上観測等による監視・観測、予測、影響評価、調査研究の推進等により気候変動に係る科学的知見を充実させます。
2 脱炭素社会の実現に向けた政府全体での取組の推進
2020年10月26日、第203回国会において、菅義偉内閣総理大臣(当時)は2050年までにカーボンニュートラル、すなわち脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。また、2021年4月22日の第45回地球温暖化対策推進本部において、2050年目標と整合的で野心的な目標として、2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指し、さらに、50%の高みに向けて挑戦を続けていくことを宣言しました。また、第204回国会で成立した地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第54号)では、2050年カーボンニュートラルを基本理念として法定化しました。さらに、同年6月9日に開催された「国・地方脱炭素実現会議」では、国民・生活者目線での2050年脱炭素社会実現に向けた「地域脱炭素ロードマップ」を取りまとめました。同年10月22日には、「地球温暖化対策計画」、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を閣議決定し、「日本のNDC(国が貢献する決定)」を国連に通報しました。経済と環境の好循環を生み出し、2030年度の野心的な目標に向けて力強く成長していくため、徹底した省エネルギーや再生可能エネルギーの最大限の導入、公共部門や地域の脱炭素化など、あらゆる分野で、でき得る限りの取組を進めていきます。
また、「革新的環境イノベーション戦略」(2020年1月統合イノベーション戦略推進会議決定)及び「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(2021年6月関係府省庁策定)に基づき、カーボンニュートラルの実現に向けて革新的技術の確立と社会実装を目指していきます。
3 エネルギー起源CO2の排出削減対策
産業・民生・運輸・エネルギー転換の各部門においてCO2排出量を抑制するため、「低炭素社会実行計画」の着実な実施と評価・検証による産業界における自主的取組の推進や、パリ協定と整合した目標設定(SBT:Science Based Targets)等の企業における中長期的な削減計画の策定支援、省エネルギー性能の高い技術・設備・機器の開発・実証・導入促進、殺菌力が強い深紫外線を発するLEDの高度化・他技術との組合せによる衛生環境向上・省CO2に資する技術の開発・実証、トップランナー制度等による家電・自動車等のエネルギー消費効率の向上、家庭・ビル・工場のエネルギーマネジメントシステム(HEMS/BEMS/FEMS)の活用や省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー管理の実施、ZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)・ZEB(ゼブ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の普及や既存の住宅・建築物の改修による省エネルギー化、動力源を抜本的に見直した革新的建設機械(電動、水素、バイオマス等)の導入拡大に向けた普及・促進、地球温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す「COOL CHOICE」の推進、次世代自動車の普及・燃費改善、道路の整備に伴って、環状道路等幹線道路ネットワークの強化、ビッグデータを活用した渋滞対策の推進等や高度道路交通システム(ITS)の推進、信号機の改良、信号灯器のLED化の推進等による交通安全施設の整備等の道路交通流対策、公共交通機関の利用促進、グリーンスローモビリティ(時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービス)の推進、ダブル連結トラック等のトラック輸送の高効率化に資する車両等の導入や過疎地域等における無人航空機を活用した物流実用化等による社会変革と物流の脱炭素化・低炭素化の同時実現、省エネ車両や回生電力の有効活用に資する設備の導入や燃料電池鉄道車両の開発の推進、鉄道車両へのバイオディーゼル燃料の導入の促進等による鉄軌道の省エネルギー化・脱炭素化の促進、荷主等と連携した新たな技術・手法を組み合わせた「連携型省エネ船」の開発・普及や、荷主等に省エネ船の選択を促す燃費性能の「見える化」の促進等による、内航海運における更なる省エネの追求、水素・燃料アンモニア等の大量かつ安定・安価な輸入・貯蔵等を可能とする受入環境の整備や、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化、集結する臨海部産業との連携等を通じて温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを目指すカーボンニュートラルポートの形成の促進、第208回国会に提出した航空法等の一部を改正する法律案に基づく航空脱炭素化推進基本方針の策定、官民協議会の設置(航空機材・装備品等への新技術導入、管制の高度化による運航方式の改善、持続可能な航空燃料(SAF:Sustainable Aviation Fuel)の導入促進)、空港施設・空港車両等からの二酸化炭素排出を削減する取組の推進、空港の再エネ拠点化の推進、モーダルシフト、共同輸配送、貨客混載等の取組支援による環境負荷の小さい効率的な物流体系の構築促進、再生可能エネルギーの最大限の導入、火力発電の高効率化や安全性が確認された原子力発電の活用等による電力分野の低炭素化等の対策・施策を実施します。また、国際海運については、国際海事機関(IMO)で地球温暖化対策が進められているところ、引き続きその取組を主導します。また、国際航空分野のCO2排出削減の長期目標について、我が国が提案し設立した国際民間航空機関(ICAO)におけるタスクグループにおいて、議長国として議論をリードしてきたところ、2022年秋に予定されているICAO総会において、検討結果を踏まえた国際的に調和が図られた野心的な長期目標が決議されるよう、引き続き議論を主導していきます。
4 エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスの排出削減対策
非エネルギー起源CO2、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等の排出削減については、農地等の適切な管理、廃棄物処理やノンフロン製品の普及等の個別施策を推進します。フロン類については、モントリオール議定書キガリ改正、改正されたフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「フロン排出抑制法」という。)の施行(2020年4月)も踏まえ、上流から下流までのライフサイクルにわたる包括的な対策により、排出抑制を推進します。
5 森林等の吸収源対策、バイオマス等の活用
森林等の吸収源対策として、間伐や再造林等の森林の整備・保全、木材・木質バイオマスの利用、農地等の適切な管理、都市緑化等を推進します。また、これらの対策を推進するため、森林・林業の担い手の育成や生産基盤の整備など、総合的な取組を実施します。
また、農地等の吸収源対策として、農地土壌への堆肥や緑肥などの有機物の継続的な施用やバイオ炭の施用等の取組を推進します。
藻場・干潟等の海洋生態系が蓄積する炭素(ブルーカーボン)を活用した新たな吸収源対策の検討を行うとともに、それらの生態系の維持・拡大に向けた取組を推進します。
6 国際的な地球温暖化対策への貢献
パリ協定の実施指針に基づき、国際的な地球温暖化対策を着実に進めます。相手国との協働に基づき、我が国の強みである技術力をいかして、市場の創出・人材育成・制度構築・ファイナンスの促進等の更なる環境整備を通じて、環境性能の高い技術・製品等のビジネス主導の国際展開を促進し、世界の排出削減に最大限貢献します。途上国と協働してイノベーションを創出する「Co-innovation(コ・イノベーション)」や、途上国支援を着実に実施していきます。また、土地利用変化による温室効果ガスの排出量は、世界の総排出量の約2割を占め、その排出を削減することが地球温暖化対策を進める上で重要な課題となっていることから、特に途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減等(REDD+)を積極的に推進し、森林分野における排出の削減及び吸収の確保に貢献します。適応分野においても各国の適応活動の促進のため、アジア太平洋気候変動適応情報プラットフォーム(AP-PLAT)において科学的知見や政策ツール、人材育成等を実施し、その活動を広報していきます。
7 横断的施策
地域脱炭素ロードマップに基づき、引き続き脱炭素先行地域の選定を進めるとともに、選定された地域において脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組を実施していきます。また、脱炭素の基盤となる重点対策を全国で実施していきます。
第208回国会に提出した地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に基づき脱炭素化に資する事業に対する資金供給その他の支援を強化することにより、民間投資の一層の誘発を図るとともに、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策のための費用に関して国が必要な財政上の措置を図ります。
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号)に基づき、促進区域の指定等に向けて取り組み、海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進します。
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策推進法」という。)に定める温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度、排出削減等指針について、2021年6月に公布された同法の一部改正法の施行等を踏まえ、一層の充実を図っていきます。
持続可能な脱炭素社会の構築や適応方策を推進するための学校や社会における環境教育、脱炭素社会に向けたライフスタイルの転換、国・地域、企業、家庭等での「見える化」の推進を図っていきます。
我が国でのより一層の取組の推進を促す観点から、公的機関の率先的取組、カーボン・オフセットや財・サービスの高付加価値化等に活用できるクレジットを認証するJ-クレジット制度の推進、カーボンフットプリントなど環境ラベルの活用、環境金融の活用、民間資金を脱炭素・低炭素投資に活用する方策の検討、エネルギー消費情報等のオープン化、グリーンなデジタル技術の実証・活用等の促進を図っていきます。
脱炭素社会構築を支えていくため、排出量・吸収量の算定手法の改善、サプライチェーン全体での排出量削減取組の推進、削減貢献量や排出削減量の算定手法に関する検討、省エネルギー・省CO2効果の高い家電やOA機器等の普及を促進するための支援策の実施、地球温暖化対策技術の開発の推進、調査研究の推進、国、地方公共団体、NGO・NPO、研究者・技術者・専門家等の人材育成・活用、評価・見直しシステムの体制整備、道路の交通流対策等を図っていきます。
さらに、「第五次環境基本計画」(2018年4月閣議決定)において掲げられた地域循環共生圏の考え方の具現化に向けた重要な第一歩として、再生可能エネルギーと動く蓄電池としてのEV(電気自動車)等を組み合わせながら、各地域に敷設した自営線で地産エネルギーを直接供給することなどにより、地域の再生可能エネルギー自給率を最大化させるとともに、防災性も兼ね備えた地域づくりを目指します。この取組を通じて、地域が主体となり、地産エネルギーを最大限活用する事例を数多く創出していくことで、脱炭素社会への移行を実現させていきます。
8 公的機関における取組
(1)政府実行計画
政府は、2021年10月に閣議決定した「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画(政府実行計画)」に基づき、2013年度を基準として、政府全体の温室効果ガス排出量を2030年度までに50%削減することを目標とし、太陽光発電の導入、新築建築物のZEB(ゼブ)化、電動車の導入、LED照明の導入、再生可能エネルギー電力の調達等の取組を率先実行していきます。
(2)地方公共団体実行計画
地球温暖化対策推進法に基づき、全ての地方公共団体は、自らの事務・事業に伴い発生する温室効果ガスの排出削減等に関する計画である地方公共団体実行計画(事務事業編)の策定が義務付けられており、都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市は、地域における再生可能エネルギーの導入拡大、省エネルギーの推進等を盛り込んだ地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定が義務付けられています。
環境省は、地方公共団体の取組を促進するため、地方公共団体実行計画の策定・実施に資するマニュアル類を公表するほか、優良な取組事例の収集・共有、地方公共団体職員向けの研修や地域レベルの温室効果ガス排出量インベントリ・推計ツール等の整備等を行います。また、2021年6月に公布された改正地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の下で、地域の脱炭素化に貢献する事業(地域脱炭素化促進事業)を促進するための制度が創設されました。この制度が円滑に活用されるよう、地方公共団体に対し、必要な助言等を行います。
さらに、改正地球温暖化対策推進法に基づき、地域における再生可能エネルギーの最大限の導入を促進するため、地方公共団体における再生可能エネルギーの導入計画の策定や、地域脱炭素化促進事業の促進区域設定等に向けた、地域が合意形成を図りゾーニング等を行う取組への支援等を行います。
第2節 気候変動の影響への適応の推進
1 気候変動の影響等に関する科学的知見の集積
気候変動の影響に対処するため、温室効果ガスの排出の抑制等を行う緩和だけではなく、既に現れている影響や中長期的に避けられない影響を回避・軽減する適応を進めることが求められています。適応を適切に実施していくためには、科学的な知見に基づいて取組を進めていくことが重要となります。
2018年に施行された気候変動適応法(平成30年法律第50号)において、環境大臣は、気候変動及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測及び評価に関する最新の科学的知見を踏まえ、おおむね5年ごとに、中央環境審議会の意見を聴いて、気候変動影響の総合的な評価についての報告書を作成し、これを公表することとされています。2020年12月に、気候変動影響の総合的な報告書として「気候変動影響評価報告書」を公表しました。同報告書でまとめられた課題を踏まえ、次期報告書の作成に向けた検討を進めます。さらに、2016年に構築された気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)において、気候変動及びその影響に関する科学的知見、地方公共団体の適応に関する計画や具体的な取組事例、民間事業者の適応ビジネス等の情報の収集・発信を行います。さらに、2020年より開始された環境研究総合推進費による「気候変動影響予測・適応評価の総合的研究」を2022年度も継続して実施します。
2 国における適応の取組の推進
2018年12月に施行された気候変動適応法及び2021年10月に改定した「気候変動適応計画」に基づき、あらゆる関連施策に適応の観点を組み込み各分野で適応の取組を推進します。また、「気候変動適応計画」に記載されている各施策の進捗管理を行うとともに、気候変動適応の進展の状況を把握、評価する手法を開発します。また、これらの取組を進めるに当たって、環境大臣が議長である「気候変動適応推進会議」の枠組みを活用することなどにより関係府省庁が連携していきます。
気候変動の影響に脆(ぜい)弱である開発途上国において、アジア太平洋地域を中心に適応に関する二国間協力を行い、各国のニーズに応じた気候変動の影響評価や適応計画の策定等の支援を行います。さらに、アジア太平洋地域の途上国が科学的知見に基づき気候変動適応に関する計画を策定し、実施できるよう、国立研究開発法人国立環境研究所と連携し、2019年6月に軽井沢で開催したG20関係閣僚会合において立ち上げを宣言した、国際的な適応に関する情報基盤であるAP-PLATの取組を強化します。
また、気候変動への適応策として重要な熱中症対策については、2022年4月に改定した「熱中症対策行動計画」に基づき、関係府省が一丸となって更なる熱中症対策を推進します。その一環として、「熱中症予防強化キャンペーン」(4~9月)を通じて、国民に対して、時季に応じた適切な予防行動の呼び掛けを実施します。また、普及啓発資料の作成・配布やシンポジウムの開催等を通じた普及啓発、「熱中症警戒アラート」などに基づき、国民、事業所などによる適切な熱中症予防行動の定着を目指します。あわせて、地方公共団体における熱中症対策を引き続き後押しするための地域におけるモデル事業を実施し、「地域における熱中症対策ガイドライン(仮称)」を策定します。引き続き災害時の熱中症対策や「新しい生活様式」における熱中症対策に関する調査・検討を行うとともに、「熱中症警戒アラート」の発表基準となる暑さ指数(WBGT)の精度向上・認知度向上に取り組みます。また、エアコン未設置の高齢者世帯等における熱中症予防対策として、初期費用なしのサブスクリプション方式(定額利用サービス)を活用した新たなビジネスモデルの確立のためのモデル事業を実施します。
3 地域等における適応の取組の推進
地方公共団体の科学的知見に基づく適応策の立案・実施を支援するため、A-PLATにおける知見の充実や、国立研究開発法人国立環境研究所による地方公共団体及び地域気候変動適応センターへの技術的支援等を行います。また、全国7ブロック(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州・沖縄)で「気候変動適応広域協議会」を開催し、気候変動適応に関する施策や取組についての情報交換・共有や、地域における気候変動影響に関する科学的知見の整理等を行います。また、「気候変動適応広域協議会」に地域の気候変動適応課題に関する分科会を立ち上げ、関係者の連携によるアクションプランの策定を行います。
また、セミナー等の機会を通じて事業者の適応の取組を促進していきます。さらに、事業者の適応ビジネスを促進するため、国内でのA-PLATやAP-PLATも活用しつつ、事業者の有する気候変動適応に関連する技術・製品・サービス等の優良事例を発掘し、国内外に積極的に情報提供を行います。
国民の適応に関する理解を深めるため、広報活動や啓発活動を行います。また、住民参加型の「国民参加による気候変動情報収集・分析」事業により、国民の関心と理解を深めます。
第3節 オゾン層保護対策等
ノンフロン・低GWP製品の普及促進や機器の廃棄時等におけるフロン類の回収がより適切に行われるよう、フロン排出抑制法の確実な施行を始め、上流から下流までのライフサイクルにわたる包括的な対策により、排出抑制を推進します。
また、特定物質等の規制、観測・監視の情報の公表については、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)に基づき、生産規制及び貿易規制を行うとともに、オゾン層等の観測成果及び監視状況を毎年公表します。さらに、途上国における取組の支援については、フロン類のライフサイクル全般にわたる排出抑制対策を国際的に展開するための枠組みであるフルオロカーボン・イニシアティブ等を通じ、アジア等の途上国に対して、フロン類を使用した製品・機器からの転換やフロン類の回収・破壊等についての技術協力や政策等の知見・経験の提供により取組を支援します。
第2章 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組
第1節 生物多様性条約COP15及び生物多様性国家戦略
生物多様性条約第15回締約国会議(COP15。以下、締約国会議を「COP」という。なお、本章におけるCOPは、生物多様性条約締約国会議を指す。)第二部において採択される予定である、新たな生物多様性の世界目標が2050年ビジョン「自然との共生」に向けて野心的な枠組みとなるよう、COP10議長国として愛知目標を取りまとめた経験も活かして引き続き積極的に議論に貢献します。
また、新たな生物多様性の世界目標を踏まえ、「生物多様性国家戦略2012-2020」(2012年閣議決定)に次ぐ新たな生物多様性国家戦略を策定します。
第2節 生物多様性の主流化に向けた取組の強化
1 多様な主体の参画
国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体など国内のあらゆる主体の参画と連携を促進し、生物多様性の保全とその持続可能な利用の確保に取り組むため、多様な主体で構成される「2030生物多様性枠組実現日本会議(J-GBF)」を通じた各主体間の連携や地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)に基づく地域連携保全活動に対する各種支援を行います。
2 生物多様性に配慮した企業活動の推進
生物多様性に係る事業活動に関する情報や考え方等を取りまとめたあらゆる業種・事業者向けの「生物多様性民間参画ガイドライン」の普及を図るとともに、表彰制度の活用や生物多様性に対する貢献・負荷・依存度の把握・評価・情報開示に関する情報提供を行うなど、バリューチェーン全体での活動において事業者を支援し、事業者の生物多様性分野への参画を促します。また、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)やSicence Based Targets for Nature(SBTs for Nature)等の国際的イニシアティブへの対応等、生物多様性を主流化するための方策について検討を進めます。
3 自然とのふれあいの推進
「みどりの月間」等における自然とのふれあい関連行事の全国的な実施や各種情報の提供、自然公園指導員及びパークボランティアの人材の活用、由緒ある沿革と都市の貴重な自然環境を有する国民公園等の庭園としての質や施設の利便性を高めるための整備運営、都市公園等の身近な場所における環境教育・自然体験活動等に取り組みます。
国立公園満喫プロジェクトを継続的に実施し、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した国内外の利用者の回復に向け、受入環境整備やワーケーション等の新たな利用推進を図ります。これまで、8つの国立公園を中心に進めてきた各種受入環境整備(利用拠点の滞在環境の上質化や多言語解説の充実、ビジターセンター等の再整備や機能充実、質の高いツアー・プログラムの充実やガイド等の人材育成支援、利用者負担による公園管理の仕組みの導入等)について、公園の特性や体制に応じて、34国立公園全体で推進するとともに、国定公園等にも展開します。また、海外だけでなく国内の誘客を強化し、プロモーションを実施するとともに、国立公園等での自然体験プログラム推進のための企画造成、ワーケーション受入や自然との調和が図られた滞在環境の整備等の受入環境整備を支援します。改正自然公園法(昭和32年法律第161号)により新たに創設された自然体験活動促進計画・利用拠点整備改善計画制度も活用し、国立公園の本来の目的である「保護」と「利用」が地域において好循環を生み出し地域の活性化につながるよう、関係省庁や地方公共団体、観光関係者を始めとする企業、団体など、幅広い関係者との協働の下、取組を進めていきます。また、貴重な自然資源である温泉の保護、適正利用及び温泉地の活性化を図ります。
第3節 生物多様性保全と持続可能な利用の観点から見た国土の保全管理
1 生態系ネットワークの形成
生物の生息・生育空間のまとまりとして核となる地域(コアエリア)及びその緩衝地域(バッファーゾーン)を適切に配置・保全するとともに、これらを生態的な回廊(コリドー)で有機的につなぐことにより、生態系ネットワーク(エコロジカルネットワーク)の形成に努めます。生態系ネットワークの形成に当たっては、流域圏など地形的なまとまりにも着目し、様々なスケールで森里川海を連続した空間として積極的に保全・再生を図るための取組を関係機関が横断的に連携して総合的に進めます。また、民間の取組等により生物多様性の保全が図られている区域を国が「自然共生サイト(仮称)」として認定する仕組みを試行する等、OECMに関する取組を進めることで、保護地域を核としたネットワーク化を図り、生物多様性の保全を推進します。
2 重要地域の保全
各重要地域について、保全対象に応じて十分な規模、範囲、適切な配置、規制内容、管理水準、相互の連携等を考慮しながら、関係機関が連携・協力して、その保全に向けた総合的な取組を進めます。
(1)自然環境保全地域等
原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域については、引き続き行為規制や現状把握等を行うとともに、新たな地域指定を含む生物多様性の保全上必要な対策を検討・実施します。沖合海底自然環境保全地域に関しては、第2章第4節も参照。
(2)自然公園
自然公園(国立公園、国定公園)については、公園計画等の見直しを進めつつ、公園計画に基づく行為規制や利用のための施設整備等を行います。また、国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」としてブランド化し、保護すべきところは保護しつつ、利用の促進を図ることにより、地域の活性化を目指す取組を推進します。その他、再生可能エネルギーの利用の促進や省エネルギー化による施設の脱炭素化の取組を推進します。
(3)鳥獣保護区
狩猟を禁止するほか、特別保護地区(鳥獣保護区内で鳥獣保護又はその生息地保護を図るため特に必要と認める区域)においては、一定の開発行為の規制を行います。
(4)生息地等保護区
生息地等保護区の指定、生息環境の把握及び維持管理、施設整備、普及啓発を行い、必要に応じ、立入り制限地区を設け、種の保存を図ります。
(5)天然記念物
動物、植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもののうち重要なものを天然記念物に指定するなど、法令等に基づく適切な保存と活用に努めます。
(6)国有林野における保護林及び緑の回廊
原生的な天然林を有する森林や希少な野生生物の生育・生息の場となる森林である「保護林」や、これらを中心としたネットワークを形成することによって野生生物の移動経路となる「緑の回廊」において、モニタリング調査等を行い森林生態系の状況を把握し順応的な保全・管理を推進します。
(7)保安林
「全国森林計画」に基づき、保安林の配備を計画的に推進するとともに、その適切な管理・保全に取り組みます。
(8)特別緑地保全地区・近郊緑地特別保全地区等
多様な主体による良好な緑地管理がなされるよう、管理協定制度等の適正な緑地管理を推進するための制度の活用を図ります。
(9)ラムサール条約湿地
湿地の保全と賢明な利用及びそのための普及啓発を図るとともに、計画的な登録を推進します。
(10)世界自然遺産
登録された5地域(「屋久島」、「白神山地」、「知床」、「小笠原諸島」、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」)において、専門家の助言を踏まえつつ、地域関係者との合意形成を図りながら、関係省庁や自治体と連携し、世界自然遺産地域の適切な保全管理を推進します。
(11)生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)
国立公園等の管理を通して、登録された各生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)の適切な保全管理を推進するとともに、地元協議会への参画を通じて、持続可能な地域づくりを支援します。また、新規登録を目指す自治体に対する情報提供、助言等を行います。
(12)ジオパーク
国立公園と重複するジオパークにおいて、地形・地質の多様性等の保全を図るとともに、ジオツアーや環境教育のプログラムづくり等について、地方公共団体等のジオパークを推進する機関と連携して進めます。
(13)世界農業遺産・日本農業遺産
世界農業遺産及び日本農業遺産に認定された地域の農林水産業システムの維持・保全等に係る活動を推進するとともに、本制度や認定地域に対する国民の認知度を向上させるための情報発信に取り組みます。
3 自然再生
河川、湿原、干潟、藻場、里山、里地、森林など、生物多様性の保全上重要な役割を果たす自然環境について、自然再生推進法(平成14年法律第148号)の枠組みを活用し、多様な主体が参加し、科学的知見に基づき、長期的な視点で進められる自然再生事業を推進します。また、地域循環共生圏の考え方や防災・減災等の自然環境の持つ機能等に着目し、地域づくりや気候変動への適応等にも資する自然環境の再生等を推進します。
4 里地里山の保全活用
里地里山等に広がる二次的自然環境の保全と持続的利用を将来にわたって進めていくため、人の生活・生産活動と地域の生物多様性を一体的かつ総合的に捉え、民間保全活動とも連携しつつ、持続的な管理を行う取組を推進します。
文化的景観のうち、地方公共団体が保存の措置を講じ、特に重要であるものを重要文化的景観として選定するとともに、地方公共団体が行う重要文化的景観の保存・活用事業に対し支援を実施します。
5 木質バイオマス資源の持続的活用
森林等に賦存する木質バイオマス資源の持続的な活用を支援し、地域の低炭素化と里山等の保全・再生を図ります。
6 都市の生物多様性の確保
(1)都市公園の整備
都市における生物多様性を確保し、また、自然とのふれあいを確保する観点から、都市公園の整備等を計画的に推進します。
(2)地方公共団体における生物多様性に配慮した都市づくりの支援
都市と生物多様性に関する国際自治体会議等に関する動向及び決議「準国家政府、都市及びその他地方公共団体の行動計画」の内容等を踏まえつつ、都市のインフラ整備等に生物多様性への配慮を組み込むことなど、地方公共団体における生物多様性に配慮した都市づくりの取組を促進するため、「生物多様性に配慮した緑の基本計画策定の手引き」の普及を図るほか、「都市の生物多様性指標」に基づき、都市における生物多様性保全の取組の進捗状況を地方公共団体が把握・評価し、将来の施策立案等に活用されるよう普及を図ります。
第4節 海洋における生物多様性の保全
我が国がこれまでに抽出した生物多様性の観点から重要度の高い海域を踏まえ、沖合の海底の自然環境の保全を図るため、沖合海底自然環境保全地域の管理等を推進します。また、漁業等の従来の活動に加えて今後想定される海底資源の開発、波力や潮力等の自然エネルギーの活用等の人間活動と海洋における生物多様性の保全との両立を図ります。
サンゴ礁の保全については、「サンゴ礁生態系保全行動計画2022-2030」に基づき、様々なステークホルダーとの協働による地域主導のサンゴ礁保全の推進を図ります。
第5節 野生生物の適切な保護管理と外来種対策の強化
1 絶滅のおそれのある種の保存
絶滅のおそれのある野生生物の情報を的確に把握し、第5次レッドリストの公表に向けたレッドリストの見直し作業を行います。第5次レッドリストは2024年度以降の公表を目指しています。人為の影響により存続に支障を来す事情のある種については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)に基づく国内希少野生動植物種として指定し、捕獲や譲渡等を規制するほか、特に個体の繁殖の促進や生息地の整備・保全等が必要と認められる種について、保護増殖事業や生息地等保護区の指定等を行います。また、2017年の同法改正により、特定第二種国内希少野生動植物種制度や認定希少種保全動植物園等制度の創設、国際希少野生動植物種の流通管理の強化等が行われ、2018年6月から施行されたことを踏まえ、これらの制度を着実に運用していきます。
2 野生鳥獣の保護管理
近年、我が国においては、一部の野生鳥獣の個体数の増加や分布拡大により、農林水産業、生態系、生活環境への被害が深刻化しています。特に、ニホンジカ、イノシシについては、農林水産省と共に「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」を2013年に策定し、個体数を2023年度までに2011年度と比較して半減させる目標を掲げています。目標達成のために、更なる捕獲を強化するとともに、鳥獣保護管理の担い手の育成、効果的な捕獲技術の開発、広域的な捕獲の強化、生息環境管理、被害防除、鳥類の鉛中毒対策等の取組を進めます。また、ジビエ利用を考慮した狩猟者の育成等の取組を進め、更なるジビエ利用拡大を図ります。
野生鳥獣に鳥インフルエンザ等の感染症が発生した場合や、油汚染事故による被害が発生した場合に備えて、野鳥におけるサーベイランス(調査)や関連情報の収集、人材育成等を行います。また、豚熱(CSF)のまん延防止のため、野生イノシシの捕獲強化、サーベイランス及びそれらに伴う防疫措置の徹底等を行います。さらに、我が国における野生鳥獣に関する感染症の実態把握や生物多様性保全の観点からのリスク評価等を踏まえ、感染症対策の観点からの鳥獣の保護及び管理を推進します。
3 外来種対策
外来種対策については、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に基づき、特定外来生物の輸入・飼養等の規制、奄美大島のマングース防除事業等の生物多様性保全上重要な地域を中心とした防除事業やヒアリ等の侵入初期の侵略的外来種の防除事業の実施、飼養・栽培されている動植物の適正な管理の徹底等の対策を進めます。また、2022年1月の「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」(中央環境審議会答申)を踏まえ、ヒアリ対策の強化、アカミミガメやアメリカザリガニといった大量に飼育されている外来種の対策及び地方公共団体等との連携強化に関する制度の見直し等を進めていきます。
4 遺伝子組換え生物対策
遺伝子組換え生物については、環境中で使用する場合の生物多様性への影響について事前に的確な評価を行うとともに、生物多様性への影響の監視を進めます。
5 動物の愛護及び適正な管理
2019年6月に改正された動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の2021年6月及び2022年6月の段階的な施行に向けた必要な対応、2022年5月に全面施行となる愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)の施行準備、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年法律第83号)及び「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」の趣旨にのっとった取組の推進により、動物の虐待防止や適正な飼養等の動物愛護に係る施策及び動物による人への危害や迷惑の防止等の動物の適正な管理に係る施策を総合的に進め、人と動物の共生する社会の実現を目指します。
第6節 持続可能な利用
1 持続可能な農林水産業
農林水産関連施策において、農林水産省では、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させる新たな政策方針として、2021年5月に「みどりの食料システム戦略」を策定し、温室効果ガス削減や生物多様性の保全等の環境負荷低減にも寄与する持続可能な食料システムの構築を強力に推進することとしています。また、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律案(みどりの食料システム法案)」を第208回国会に提出しました。化学農薬・肥料の低減や有機農業の拡大などに取り組む生産者や地域ぐるみの活動、環境負荷低減につながる技術開発等を促進します。
また、サプライチェーン全体で生物多様性をより重視した視点を農林水産施策に取り入れ、持続可能な食料・農林水産業を推進するとともに、農林水産業の生産現場であり、それを担う人々の暮らしの場でもある農山漁村の活性化を図ります。具体的には農地・水資源の保全・維持、生物多様性保全に効果の高い営農活動の導入や持続可能な森林経営等を積極的に進めるとともに、生態系に配慮した再生可能エネルギー等の利用を促進します。
持続可能な農業生産を支える取組の推進を図るため、化学肥料、化学合成農薬の使用を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者の組織する団体等を支援する環境保全型農業直接支払を実施します。
環境保全等の持続可能性を確保するための取組である農業生産工程管理(GAP)の普及・推進や、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)に基づき、土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減に効果が高い農業生産方式の導入計画の認定を受けた農業者(エコファーマー)の普及推進、有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)に基づく有機農業の推進に関する基本的な方針の下で、有機農業指導員の育成及び新たに有機農業に取り組む農業者の技術習得等による人材育成、有機農産物の安定供給体制の構築、国産有機農産物の流通、加工、小売等の事業者と連携した需要喚起の取組を支援します。
2 エコツーリズムの推進
エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)に基づき、全体構想の認定・周知、ガイド等の人材の育成、情報の収集、広報活動等を実施するなど、地域が主体的に行うエコツーリズムの活動を支援します。
第7節 国際的取組
1 生物多様性に関する世界目標への貢献
2021年10月に開催されたCOP15第一部において山口壯環境大臣から表明した総額1,700万ドル規模(約18億円)の「生物多様性日本基金」第2期により、ポスト2020生物多様性枠組実施への途上国支援を進めます。具体的には、我が国が推進しているSATOYAMAイニシアティブの経験も踏まえた生物多様性国家戦略の策定・改定や、生物多様性保全と地域資源の持続可能な利用を進めるSATOYAMAイニシアティブの現場でのプロジェクトを検討しています。
2 生物多様性及び生態系サービスに関する科学と政策のインターフェースの強化
生物多様性や生態系サービスに関して科学と政策の結び付きを国際的に強化するため、「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)」の活動を支援します。特に、2019年2月に業務を開始した「侵略的外来種に関するテーマ別評価」の技術支援機関の活動を支援するほか、評価報告書等に我が国の知見を効果的に反映させるため、国内専門家及び関係省庁による国内連絡会を開催します。また、IPBESの成果を踏まえて研究や対策等の取組が促進されるよう、2019年5月に公表された生物多様性と生態系サービスに関する地球規模の評価報告書を含むIPBESのこれまでの成果を国内に発信します。
3 二次的自然環境における生物多様性の保全と持続可能な利用・管理の促進
COP15を機に、我が国の取組事例の国際展開を含め、これまで73か国・地域で展開してきたSATOYAMAイニシアティブを一層推進するなど、ポスト2020生物多様性枠組の実施に向けた取組を強化していきます。
4 アジア保護地域パートナーシップの推進
アジアにおける保護地域の管理水準の向上に向けて、保護地域の関係者がワークショップ等を通じて情報共有を図る枠組みである「アジア保護地域パートナーシップ」での活動を推進します。
5 森林の保全と持続可能な経営の推進
世界における持続可能な森林経営に向けた取組を推進するため、国連森林フォーラム(UNFF)、モントリオールプロセス等の国際対話への積極的な参画、国際熱帯木材機関(ITTO)、国連食糧農業機関(FAO)等の国際機関を通じた協力、国際協力機構(JICA)、世界銀行の森林炭素パートナーシップ基金(FCPF)、緑の気候基金(GCF)等を通じた技術・資金協力等により、多国間、地域間、二国間の多様な枠組みを活用した取組の推進に努めます。
6 砂漠化対策の推進
砂漠化対処条約(UNCCD)に関する国際的動向を踏まえつつ、同条約への科学技術面からの貢献を念頭に砂漠化対処のための調査等を進め、二国間協力等の国際協力の推進に努めます。
7 南極地域の環境の保護
南極地域の環境保護を図るため、南極地域での観測、観光等に対する確認制度等を運用し、普及啓発を行うなど、環境保護に関する南極条約議定書及びその国内担保法である南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)の適正な施行を推進します。また、毎年開催される「南極条約協議国会議」に参加し、南極における環境の保護の方策について議論を行います。
8 サンゴ礁の保全
国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)の枠組みの中で策定した「地球規模サンゴ礁モニタリングネットワーク(GCRMN)東アジア地域解析実施計画書」に基づき、サンゴ礁生態系のモニタリングデータの地球規模の解析を各国と協力して進めます。
9 生物多様性関連諸条約の実施
ワシントン条約に基づく絶滅のおそれのある野生生物種の保護、ラムサール条約に基づく国際的に重要な湿地の保全及び適正な利用、二国間渡り鳥等保護条約や協定を通じた渡り鳥等の保全、カルタヘナ議定書に基づく遺伝子組換え生物等の使用等の規制を通じた生物多様性影響の防止、名古屋議定書に基づく遺伝資源への適正なアクセスと利益配分の推進等の国際的取組を推進します。
第8節 生物多様性及び生態系サービスの把握
1 自然環境データの整備・提供・利活用の推進
生物多様性に関する科学的知見の充実を図るため、自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)やモニタリングサイト1000等の継続的な調査の実施やデータの解析、各主体間の連携によるデータの収集・提供・利活用等に係る情報基盤の整備を進めます。また、日本生物多様性情報イニシアチブ(データ提供拠点)である独立行政法人国立科学博物館及び大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立遺伝学研究所と連携しながら、生物多様性情報を地球規模生物多様性情報機構(GBIF)に提供します。
2 放射線による野生動植物への影響の把握
東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する放射線による自然生態系への影響を把握するため、野生動植物の試料採取及び放射能濃度の測定等による調査を実施します。また、調査研究報告会の開催等を通じて情報を集約し、関係機関及び各分野の専門家等との情報共有を図ります。
3 生物多様性及び生態系サービスの総合評価
最新の科学的知見等を踏まえて取りまとめられた「生物多様性及び生態系サービスの総合評価2021(JBO3)」に関して、政策決定を支える客観的情報とするとともに、国民に分かりやすく伝えていきます。さらに、生物多様性及び生態系サービスの価値が行政や企業の意思決定及び行動に反映されるよう、その評価手法の検討を進めます。
4 生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)及び気候変動適応策(EbA)の推進
自然生態系を基盤とした気候変動への適応や防災・減災を進めるため、かつての氾濫原や湿地等の再生による流域全体での遊水機能等の強化に向けた「生態系機能ポテンシャルマップ」の作成を進めます。また、同マップの作成方法や活用方策等の技術的な情報をまとめた自治体職員向けの手引きを策定し、その情報発信に努めます。
第3章 循環型社会の形成
第1節 持続可能な社会づくりとの統合的取組
持続可能な開発目標(SDGs)やG7富山物質循環フレームワークに基づき、化学物質や廃棄物について、ライフサイクルを通じて適正に管理することで大気、水、土壌等の保全や環境の再生に努めるとともに、環境保全を前提とした循環型社会の形成を推進すべく、資源効率性・3R(リデュース、リユース、リサイクル)と気候変動、有害物質、自然環境保全等の課題に関する政策を包括的に統合し、促進します。
リサイクルに加えて2R(リデュース、リユース)を促進することで資源効率性の向上と脱炭素化の同時達成を図ることや、地域特性等に応じて廃棄物処理施設を自立・分散型の地域のエネルギーセンターや災害時の防災拠点として位置付けることにより、資源循環と脱炭素化や国土の強靱(じん)化との同時達成を図ることなど、環境・経済・社会課題の統合的解決に向けて、循環型社会形成を推進します。
環境的側面・経済的側面・社会的側面を統合的に向上させるため、国民、国、地方公共団体、NPO・NGO、事業者等が連携を更に進めるとともに、各主体の取組をフォローアップし、推進します。
第2節 多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化
循環、脱炭素、自然共生の統合的アプローチに基づき、地域の循環資源を中心に、再生可能資源、ストック資源の活用、森里川海が生み出す自然的なつながり、資金循環や人口交流等による経済的なつながりを深めていく「地域循環共生圏」を実現します。
具体的には、各地域における既存のシステムや産業・技術、ひいては人的資源・社会関係資本を駆使しながら地域における資源利用効率の最大化を図るべく、各地域における資源循環領域の課題・機会の掘起し、事業化に向けた実現可能性調査の支援、優れた事例の全国的周知等を行い、例えば、排出事業者の廃棄物処理に関する責任や市町村の一般廃棄物処理に関する統括的責任が果たされることを前提に、リユース、リサイクル、廃棄物処理、農林水産業など多様な事業者の連携により循環資源、再生可能資源を地域でエネルギー活用を含めて循環利用し、これらを地域産業として確立させることで、地域コミュニティの再生、雇用の創出、地域経済の活性化等につなげます。
市町村等による一般廃棄物の適正処理・3Rの推進に向けた取組を支援するため、市町村の処理責任や一般廃棄物処理計画の適正な策定及び運用等について引き続き周知徹底を図ります。
上記の推進に当たって、地域の特性や循環資源の性質に応じて、狭い地域で循環させることが適切なものはなるべく狭い地域で循環させ、広域で循環させることが適切なものについては循環の環を広域化させること、地域の森里川海を保全し適度に手を加え維持管理することで生み出される再生可能資源を継続的に地域で活用していくことを考慮します。
「バイオマス活用推進基本計画」(2016年9月策定)の改定に向けた取組を進めます。また、「バイオマス事業化戦略」に基づき、グリーン産業創出等に向けたバイオマス産業都市の構築を推進します。農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)に基づき、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギーの導入を促進します。
第3節 ライフサイクル全体での徹底的な資源循環
サービサイジング、シェアリング、リユース、リマニュファクチャリングなど2R型ビジネスモデルの普及が循環型社会にもたらす影響(天然資源投入量、廃棄物発生量、CO2排出量等の削減や資源生産性の向上等)について、可能な限り定量的な評価を進めつつ、そうしたビジネスモデルの確立・普及を促進します。
資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)(平成3年法律第48号)については、これまでに行ってきた家庭から排出される使用済パソコンや小形二次電池の回収体制の整備、家電・パソコンに含有される物質に関する情報共有の義務化の措置等を踏まえ、循環型社会の形成に向けた取組を推進するために、最近の資源有効利用に係る取組状況等を踏まえつつ、3Rの更なる促進に努めます。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)(平成7年法律第112号)については、2016年5月の中央環境審議会及び産業構造審議会からの意見具申や2019年5月に策定した「プラスチック資源循環戦略」(2019年5月31日消費者庁・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省策定)を踏まえ、環境負荷低減と社会全体のコスト低減等を図り、循環型社会の形成や資源の効率的な利用を推進するために、各種課題の解決や容器包装のライフサイクル全体を視野に入れた3Rの更なる推進に取り組みます。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)については、2019年7月に策定された新たな基本方針に基づき、事業系食品ロス削減に係る目標及び再生利用等実施率等の目標の達成に向けて、食品ロスを含めた食品廃棄物等の発生抑制と食品循環資源の再生利用等の促進に取り組みます。さらに、食品廃棄物等の不適正処理対策を徹底します。
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)(平成24年法律第57号)については、2020年8月に取りまとめられた「小型家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」を踏まえ、使用済小型家電の回収量拡大に向けて取り組み、有用金属等の再資源化を促進します。また、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会のメダルを使用済小型家電由来の金属から製作する「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」を通じて得られた機運や使用済小型家電の回収環境等をレガシーとする「アフターメダルプロジェクト」を通じて、引き続き小型家電リサイクルの普及啓発を行い、循環型社会の構築や3R意識の醸成に活用していきます。
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)(平成10年法律第97号)については、2014年10月に取りまとめられた「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」から5年を経過していることから、制度検討を進めています。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)(平成14年法律第87号)は、2021年7月に産業構造審議会・中央環境審議会の合同会議において示された制度の評価・検討の結果を踏まえつつ、適切な施策を講じていきます。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)(平成12年法律第104号)については、前回の見直し時の中央環境審議会及び社会資本整備審議会からの意見具申に基づき、確実に法を施行していきます。
1 プラスチック
海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応等の幅広い課題に対応するため、「プラスチック資源循環戦略」で掲げた野心的なマイルストーンの達成を目指し、2022年4月1日に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。)の円滑な施行を始め、予算、制度的対応を進めていきます。また、「バイオプラスチック導入ロードマップ」(2021年1月策定)に基づき、バイオプラスチックの実用性向上と化石燃料由来プラスチックとの代替促進を進めていきます。「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」(2021年1月経済産業省、環境省策定)に基づき、企業価値の向上と国際競争力の強化につながるよう、共通基盤を整備していきます。
2 バイオマス(食品、木など)
「第四次循環型社会形成推進基本計画」(以下、循環型社会形成推進基本計画を「循環基本計画」という。)及び新たな食品リサイクル法基本方針に示された、食品ロス削減目標の達成のため、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)に基づく基本方針も踏まえ、食品ロス削減の取組を推進します。
食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業、家庭の各主体の取組を促進するとともに、地方公共団体が各主体間の連携を調整し、地域全体で取組を促進します。
食品廃棄物等の不適正処理対策の徹底と食品リサイクルの取組を同時に促進します。
3 ベースメタルやレアメタル等の金属
小型家電リサイクルの普及による影響と効果を分析した上で、小型家電の収集・運搬の効率化や、地域特性に応じた最適な回収方法の選択を促すことによって、回収量の更なる増大につなげます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)及びその政省令の改正等を通じて、いわゆる雑品スクラップに含まれる有害使用済機器の適正な処理やリサイクルを推進します。
使用済製品のより広域でのリサイクルを行うため、広域的な実施によって、廃棄物の減量化や適正処理の確保に資するとして環境大臣の認定を受けた者については、地方公共団体ごとに要求される廃棄物処理業の許可を不要とする制度(広域認定制度)の適切な運用を図り、情報処理機器や各種電池等の製造事業者等が行う高度な再生処理によって、有用金属の分別回収を推進します。
4 土石・建設材料
建設廃棄物や建設発生土等の建設副産物の減量のため、脱炭素化や強靱(じん)化も考慮した既存住宅の改修による長寿命化など、良質な社会ストックを形成し、社会需要の変化に応じて機能を変えながら長期活用を進めます。また、人口減少等により、空き家等の放置された建築物について廃棄物対策を推進します。
5 温暖化対策等により新たに普及した製品や素材
太陽光発電設備等の脱炭素製品の3Rを推進し、これら脱炭素製品の普及を促進します。
第4節 適正処理の更なる推進と環境再生
1 適正処理の更なる推進
一般廃棄物の適正処理については、当該処理業が専ら自由競争に委ねられるべき性格のものではなく、継続性と安定性の確保が考慮されるべきとの最高裁判所判決(2014年1月)や、市町村が処理委託した一般廃棄物に関する不適正処理事案の状況を踏まえ、2014年10月8日に通知を発出しており、市町村の統括的責任の所在、市町村が策定する一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物処理法の適正な運用について、引き続き周知徹底を図ります。また、一般廃棄物処理に関するコスト分析方法、有料化の進め方、標準的な分別収集区分等を示す「一般廃棄物会計基準」、「一般廃棄物処理有料化の手引き」、「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」の三つのガイドラインについて、更なる普及促進に努めます。
感染症等に対応する強靱(じん)で持続可能な廃棄物処理体制の構築に向けた検討を行います。また、IoT及びAIの活用による適正処理工程の監視の高度化及び省力化等の技術情報の収集等を進めます。
一般廃棄物処理施設整備に当たっては、人口減少等の社会状況の変化を考慮した上で、IT等を活用した高度化、広域化・集約化、長寿命化等のストックマネジメントによる効率的な廃棄物処理を推進するとともに、地域のエネルギーセンターや防災拠点としての役割を担うなど、関係者と連携し、地域の活性化等にも貢献する一般廃棄物処理の中核をなす処理施設の整備を促進します。また、2022年4月にプラスチック資源循環促進法が施行されたことを踏まえ、循環型社会形成推進交付金等の交付要件に「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化に必要な措置を行っていること」を追加し、これにより、プラスチック使用製品廃棄物の再商品化等を推進します。
一般廃棄物の最終処分場に関しては、ごみのリサイクルや減量化を推進した上でなお残る廃棄物を適切に処分するため、最終処分場の設置又は改造、既埋立物の減容化等による一般廃棄物の最終処分場の整備を図ります。このため、循環型社会形成推進交付金等による、市町村への一般廃棄物処理施設の整備等の支援を継続するとともに、必要に応じて、交付対象事業の見直し等を検討します。
最終処分場の延命化・確保のためにも3Rの取組を進展させることにより、最終処分量の一層の削減を進めます。
廃棄物処理法及びその政省令の改正等を踏まえて、廃棄物の不適正処理への対応強化を進めます。
不法投棄の撲滅に向けて、早期発見による未然防止及び早期対応による拡大防止を進めます。
盛土による災害防止の取組として、電子マニフェストの利用促進、建設現場パトロールの強化等、廃棄物混じり盛土の発生防止に向けた対応策を関係省庁連携の上、進めていきます。
優良産廃処理業者の育成、優良認定制度の活用や電子マニフェストの普及拡大、排出事業者の意識改革等により、良貨が悪貨を駆逐する競争環境の整備に取り組み、循環分野における環境産業全体の健全化及び振興を図ります。
各種手続等の廃棄物に関する情報の電子化の検討を進めるとともに、廃棄物分野において電子化された、電子マニフェストを含む各種情報の活用の検討を進めます。
石綿(アスベスト)、水銀廃棄物、残留性有機汚染物質(POPs)を含む廃棄物、埋設農薬等については、製造、使用、廃棄の各段階を通じた化学物質対策全体の視点も踏まえつつ、水質汚濁・大気汚染・土壌汚染等の防止対策と連携するとともに、当該物質やそれらを含む廃棄物に関する情報を関係者間で共有し、適正に回収・処理を進めます。
高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について、2018年度に北九州事業地域の変圧器・コンデンサー等の計画的処理完了期限を迎えました。引き続き、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)(平成13年法律第65号)及び閣議決定した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に基づき、処理が一日も早く進むよう、関係者が一丸となって取組を推進します。
プラスチックの資源循環を通じたリサイクル原料への有害物質の混入について、有害物質規制の強化等の国際的動向も踏まえ、上流側の化学物質対策等と連携し、ライフサイクル全体を通じたリスクを削減します。
2 廃棄物等からの環境再生
マイクロプラスチックを含む海洋ごみや散乱ごみに関して、国際的な連携の推進と共に、実態把握や発生抑制を進めます。
生活環境保全上の支障等がある廃棄物の不法投棄等について支障の除去等を進めます。
放置艇の沈船化による海域汚染を防止するため、係留・保管能力の向上と規制措置を両輪とした放置艇対策を推進します。
3 東日本大震災からの環境再生
東日本大震災からの被災地の復興・再生については、2021年3月に、「『第2期復興・創生期間』以降における東日本大震災からの復興の基本方針」(以下「『第2期復興・創生期間』以降の復興基本方針」という。)を閣議決定し、2021年度以降の復興の取組方針が示されたところです。引き続き、安心して生活できる環境を取り戻す環境再生の取組を着実に進めます。環境再生の取組に加えて、環境の視点から地域の強みを創造・再発見する未来志向の取組も推進します。
(1)除染等の措置等
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)に基づき、必要な土壌等の除染等の措置及び除去土壌等の保管等を適切に実施します。また、2018年3月に策定した仮置場等の原状回復に係るガイドラインに沿って、除去土壌等の搬出が完了した仮置場の原状回復を進めます。さらに、福島県外の除去土壌の処分方法について、除去土壌の埋立処分の実証事業の結果や有識者による「除去土壌の処分に関する検討チーム」での議論を踏まえ、検討を進めていきます。
(2)中間貯蔵施設の整備等
福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物等を福島県外で最終処分するまでの間、安全かつ集中的に管理・保管する施設として中間貯蔵施設を整備しています。中間貯蔵施設事業は、「令和4年度の中間貯蔵施設事業の方針」(2022年1月公表)及び「『第2期復興・創生期間』以降の復興基本方針」に基づき取組を実施しています。特定復興再生拠点区域等で発生した除去土壌等の搬入や、中間貯蔵施設内の各施設の安全な稼働等、安全を第一に、地域の理解を得ながら、事業を実施していきます。
中間貯蔵開始後30年以内の福島県外での最終処分に向けては、「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び「工程表」(2016年4月策定、2019年3月見直し)に沿って、除去土壌等の減容・再生利用に関する技術開発実証事業や国民理解の醸成に向けた取組等を着実に進めていきます。
(3)放射性物質に汚染された廃棄物の処理
福島県内の汚染廃棄物対策地域では、「対策地域内廃棄物処理計画」(2013年12月一部改定)等に基づき着実に処理を進めていきます。指定廃棄物の処理については、放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針において、当該指定廃棄物が発生した都道府県内において行うこととされており、引き続き各都県ごとに早期の処理に向け取り組んでいきます。
(4)帰還困難区域の復興・再生に向けた取組
帰還困難区域については、2017年5月に改正された福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)に基づき、各町村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に沿って、2022年から2023年の避難指示の解除に向け、特定復興再生拠点区域における除染・家屋等の解体を進めます。特定復興再生拠点区域外については、2021年8月31日に決定した「特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除に関する考え方」(原子力災害対策本部・復興推進会議)に基づき、2020年代をかけて、帰還意向のある住民が帰還できるよう、避難指示解除の取組を進めます。
(5)復興の新たなステージに向けた未来志向の取組
地域のニーズに応え、環境再生の取組のみならず、脱炭素、資源循環、自然共生といった環境の視点から地域の強みを創造・再発見する「福島再生・未来志向プロジェクト」を推進しています。
本プロジェクトでは2020年8月に福島県と締結した「福島の復興に向けた未来志向の環境施策推進に関する連携協力協定」を踏まえ、福島県や関係自治体と連携しつつ脱炭素・風評対策・風化対策の三つの視点から施策を進めていきます。
(6)放射性物質による環境汚染対策についての検討
放射性物質による環境汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第60号)において放射性物質に係る適用除外規定の削除が行われなかった廃棄物処理法、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)その他の法律の取扱いについて、放射性物質汚染対処特措法の施行状況の点検結果を踏まえて検討します。
第5節 万全な災害廃棄物処理体制の構築
平時から災害時における生活ごみ、避難所ごみやし尿に加え、災害廃棄物の処理を適正かつ円滑・迅速に実施するため、国、地方公共団体、研究・専門機関、民間事業者等の連携を促進するなど、引き続き、地方公共団体レベル、地域レベル、全国レベルで重層的に廃棄物処理システムの強靱化を進めるとともに、関係機関等における連携強化等を進めます。
1 地方公共団体レベルでの災害廃棄物対策の加速化
地方公共団体における災害廃棄物処理計画の策定を推進するとともに、これまでの災害対応における検証結果を踏まえ、災害廃棄物対策の実効性の向上に向けた処理計画の点検・見直しに関してモデル事業等の支援を行います。また、地方公共団体における災害廃棄物分野の人材育成による支援人材の拡充を図るとともに、大規模災害発生時においても、生活環境の保全と衛生が保たれるよう、地方公共団体の災害対応拠点となり得る廃棄物処理施設の整備を支援します。
2 地域レベルでの災害廃棄物広域連携体制の構築
全国8つの地域ブロック協議会を継続的に運営し、これまでの災害対応における効果的なブロック内連携の実績を踏まえ、都道府県域を越えた実効性のある広域連携体制を構築し、災害時の円滑な廃棄物処理体制を構築するため、災害廃棄物対策行動計画の見直しを行います。また、災害時に円滑に体制を構築するため、地域ブロック単位の共同訓練等を開催するとともに、自治体による災害対策が強化されるよう、情報共有や人材交流の場の設置、啓発セミナー等を実施します。
3 全国レベルでの災害廃棄物広域連携体制の構築
全国各地で発生した非常災害における災害廃棄物処理に関する実績を継続的に蓄積・検証し、南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模災害に備えた災害廃棄物処理システムの更なる強靱(じん)化を推進します。蓄積・検証した教訓を活用し、災害廃棄物処理支援ネットワーク(D.Waste-Net)メンバーや関係機関との連携を強化して、より効果的な災害廃棄物処理体制の構築を図ります。加えて、「災害廃棄物処理支援員制度」を継続的に運用するとともに、支援員の発災時の支援活動の強化を図ります。また、地域ブロックをまたぐ連携方策の検討を進め、大規模災害に備えた支援体制の構築を図ります。
港湾においては、災害廃棄物の広域処理を円滑かつ適正に実施できるよう、港湾を活用した海上輸送に関する手順や留意事項等を整理したガイドライン(案)を取りまとめます。
第6節 適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進
1 適正な国際資源循環体制の構築
不法輸出入対策について、関係省庁、関係国・関係国際機関との連携を一層進め、取締りの実効性を確保します。
2021年1月に効力が生じたバーゼル条約改正附属書及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第24号)に基づき、プラスチックの廃棄物の輸出入を適正に管理し、輸入国における環境汚染の防止に努めます。
2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再生利用のための香港国際条約(シップ・リサイクル条約)に基づき、2018年6月に成立・公布された船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成30年法律第61号)の円滑な施行に向けて船舶の適切な解体に向けた取組を進めます。
2021年5月のG7気候・環境大臣会合において合意された「循環経済及び資源効率の原則」の策定や、同年7月のG20環境大臣会合で合意された、各国における循環経済の取組事例や指標に関するポータルサイトの設立等の取組を通じて、循環経済の世界的な移行に貢献します。
「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」等を通じ、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向けて、G20全体での資源効率性の向上や循環経済への移行の推進、海洋ごみ対策の推進に貢献します。
経済協力開発機構(OECD)や国連環境計画(UNEP)国際資源パネル(IRP)、UNEP国際環境技術センター(IETC)、短寿命気候汚染物質削減のための気候と大気浄化のコアリション(CCAC)、バーゼル条約等の活動等に積極的に貢献します。
我が国とつながりの深いアジア太平洋諸国において循環型社会が構築されるよう、アジア太平洋3R・循環経済推進フォーラム等を通じて、3R及び循環経済推進に関する情報共有や合意形成を推進するとともに、アジア太平洋3R白書等を通じた基礎情報の整備に努めるほか、日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)や北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)等を通じて関係国間での海洋ごみ対策に関する取組を進めます。
2017年4月に我が国が設立した「アフリカのきれいな街プラットフォーム(ACCP)」の活動として、2019年8月に第2回全体会合で採択された「ACCP横浜行動指針」に基づき、廃棄物管理に関する知見の共有・情報整備や廃棄物管理制度・技術に関する研修等の活動を進めていきます。
相手国との協力覚書の締結や環境政策対話、両国が合同で開催する委員会・ワークショップ等、独立行政法人国際協力機構(JICA)等による専門家の派遣、研修員受入れ等を通じ、地方公共団体等とも連携しながら、相手国における循環型社会構築や3R推進、適正処分等を通じて、循環経済への移行促進や環境改善や衛生状態の向上につなげます。
2 循環産業の海外展開の推進
「インフラシステム海外展開戦略2025」等に基づき、途上国・新興国のニーズを踏まえた上で、廃棄物処理・リサイクル分野における我が国の質の高い環境インフラの国際展開支援を、地方公共団体等とも連携しながら行います。具体的には、二国間政策対話・地域フォーラムを活用したトップセールス、制度から技術、ファイナンスまでのパッケージでの支援、実現可能性調査や個別プロジェクト形成のフォローアップを行います。また、研修の実施、専門家等の派遣、相手国の自治体・政府との政策対話・ワークショップの開催等を進めます。
海外の循環産業の発展に貢献するため、産業廃棄物処理業における技能実習制度の活用など、人材育成の方策についての検討を進めます。
我が国の災害廃棄物対策に係るノウハウを提供するとともに、関係機関と連携した被災国支援スキームの構築等に取り組みます。
第7節 循環分野における基盤整備
1 循環分野における情報の整備
「循環基本計画」の指標の更なる改善に向けた取組とともに、その裏付けとなるデータの改善・整備を並行して推進します。「第四次循環基本計画」において「今後の検討課題等」とされた事項等について、指標に関する検討会にて、引き続き検討します。また、各主体が循環型社会形成に向けた取組を自ら評価し、向上していくために、取組の成果を評価する手法や分かりやすく示す指標について検討します。
2 循環分野における技術開発、最新技術の活用と対応
デジタル技術・ICT・AI・リモートコントロール技術・ビッグデータの活用など高度な技術や新たなサービスの開発・導入や、災害廃棄物処理の円滑化・高効率化を推進するため、ITや最新技術を活用して、被災家屋の被害の推計手法の高度化を図ります。また、収集運搬と中間処理の効率化を実現し、更なるCO2排出削減を図るため、ICTを活用したごみ収集車が自動運転により作業員を追尾する実証を行います。
地域循環共生圏形成に資する廃棄物処理システムの構築に関する研究・技術開発、ライフサイクル全体での徹底的な資源循環に関する研究・技術開発、社会構造の変化に対応した持続可能な廃棄物の適正処理の確保に関する研究・技術開発等の実施により、環境政策の推進にとって不可欠な科学的知見の集積及び技術開発を推進します。
3 循環分野における人材育成、普及啓発等
地域において資源循環を担う幅広い分野の総合的な人材の育成や主体間の連携を促進します。
国民に向けたアプローチとしては、「限りある資源を未来につなぐ。今、僕らにできること。」をキーメッセージとしたウェブサイト「Re-Style」からの情報発信、3R行動を促進する消費者キャンペーン「選ぼう!3Rキャンペーン」、「Re-Style FES!」イベント等を通じて、意識醸成や行動喚起を促進します。
環境省及び3R活動推進フォーラムは、2022年度に「第16回3R推進全国大会」を共催し、同イベントを通じて、3Rによる循環型社会づくりを推進するため、地方公共団体との連携体制を推進します。
産業廃棄物処理業における人材育成の方策について、業界団体等によるより実効的な研修や講習の実施など、職員の能力・知識の向上を一層推進するための取組について必要な検討を進めます。
海洋プラスチックごみの削減に向けプラスチックとの賢い付き合い方を全国的に推進する「プラスチック・スマート」の展開を通して、海洋プラスチックごみ汚染の実態の正しい理解を促しつつ、国民的気運を醸成し、幅広い関係主体の連携協同を促進します。
第4章 水環境、土壌環境、地盤環境、海洋環境、大気環境の保全に関する取組
第1節 健全な水循環の維持・回復
健全な水循環の維持又は回復に当たっては、河川の流入先の沿岸域も含め流域全体を総合的に捉え、それぞれの地域に応じて、各主体がより一層の連携を図りつつ、次のような流域に共通する取組を進めるとともに、地域の特性に応じた課題を取り込みつつ、取組を展開していきます。
1 流域における取組
流域全体を総合的に捉え、効率的かつ持続的な水利用等を今後とも推進していくため、水の再利用等による効率的利用、水利用の合理化、雨水の利用等を進めるとともに、必要に応じて、未活用水の有効活用、環境用水の導入、ダムの弾力的管理を図り、水質や水生生物等の保全等の観点から、流量変動も考慮しつつ、流量確保のための様々な施策を行います。
流域全体を通じて、貯留浸透・涵(かん)養能力の維持・向上を図り、湧水の保全・復活に取り組むほか、降雨時等も含め、地下水を含む流域全体の水循環や栄養塩類等の物質循環の把握を進め、地域の特性を踏まえた適切な管理方策の検討を行います。その際、地下水については、共有資源としての性格にも留意し、地下水流域の観点に立って検討を行います。さらに、流水は、土砂の移動にも役割を果たしていることから、流域の源頭部から海岸までの総合的な土砂管理の観点から、関係機関と連携し、土砂移動の調査研究や下流への土砂還元対策に取り組みます。
より一層の生物多様性の確保を図るため、水辺地を含む流域の生態系を視野に入れた水辺地の保全・再生に取り組み、多様な水生生物の種や個体群等の保全を図ります。
気温の上昇や短時間強雨の頻度の増加等の気候変動により、水温上昇、水質や生態系の変化等の水環境への影響が予想されることから、これらの観測・監視や影響評価等の調査研究により知見を蓄積し、適応策について検討を行います。
地震等災害時等においても、国民生活上最低限求められる水循環を確保できるよう、災害に強くエネルギー効率の高い適切な規模の水処理システムや水利用システムの構築や災害時の水環境管理の方策の確立など様々な施策を推進します。
これらの施策を推進していくためにも、水環境に精通した人材育成が欠かせないことから、国立研究開発法人国立環境研究所の政策支援機能や地方の研究機関、大学等との連携・調整機能の強化を図ります。また、水域の物質循環機構、生物多様性や生息・再生産機構の解明、モニタリングデータの解析・評価など良好な水環境の形成に資する調査研究や科学技術の進歩を活かした技術開発を推進します。
2 森林、農村等における取組
森林は水源涵(かん)養機能、生物多様性保全機能など水環境の保全に資する多様な公益的機能を有しており、それらの機能の維持、向上のため、水源地対策の一環として、保安林等の法制度の活用や治山施設の整備等により、森林の保全を推進します。また、流域全体を通じて森林所有者等による森林の適正な整備を推進するとともに、水源涵(かん)養機能等の発揮を図るための適正な整備を必要とするものについては、公的主体による森林の整備を推進します。さらに、渓畔林など水辺森林の保全・管理に際して水環境の保全により一層配慮するとともに、森林の公益的機能に着目した基金を地域の特性を踏まえて活用することやボランティア活動など流域の住民や事業者が参加した森林の保全・整備の取組を推進します。なお、森林整備に当たっては、地域の実情を踏まえて、長伐期化や複層林化など、多様で健全な森林づくりを通じて保水能力の高い森林の育成に努めます。
農村・都市郊外部においては、川の流れの保全や回復、流域の貯留浸透・涵(かん)養能力の保全・向上、面源からの負荷削減のため、里地里山の保全、緑地の保全、緑化、適正な施肥の実施、家畜排せつ物の適正な管理を推進します。水源涵(かん)養機能等の農業の多面的機能は、農業の持続的な営みを通じて発揮されることから、水田や畑地の保全を推進し、荒廃農地の発生を防止します。また、地域住民を含め多様な主体の参画を得て、水田や水路、ため池など農地周りの水環境の保全活動を進めるとともに、環境との調和に配慮しつつ基盤整備を推進します。
3 水環境に親しむ基盤づくり
都市部においては、水循環の変化による問題が現れやすく、河川流量の減少、親水性の低下、ヒートアイランド現象等が依然として問題となっており、貯留浸透・涵(かん)養機能の回復など、可能な限り自然の水循環の恩恵を増加させる方向で関連施策の展開を図る必要があることから、地下水涵(かん)養機能の増進や都市における貴重な貯留・涵(かん)養能力を持つ空間である緑地の保全と緑化を推進するとともに、都市内の水路等の創出・保全を図ります。
地下水涵(かん)養に資する雨水浸透施設の整備、流出抑制型下水道の整備、透水性舗装の促進等を進めます。さらに、雨水や下水再生水の利用を進めるとともに、貯水池の弾力的な運用や下水の高度処理水等の河川還元等による流量の確保等の取組を進めます。河川整備に際しては、多自然川づくりを基本として自然に配慮することなどにより水辺の自然環境を改善し、生物の良好な生息・生育・繁殖環境の保全・創出に努めます。このほか、親水性の向上、ヒートアイランド対策等への活用が有効な地域では、都市内河川、下水の高度処理水等の利用や地中熱、下水熱の利用を環境影響に配慮しつつ進めます。
第2節 水環境の保全
1 環境基準の設定、排水管理の実施等
水質汚濁に係る環境基準については、水環境中での存在状況や有害性情報等の知見の収集・集積を引き続き行い、必要な見直し等を実施します。また、国が類型指定を行った水域について随時必要な見直しを行うとともに、2016年3月に生活環境項目環境基準に設定された底層溶存酸素量については、新たな水域類型の指定を実施します。
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づき、国及び地方公共団体は、公共用水域及び地下水の水質について、放射性物質を含め、引き続き常時監視を行います。また、要監視項目についても、地域の実情に応じて水質測定を行います。
工場・事業場については適切な排水規制を行うとともに、水質汚濁に係る環境基準の見直し等の状況に応じ必要な対策等の検討を進めます。また、各業種の排水実態等を適切に把握しつつ、特に経過措置として一部の業種に対して期限付きで設定されている暫定排水基準については、随時必要な見直しを行います。
2 湖沼
湖沼については、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)に基づく「湖沼水質保全計画」が策定されている11の指定湖沼について、同計画に基づき、各種規制措置のほか、下水道及び浄化槽の整備、その他の事業を総合的に推進します。
浄化の機能及び生物多様性の保全及び回復の観点から、湖辺域の植生や水生生物の保全など、湖辺環境の保全を図ります。
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)に基づき主務大臣が定めた「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」及び滋賀県が策定した「琵琶湖保全再生施策に関する計画」等を踏まえ、関係機関と連携して各種施策を推進します。
3 閉鎖性海域
閉鎖性海域については、流域からの負荷削減の取組が進んでいるものの、底質環境の悪化や内部生産の影響により貧酸素水塊が発生するなど依然として問題が生じています。このため、引き続き必要な負荷削減に取り組むとともに、浄化機能及び生物多様性の確保の観点から、自然海岸、干潟、藻場等について、適切な保全を図り、干潟・海浜、藻場等の再生、覆砂等による底質環境の改善、貧酸素水塊が発生する原因の一つである深堀跡について埋戻し等の対策、失われた生態系の機能を補完する環境配慮型構造物等の導入など健全な生態系の保全・再生・創出に向けた取組を推進します。その際、「里海」づくりの考え方を取り入れつつ、流域全体を視野に入れて、官民で連携した総合的施策を推進します。また、漂流ごみや流出油の円滑な回収・処理に努めます。
瀬戸内海については、2021年6月に公布された瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第59号)を踏まえ、湾・灘ごと、さらには湾・灘内の特定の海域ごと、また、季節ごとの実情に応じた施策を引き続き検討・実施します。有明海及び八代海等については、再生に係る評価及び基本方針に基づく再生のための施策を推進します。
4 汚水処理施設の整備
水質環境基準等の達成、維持を図るため、工場・事業場排水、生活排水、市街地・農地等の非特定汚染源からの排水等の発生形態に応じ、水質汚濁防止法等に基づく排水規制、水質総量削減、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬の規制、下水道、農業集落排水施設及び浄化槽等の生活排水処理施設の整備等の汚濁負荷対策を推進します。
関係機関が連携して水環境の保全を進めるとの考えの下、生活排水処理を進めるに当たっては、人口減少など社会構造の変化等を踏まえつつ、地域の実情に応じて、より効率的な汚水処理施設の整備や既存施設の計画的な更新や再構築を進めるとともに、河川水を取水、利用した後の排水については、地域の特性に応じて見直しを含めた取排水系統の検討を行います。
今般、単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換と浄化槽の管理の向上について、議員立法により浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号。以下「改正浄化槽法」という。)が、2019年6月に成立・公布され、2020年4月に施行されました。
改正浄化槽法において、緊急性の高い単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換に関する措置、浄化槽処理促進区域の指定、公共浄化槽の設置に関する手続き、浄化槽の使用の休止手続き、浄化槽台帳の整備の義務付け、協議会の設置、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保、環境大臣の責務に関する仕組みが新たに創設されており、これらの取組を進めることで単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換を進めるとともに浄化槽の管理の向上を推進します。
5 地下水
地下水の水質については、水質汚濁防止法に基づく有害物質の地下浸透規制や、有害物質を貯蔵する施設の構造等に関する基準の遵守及び定期点検等により、地下水汚染の未然防止の取組を進めます。また、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染対策について、地域における取組支援の事例等を地方公共団体に提供したり、「硝酸性窒素等地域総合対策ガイドライン」の周知を図るなど、負荷低減対策の促進方策に関する検討を進めます。
第3節 アジアにおける水環境保全の推進
アジアにおける水環境の改善を図るため、2021年6月に政府が取りまとめた「インフラシステム海外展開戦略2025」の下で、アジア諸国の行政官のネットワークにおいて、水環境管理に携わる関係者間の協力体制を構築し、情報収集・普及や人材育成・能力構築等を通じた水環境ガバナンスを強化します。また、我が国の民間企業が持つ排水処理技術の実現可能性調査や現地実証試験等のモデル事業を通じたアジア、大洋州諸国への水処理技術等の海外展開を支援します。
第4節 土壌環境の保全
1 市街地等の土壌汚染対策
土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進し、人の健康への影響を防止するため、2017年5月に公布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)による改正後の土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染の適切な調査や対策を推進します。また、ダイオキシン類による土壌汚染については、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に基づき、早急かつ的確な対策が実施されるよう必要な支援に努めます。
2 農用地の土壌汚染対策
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づき、特定有害物質による農用地の土壌汚染を防止又は除去するための対策事業を進めます。
第5節 地盤環境の保全
地下水位の低下により発生する地盤沈下等の障害を防ぐため、地下水採取の規制を継続して行うとともに、関係省庁との連携を一層強化し、健全な水循環の確保に向けた取組を推進します。また、地下水・地盤環境の保全に留意しつつ地中熱利用の普及を促進するため、「地中熱利用にあたってのガイドライン」の改訂に向けた検討を行います。
第6節 海洋環境の保全
1 海洋ごみ対策
美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年法律第82号)及び同法に基づく基本方針、海洋プラスチックごみ対策アクションプラン(2019年5月)、その他関係法令等に基づき、マイクロプラスチックを含む海洋ごみの分布状況や生態系への影響等に関する調査研究、地方公共団体等が行う海洋ごみの回収処理・発生抑制対策への財政支援、使い捨てプラスチック容器包装等のリデュース、使用後の分別意識向上、リサイクル、不法投棄防止を含めた適正な処分の確保等について、普及啓発を含めて総合的に推進します。また、海洋中のマイクロプラスチックの供給源の一つと考えられる河川水中のマイクロプラスチックについても実態を把握するための調査に取り組みます。
海洋環境整備船を活用した漂流ごみ回収の取組を実施します。また、外国由来の海洋ごみへの対応も含めた国際連携として、マイクロプラスチックの世界的なデータ集約に向けたデータ共有システムの整備、関係国の施策等に関する情報交換、調査研究等に関する協力を進めます。
船舶起源の海洋プラスチックごみの削減に向けて、実態の把握や指導・啓発活動に取り組むとともに、国際海事機関(IMO)等における議論に積極的に参画していきます。
2 海洋汚染の防止等
ロンドン条約1996年議定書を国内担保する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき、廃棄物の海洋投入処分及びCO2の海底下廃棄等に係る許可制度の適切な運用等を着実に実施するとともに、船舶バラスト水規制管理条約及び船舶汚染防止国際条約(MARPOL条約)等に基づくバラスト水処理装置等の審査や未査定液体物質の査定、1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約(OPRC条約)等に基づく排出油等の防除体制の整備等を適切に実施します。また、船舶事故等で発生する流出油による海洋汚染の拡散防止等を図るため、関係機関と連携し、大型浚渫(しゅんせつ)兼油回収船を活用するなど、流出油の回収を実施します。さらに、我が国周辺海域における海洋環境データ及び科学的知見の集積、北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)等への参画等を通じた国際的な連携・協力体制の構築等を推進します。
3 生物多様性の確保等
海洋保護区の設定及びサンゴ礁生態系の保全に関しては、第2章第4節を参照。
サンゴ礁生態系の保全の国際的取組については、第2章第7節8を参照。
4 沿岸域の総合的管理
森里川海のつながりや自然災害への対応、流域全体の水循環等を意識した沿岸域の総合的管理を推進するため、総合的な土砂管理、防護・環境・利用が調和した海岸空間の保全、生態系を活用した防災・減災を推進します。閉鎖性海域に関して、環境負荷の適正管理や保全・再生に向けた施策を実施するとともに、「きれいで豊かな海」の確保に向け、水質・海水温・生物生息場の変化等と水産資源等の関係性に関する調査研究を行い、科学的知見を踏まえた対策の在り方に関する検討等を実施します。
5 気候変動・海洋酸性化への対応
海水温上昇や海洋酸性化等の海洋環境変動の実態とそれらによる海洋生態系に対する影響を的確に把握するため、海洋における監視・観測の継続的な実施とともに、観測データの充実・精緻(ち)化や効率的な観測等のための取組を行います。また、気候変動及びその影響の予測・評価に関する取組を進めるとともに、海洋における適応策に関する各種取組を実施します。
6 海洋の開発・利用と環境の保全との調和
洋上風力発電、二酸化炭素回収・貯留(CCS)等の海洋の開発・利用の際には、環境の保全との調和を図りつつ取り組むことが重要であるため、今後の沖合域や深海域における海洋の開発・利用に関して、国内外での取組状況や国際的な議論も考慮しつつ、環境への影響を把握する上で必要となるデータを収集するとともに、環境への影響の評価の在り方に関する検討を行います。
生物多様性保全と持続的経済活動を調和した海洋生態系の保全利用計画の実現のため、ビッグデータを活用した分析技術を開発し、それらを基に温暖化・沿岸開発・漁業・海運に関係した海の生物多様性と生態系サービスの劣化リスク評価等を実施します。
7 海洋環境に関するモニタリング・調査研究の推進
海洋環境や海洋生態系の状況を的確に把握するため、我が国領海及び排他的経済水域における海洋環境モニタリング(監視・観測)を継続的に実施します。
第7節 大気環境の保全
1 窒素酸化物・光化学オキシダント・PM2.5等に係る対策
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づく固定発生源対策及び移動発生源対策等を引き続き適切に実施するとともに、光化学オキシダント及びPM2.5の生成の原因となり得る窒素酸化物(NOX)、揮発性有機化合物(VOC)について、排出実態や科学的知見、排出抑制技術(対策効果の定量的予測・評価を可能とするシミュレーションの高度化を含む。)の開発・普及の状況等を踏まえて、経済的及び技術的考慮を払いつつ、対策を進めます。また、PM2.5については、集積した知見を踏まえ、高濃度地域に着目しつつ、より効果的な排出抑制策の検討を進めます。加えて、光化学オキシダントについては、人健康影響に加え、植物によるCO2吸収を阻害するため、気候変動という観点でも影響が懸念されている大気汚染物質になります。このような背景を踏まえ、2022年1月の中央環境審議会大気・騒音振動部会では、光化学オキシダント対策に係るワーキングプランを示し、気候変動対策・大気環境改善に資する総合的な対策について検討を進めています。
(1)ばい煙に係る固定発生源対策
大気汚染防止法に基づく排出規制の状況、科学的知見や排出抑制技術の開発・普及の状況等を踏まえて、経済的及び技術的考慮を払いつつ、追加的な排出抑制策の可能性を検討します。
(2)移動発生源対策
自動車排出ガス規制(オフロード特殊自動車も含む。)及び自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)に基づく車種規制を引き続き実施するとともに、環境性能に優れた低公害車の普及等を引き続き促進します。また、大気環境保全の観点から、自動車排出ガス低減技術の進展を見据えつつ、国内の大気環境、走行実態及び国際基準への調和等を考慮した許容限度の見直しに資する検討を進めます。
道路交通情報通信システム(VICS)やETC2.0、高度化光ビーコン等を活用した道路交通情報の内容・精度の改善・充実、信号機の改良、公共車両優先システム(PTPS)の整備等の高度道路交通システム(ITS)の推進、観光地周辺の渋滞対策、総合的な駐車対策の効果的実施等の交通流の円滑化対策を推進します。
これらの対策に加え、エコドライブの普及啓発を実施するとともに、公共交通機関への利用転換による低公害化・低炭素化を促進します。
(3)VOC対策
VOCの排出量の実態把握を進めることなどにより排出抑制対策の検討を行うとともに、法規制と自主的取組のベストミックスによる排出抑制対策を引き続き進めます。
大気環境配慮型SS(e→AS(イーアス))認定制度を通じて、VOCの一種である燃料蒸発ガスを回収する機能を有する給油機(Stage2)の利用促進・普及促進を図ります。
(4)監視・観測、調査研究
大気汚染の状況を全国的な視野で把握するとともに、大気保全施策の推進等に必要な基礎資料を得るため、大気汚染防止法に基づき、都道府県等で常時監視を行っています。引き続き、リアルタイムに収集した測定データ(速報値)、都道府県等が発令した光化学オキシダント注意報等やPM2.5注意喚起の情報を「大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)」により、国民に分かりやすく情報提供を行います。その他、酸性雨や黄砂、越境大気汚染の長期的な影響を把握することを目的としたモニタリングや放射性物質モニタリングを引き続き実施します。また、PM2.5と光化学オキシダントは発生源や原因物質において共通するものが多いことに鑑み、両者の総合的対策に向け科学的知見の充実を図ります。
2 アジアにおける大気汚染対策
アジア地域におけるPM2.5、光化学オキシダント等の大気汚染の改善に向け、コベネフィット(共通便益)・アプローチも活用しながら、様々な二国間・多国間協力を通じて大気汚染対策を推進します。
(1)二国間協力
モンゴルとのコベネフィット事業や韓国とのPM2.5の発生源解析等に関する共同研究による科学的知見の集積等を通じて、我が国の知見やノウハウを相手国に提供するとともに、我が国の技術の海外展開等を図り、広くアジア地域の大気環境改善や気候変動対策に貢献します。
(2)日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)の下の協力
日中韓三か国間の大気汚染に関する政策対話、黄砂に関する共同研究等において、最新情報の共有や意見交換を実施することで、三か国の政策や技術の向上を図ります。
(3)多国間協力
アジア地域規模での広域的な大気環境改善を目指し、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)、アジア太平洋クリーン・エア・パートナーシップ(APCAP)等の既存の枠組みにおける活動を推進します。
3 多様な有害物質による健康影響の防止
(1)アスベスト(石綿)対策
引き続き、大気中の石綿濃度の調査を実施するとともに、石綿を使用している建築物の解体等工事における発注者の届出や施工者の作業基準の遵守等の徹底を図ることや、改正法の周知を徹底するなど、石綿の飛散防止を進めます。
(2)水銀大気排出対策
水銀に関する水俣条約を踏まえて改正された大気汚染防止法に基づく水銀大気排出対策の着実な実施を図るため、引き続き、地方公共団体や関係団体等の協力を得て、水銀排出施設及び要排出抑制施設における水銀濃度測定結果の把握や、水銀大気排出インベントリーの作成等を行います。これらの情報を基に、必要に応じて新たな措置を検討するなど、水銀大気排出対策を推進します。
(3)有害大気汚染物質対策等
引き続き、地方公共団体と連携して有害大気汚染物質の排出削減を図るとともに、有害大気汚染物質等の大気環境モニタリング調査を実施します。特に、酸化エチレン等の有害大気汚染物質について、環境目標値の設定・再評価や健康被害の未然防止に効果的な対策の在り方について検討するとともに、残留性有機汚染物質(POPs)等の化学物質に関しても、知見の収集に努めます。
4 地域の生活環境保全に関する取組
(1)騒音・振動対策
ア 自動車交通騒音・振動対策
車両の低騒音化、道路構造対策、交通流対策や、住宅の防音工事等のばく露側対策に加え、沿道に新たな住居等が立地される前に騒音状況を情報提供するなどにより、騒音問題の未然防止を図ります。また、自動車騒音低減技術の進展を見据えつつ、自動車交通騒音への影響や、国内の走行実態及び国際基準への調和等を考慮した許容限度の見直しに資する検討を進めます。
イ 鉄道騒音・振動、航空機騒音対策
鉄道騒音・振動、航空機騒音の状況把握や予測・評価手法の検討を進めるとともに、車両の低騒音化等の発生源対策や住宅の防音工事等のばく露側対策に加え、騒音状況の情報提供等により騒音問題の未然防止を図ります。さらに、土地利用対策について、関係省庁や沿線自治体と連携しながら推進していきます。
ウ 工場・事業場及び建設作業の騒音・振動対策
最新の知見の収集・分析等を行い、騒音・振動の評価方法等についての検討を行います。また、従来の規制的手法による対策に加え、最新の技術動向等を踏まえ、情報的手法及び自主的取組手法を活用した発生源側の取組を促進します。
エ 低周波音その他の対策
従来の環境基準や規制を必ずしも適用できない新しい騒音問題について対策を検討するために必要な科学的知見を集積します。風力発電施設や家庭用機器等から発生する騒音・低周波音については、その発生・伝搬状況や周辺住民の健康影響との因果関係、わずらわしさを感じさせやすいと言われている純音性成分など、未解明な部分について引き続き調査研究を進めます。
(2)悪臭対策
最新の知見を踏まえた分析手法の見直しを検討するとともに、排出規制、技術支援及び普及啓発を進めます。
(3)ヒートアイランド対策
近年の暑熱環境や今後の見通しを踏まえ、人工排熱の低減、地表面被覆の改善、都市形態の改善、ライフスタイルの改善、人の健康への影響等を軽減する適応策の推進を柱とするヒートアイランド対策を推進します。また、暑さ指数(WBGT)等の熱中症予防情報の提供を実施します。
(4)光害(ひかりがい)対策等
光害(ひかりがい)対策ガイドライン等を活用し、良好な光環境の形成に向け、普及啓発を図ります。また、星空観察の推進を図り、より一層大気環境保全に関心を深められるよう取組を推進します。
(5)効果的な公害防止の取組の促進
2010年1月の中央環境審議会答申「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について」を踏まえ、事業者や地方公共団体が公害防止を促進するための方策等を引き続き検討・実施します。
第5章 包括的な化学物質対策に関する取組
第1節 化学物質のリスク評価の推進及びライフサイクル全体のリスクの削減
化学物質関連施策を講じる上で必要となる各種環境調査・モニタリング等について、各施策の課題、分析法等の調査技術の向上を踏まえ、適宜、調査手法への反映や集積した調査結果の体系的整理等を図りながら、引き続き着実に実施します。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質審査規制法)(昭和48年法律第117号)に基づき化学物質のリスク評価を行い、著しいリスクがあるものを第二種特定化学物質に指定します。その結果に基づき、所要の措置を講じるなど同法に基づく措置を適切に行います。
リスク評価をより効率的に進めるため、化学物質の有害性評価について、定量的構造活性相関(QSAR)等の活用について検討し、より幅広く有害性を評価することができるよう取り組みます。また、化学物質の製造から廃棄までのライフサイクル全体のリスク評価手法、海域におけるリスク評価手法等の新たな手法の検討を行います。
農薬については、2020年4月に完全施行された改正農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、生活環境動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定等を適切に実施します。また、2021年度に開始された既登録農薬の再評価について、円滑に評価を進めるための事前相談に対応しつつ、国内での使用量が多い農薬から順次評価を実施します。さらに、長期ばく露による影響に関するリスク評価手法を確立するための検討を行い、農薬登録制度における生態影響評価の拡充を進めます。
環境中に存在する医薬品等については、環境中の生物に及ぼす影響に着目した情報収集を行い、生態毒性試験、環境調査及び環境リスク評価を進めます。
物の燃焼や化学物質の環境中での分解等に伴い非意図的に生成される物質、環境への排出経路や人へのばく露経路が明らかでない物質等については、人の健康や環境への影響が懸念される物質群の絞り込みを行い、文献情報、モニタリング結果等を用いた初期的なリスク評価を実施します。
リスク評価の結果に基づき、ライフサイクルの各段階でのリスク管理方法について整合を確保し、必要に応じてそれらの見直しを検討します。特に、リサイクル及び廃棄段階において、「循環型社会形成推進基本計画」を踏まえ、資源循環と化学物質管理の両立、拡大生産者責任の徹底、製品製造段階からの環境配慮設計及び廃棄物データシート(WDS)の普及等による適切な情報伝達の更なる推進を図ります。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「化学物質排出把握管理促進法」という。)に基づく化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)及び安全データシート制度(SDS制度)の適切な運用により、化学物質の排出に係る事業者の自主的管理の改善及び環境保全上の支障の未然防止を図ります。特に、最新の科学的知見や国内外の動向を踏まえて改正した化学物質排出把握管理促進法施行令(平成12年政令第138号)及び同法施行規則(平成13年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)の内容について、届出事業者等への周知等を図り、2023年4月の施行に向けた準備を進めます。また、PRTR制度により得られる排出・移動量のデータを、正確性や信頼性を確保しながら引き続き公表することなどにより、リスク評価等への活用を進めます。さらに、SDS制度により特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供を行います。
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づく有害大気汚染物質対策並びに水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排水規制及び地下水汚染対策等を引き続き適切に実施し、排出削減を図るとともに、新たな情報の収集に努め、必要に応じて更なる対策について検討します。特に、酸化エチレン等の有害大気汚染物質について、環境目標値の設定・再評価や健康被害の未然防止に効果的な対策の在り方について検討するとともに、残留性有機汚染物質(POPs)等の化学物質に関しても、知見の収集に努めます。非意図的に生成されるダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に基づく対策を引き続き適切に推進します。事故等に関し、有害物質の排出・流出等により環境汚染等が生じないよう、有害物質に関する情報共有や、排出・流出時の監視・拡散防止等を的確に行うための各種施策を推進します。
汚染された土壌及び廃棄物等の負の遺産については、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)等により適正な処理等の対応を進めます。
事業者による有害化学物質の使用・排出抑制やより安全な代替物質への転換等のグリーン・サステイナブルケミストリーと呼ばれる取組を促進するため、代替製品・技術に係る研究開発の推進等の取組を講じます。
第2節 化学物質に関する未解明の問題への対応
科学的に不確実であることをもって対策を遅らせる理由とはせず、科学的知見の充足に努めながら予防的取組方法の考え方に立って、以下を始めとする未解明の問題について対策を講じていきます。
化学物質ばく露等が子供の健康に与える影響を解明するために、2010年度から開始した「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」を引き続き着実に実施します。エコチル調査は、全国で約10万組の親子を対象とした大規模かつ長期の出生コホート調査であり、調査の実施に当たっては、関係機関や学術団体との連携を強化していきます。また、同規模の疫学調査がデンマーク、ノルウェー等でも実施されており、これら諸外国の調査や国際機関との連携も強化していきます。
得られた成果については、シンポジウム等の広報活動や対話の実践等を通じて社会へ還元するとともに、化学物質の適正な管理等に関する施策に活用することにより、安全・安心な子育て環境の構築に役立てていきます。
化学物質の内分泌かく乱作用について、評価手法の確立と評価の実施を加速化し、その結果を踏まえリスク管理に係る所要の措置を講じます。また、経済協力開発機構(OECD)等の取組に参加しつつ、新たな評価手法等の開発検討を進め、併せて国民への情報提供を実施します。
複数の化学物質が同時に人や環境に作用する場合の複合影響や、化学物質が個体群、生態系又は生物多様性に与える影響について、国際的な動向を参照しつつ、科学的知見の集積、機構の解明、評価方法の検討・開発等に取り組みます。その成果を踏まえ、可能なものについてリスク評価を順次進めます。
急速に実用化が進み環境リスクが懸念されるナノ材料について、OECD等の取組に積極的に参加しつつ、その環境リスクに関する知見の集積を図るとともに、環境中挙動の把握やリスク評価手法に関する情報収集を進めることで、状況の早期把握に努めます。
第3節 化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進
国民、事業者、行政等の関係者が化学物質のリスクと便益に係る正確な情報を共有しつつ意思疎通を図ります。具体的には、「化学物質と環境に関する政策対話」等を通じたパートナーシップ、自治体や事業者と周辺住民の間で、化学物質に対する適切な情報の提供を行うことを支援する役割を持つ「化学物質アドバイザー」の活用、あらゆる主体への人材育成及び環境教育、化学物質と環境リスクに関する理解力の向上に向けた各主体の取組及び主体間連携等を推進します。
第4節 化学物質に関する国際協力・国際協調の推進
化学物質のライフサイクル全体を通じた環境リスクの最小化を目指すための国際戦略であるSAICM(サイカム)終了後の2020年以降の枠組みに関する国際的な議論を積極的にリードし、次期枠組みの採択に向け貢献します。さらに、次期枠組みの採択後には、次期枠組みに基づいた国内実施計画の策定を目指します。
水銀に関する水俣条約に関して、国内では水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)に基づき条約の規定を上回る措置を講じるとともに、途上国支援等を通じて条約の実施に貢献します。
POPs関係では、国内実施計画に沿って総合的な対策を推進するほか、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の有効性評価に資するモニタリング結果等必要な情報を確実に収集します。また、国内の優れた技術・経験の伝承と積上げを図りつつ、国際的な技術支援等に貢献します。
OECD等の国際的な枠組みの下、試験・評価手法の開発・国際調和、データの共有等を進めます。子供の健康への化学物質の影響の解明に係る国際協力を推進します。
アジア地域においては、化学物質による環境汚染や健康被害の防止を図るため、モニタリングネットワークや日中韓化学物質管理政策対話等の様々な枠組みにより、我が国の経験と技術を踏まえた積極的な情報発信、国際共同作業、技術支援等を行い、化学物質の適正管理の推進、そのための制度・手法の調和及び協力体制の構築を進めます。
第5節 国内における毒ガス弾等に係る対策
茨城県神栖市の事案については、引き続きジフェニルアルシン酸(有機ヒ素化合物)にばく露された方の症候及び病態の解明を図り、その健康不安の解消等に資することを目的とし、緊急措置事業及び健康影響についての調査研究を実施するとともに、地下水モニタリングを実施することで、ジフェニルアルシン酸による健康影響の発生を未然に防止します。神奈川県平塚市の事案についても、引き続き地下水モニタリングを実施します。
旧軍毒ガス弾等による被害の未然防止を図るため、引き続き土地改変時における所要の環境調査等を実施します。
環境省に設置した毒ガス情報センターにおいては、関係省庁及び地方公共団体の協力を得ながら、継続的に情報収集を行い、集約した情報や一般的な留意事項をパンフレットやウェブサイト等を通じて周知を図ります。
第6章 各種施策の基盤となる施策及び国際的取組に係る施策
第1節 政府の総合的な取組
1 環境基本計画
「第五次環境基本計画」(2018年4月閣議決定)では、目指すべき持続可能な社会の姿として、循環共生型の社会(「環境・生命文明社会」)の実現を掲げています。今後の環境政策の展開に当たっては、経済・社会的課題への対応を見据えた環境分野を横断する6つの重点戦略(経済、国土、地域、暮らし、技術、国際)を設定し、それに位置付けられた施策を推進するとともに、環境リスク管理等の環境保全の取組は、重点戦略を支える環境政策として揺るぎなく着実に推進していきます。
環境基本計画の着実な実行を確保するため、2022年度において中央環境審議会は、重点戦略、重点戦略を支える環境政策等について、関係府省からのヒアリングの実施等により個別施策の進捗状況を点検し、その結果を踏まえ、本計画の点検分野に係る総合的な進捗状況に関する報告を取りまとめることとしています。
2 環境保全経費
政府の予算のうち環境保全に関係する予算について、環境省において見積り方針の調整を図り、環境保全経費として取りまとめます。
第2節 グリーンな経済システムの構築
1 企業戦略における環境ビジネスの拡大・環境配慮の主流化
グリーンな経済システムを構築していくためには、企業戦略における環境配慮の主流化を後押ししていくことが必要です。具体的には、環境経営を促進するため、幅広い事業者へ「エコアクション21」を始めとする環境マネジメントシステムの普及促進を引き続き行うとともに、環境報告ガイドラインや環境報告のための解説書、「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門~OECDガイダンスを参考に~」等の普及を通じ、企業の環境取組、環境報告を促していきます。
グリーン購入・環境配慮契約の推進について、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)(平成12年法律第100号)及び国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)(平成19年法律第56号)に基づく基本方針について適宜見直しを行い、国及び独立行政法人等の各機関が、これらの基本方針に基づきグリーン購入・環境配慮契約に取り組むことで、グリーン製品・サービスに対する需要の拡大を促進していきます。
2 金融を通じたグリーンな経済システムの構築
環境・経済・社会が共に発展し、持続可能な経済成長を遂げるためには、長期的な視点に立ってESG金融(環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)といった非財務情報を考慮する金融)を促進していくことが重要です。このため、環境情報と企業価値に関する関連性に対する投資家の理解の向上や、金融機関が本業を通して環境等に配慮する旨をうたう「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」に対する支援等に取り組みます。
また、産業と金融の建設的な対話を促進するため、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に賛同する企業等により設立された「TCFDコンソーシアム」の活動の支援やシナリオ分析等を含めたTCFD報告書に基づく開示支援等を通じて、企業や金融機関の積極的な情報開示や投資家等による開示情報の適切な利活用を推進していくとともに、産業界と金融界のトップを集めた国際的な会合「TCFDサミット」の継続的な開催を通じて我が国の取組を世界に発信していきます。
金融・投資分野の各業界トップと国が連携し、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として「ESG金融ハイレベル・パネル」を定期的に開催するとともに、ESG金融に関する幅広い関係者を表彰する我が国初の大臣賞である「ESGファイナンス・アワード」を引き続き開催します。
さらに、脱炭素社会の実現に向け、長期的な戦略にのっとった温室効果ガス排出削減の取組に対して資金供給する「トランジション・ファイナンス」について、引き続き検討を行います。
環境事業への投融資を促進するため、民間資金が十分に供給されていない脱炭素化プロジェクトに対する「地域脱炭素投資促進ファンド」からの出資、脱炭素機器のリース料の補助によるESGリースの促進、地域の脱炭素化に資する融資に対する利子補給などにより、再生可能エネルギー事業創出や省エネ設備導入に向けた取組を支援します。加えて、グリーンボンド等の調達に要する費用に対する補助等により資金調達・投資の促進、地域金融機関のESG金融への取組支援等を引き続き実施していきます。
以上により、金融を通じて環境への配慮に適切なインセンティブを与え、金融のグリーン化を進めていきます。
3 グリーンな経済システムの基盤となる税制
2022年度税制改正において、[1]カーボンニュートラル実現に向けたポリシーミックスの検討、[2]地球温暖化対策のための税の着実な実施、[3]公共の危害防止のために設置された施設又は設備(廃棄物処理施設、汚水又は廃液処理施設)に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)、[4]再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)、[5]認定長期優良住宅に係る特例措置の延長(登録免許税、固定資産税、不動産取得税)、[6]認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減の延長(登録免許税)、[7]既存住宅の省エネ改修に係る軽減措置の拡充・延長(所得税、固定資産税)、[8]住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置を講じています。
エネルギー課税、車体課税といった環境関連税制等による環境効果等について、諸外国の状況を含め、総合的・体系的に調査・分析を行い、引き続き税制全体のグリーン化を推進していきます。地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例については、その税収を活用して、エネルギー起源CO2排出削減の諸施策を着実に実施していきます。
第3節 技術開発、調査研究、監視・観測等の充実等
1 環境分野におけるイノベーションの推進
(1)環境研究・技術開発の実施体制の整備
環境研究総合推進費を核とする環境政策に貢献する研究開発の実施、環境研究の中核機関としての国立研究開発法人国立環境研究所の研究開発成果の最大化に向けた機能強化、地域の環境研究拠点の役割強化、環境分野の研究・技術開発や政策立案に貢献する基盤的な情報の整備、地方公共団体の環境研究機関との連携強化、環境調査研修所での研修の充実等を通じた人材育成等により基盤整備に取り組みます。
国立水俣病総合研究センターでは、国の直轄研究機関としての使命を達成するため、2020年4月に策定した今後5か年の計画となる「中期計画2020」に基づき、本計画に掲げる4つの重点項目を基本として、引き続き研究及び業務を積極的に推進します。特に、地元医療機関との共同による脳磁計(MEG)・磁気共鳴画像診断装置(MRI)を活用したヒト健康影響評価及び治療に関する研究、メチル水銀中毒の予防及び治療に関する基礎研究、国内外諸機関との共同による環境中の水銀移行に関する研究並びに水俣病発生地域の地域創生に関する調査・研究等を進めます。
水俣条約発効を踏まえ、水銀分析技術の簡易・効率化を図り、開発途上国に対する技術移転を促進します。水俣病情報センターについては、歴史的資料等保有機関として適切な情報収集及び情報提供を実施します。
国立研究開発法人国立環境研究所では、環境大臣が定めた中長期目標(2021年度~2025年度)を達成するための第5期中長期計画に基づき、「環境研究・環境技術開発の推進戦略について」で提示されている重点的に取り組むべき課題に対応する8つの分野を設置するとともに、戦略的研究プログラムを実施するなど、環境研究の中核的機関として、従来の個別分野を越えて、国内外の研究機関とも連携し、統合的に環境研究を推進します。また、環境研究の各分野における科学的知見の創出、衛星観測及び子どもの健康と環境に関する全国調査に関する事業、国内外機関との連携・協働及び政策貢献を含む研究成果の社会実装を組織的に推進します。さらに、環境情報の収集・整理及び提供と一体的に研究成果の普及に取り組み、情報発信を強化します。加えて、気候変動への適応に関し、我が国の情報基盤の中核としての役割を担うとともに、地方公共団体等を支援し、適応策の推進に貢献します。
地方公共団体の環境関係試験研究機関は、監視測定、分析、調査、基礎データの収集等を広範に実施するほか、地域固有の環境問題等についての研究活動も活発に推進しています。これらの地方環境関係試験研究機関における試験研究の充実強化を図るため、環境省では地方公共団体環境試験研究機関等所長会議を開催するとともに、全国環境研協議会等と共催で環境保全・公害防止研究発表会を開催し、研究者間の情報交換の促進、国と地方環境関係試験研究機関との緊密な連携の確保を図ります。
(2)環境研究・技術開発の推進
環境省では、「環境研究・環境技術開発の推進戦略」(2019年5月環境大臣決定)に基づき、地域循環共生圏とSociety5.0の一体的実現に向けた研究・技術開発を推進します。
特に以下のような研究・技術開発に重点的に取り組み、その成果を社会に適用していきます。
ア 中長期的なあるべき社会像を先導する環境分野におけるイノベーションのための統合的視点からの政策研究の推進
中長期の社会像はどうあるべきかを不断に追求するため、環境と経済・社会の観点を踏まえた、統合的政策研究を推進します。
そのような社会の達成のために、国内外において新たな取組が求められている環境問題の諸課題について、新型コロナウイルス感染症の経済影響を踏まえた環境と経済の相互関係に関する研究、環境の価値の経済的な評価手法、規制や規制緩和、経済的手法の導入等による政策の経済学的な評価手法等を推進し、政策の企画・立案・推進を行うための基盤を提供します。
イ 統合的な研究開発の推進
複数の課題に同時に取り組むWin-Win型の技術開発や、逆にトレードオフを解決するための技術開発など、複数の領域にまたがる課題及び全領域に共通する課題も、コスト縮減や研究開発成果の爆発的な社会への普及の観点から、重点を置いて推進します。また、情報通信技術(ICT)、先端材料技術、モニタリング技術など、分野横断的に必要とされる要素技術については、技術自体を発展させるとともに、個別の研究開発への活用を積極的に促進します。
(3)環境研究・技術開発の効果的な推進方策
研究開発を確実かつ効果的に実施するため、以下の方策に沿った取組を実施します。
ア 各主体の連携による研究技術開発の推進
技術パッケージや経済社会システムの全体最適化を図っていくため、複数の研究技術開発領域にまたがるような研究開発を進めていくだけでなく、一領域の個別の研究開発についても、常に他の研究開発の動向を把握し、その研究開発がどのように社会に反映されるかを意識する必要があります。
このため、研究開発の各主体については、産学官、府省間、国と地方等の更なる連携等を推進し、また、アジア太平洋等との連携・国際的な枠組みづくりにも取り組みます。その際、国や地方公共団体は、関係研究機関を含め、自ら研究開発を行うだけでなく、研究機関の連携支援や、環境技術開発に取り組む民間企業や大学等の研究機関にインセンティブを与えるような研究開発支援を充実させます。
イ 環境技術普及のための取組の推進
研究開発の成果である優れた環境技術を社会に一層普及させていくために、新たな規制や規制緩和、経済的手法、自主的取組手法、特区の活用等、あらゆる政策手法を組み合わせ、環境負荷による社会的コスト(外部不経済)の内部化や、予防的見地から資源制約・環境制約等の将来的なリスクへの対応を促すことにより、環境技術に対する需要を喚起します。また、技術評価を導入するなど、技術のシーズを拾い上げ、個別の技術の普及を支援するような取組を実施していきます。さらに、諸外国と協調して、環境技術に関連する国際標準化や国際的なルール形成を推進します。
環境省や経済産業省では、二酸化炭素回収・貯留(CCS)技術の導入に向けて、火力発電所等の排ガスから商用規模でのCO2分離回収、海底下での安定的な貯留、我が国に適したCCSの円滑な導入手法の検討等を行います。
地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業により、将来的な地球温暖化対策強化につながり、各分野におけるCO2削減効果が相対的に大きいものの、民間の自主的な取組だけでは十分に進まない技術の開発・実証を強力に推進し、その普及を図ります。
環境スタートアップの研究開発・事業化を支援し、持続可能な社会の実現に向けて支援します。環境技術実証事業では、先進的な環境技術の普及に向け、技術の実証やその結果の公表等を引き続き実施します。
ウ 成果の分かりやすい発信と市民参画
研究開発の成果が分かりやすくオープンに提供されることは、政策決定に関わる関係者にとって、環境問題の解決に資する政策形成の基礎となります。そのためには、「なぜその研究が必要だったのか」、「その成果がどうだったのか」に遡って分かりやすい情報発信を実施していきます。また、研究成果について、ウェブサイト、シンポジウム、広報誌、見学会等を積極的に活用しつつ、広く国民に発信し、成果の理解促進のため市民参画を更に強化します。
環境研究総合推進費や地球環境保全等試験研究費等により実施された研究成果について、引き続き広く行政機関、研究機関、民間企業、民間団体等に紹介し、その普及を図ります。
エ 研究開発における評価の充実
研究開発における評価においては、PDCAサイクルを確立し、政策、施策等の達成目標、実施体制等を明確に設定した上で、その推進を図るとともに、進捗状況や研究成果がどれだけ政策・施策に反映されたかについて、適時、適切にフォローアップを行い、実績を踏まえた政策等の見直しや資源配分、さらには新たな政策等の企画立案を行っていきます。
2 官民における監視・観測等の効果的な実施
監視・観測等については、個別法等に基づき、着実な実施を図ります。また、広域的・全球的な監視・観測等については、国際的な連携を図りながら実施します。このため、監視・観測等に係る科学技術の高度化に努めるとともに、実施体制の整備を行います。また、民間における調査・測定等の適正実施、信頼性向上のため、情報提供の充実や技術士(環境部門等)等の資格制度の活用等を進めます。
3 技術開発などに際しての環境配慮等
新しい技術の開発や利用に伴う環境への影響のおそれが予見される場合には、環境に及ぼす影響について技術開発の段階から十分検討し、未然防止の観点から必要な配慮がなされるよう適切な施策を実施します。また、科学的知見の充実に伴って、環境に対する新たなリスクが明らかになった場合には、予防的取組の観点から必要な配慮がなされるよう適切な施策を実施します。
第4節 国際的取組に係る施策
1 地球環境保全等に関する国際協力の推進
(1)質の高い環境インフラの普及
2021年6月に改訂された「インフラシステム海外展開戦略2025」に基づき、質の高い環境インフラの海外展開を進め、途上国の環境改善及び気候変動対策の促進とともに、我が国の経済成長にも貢献していきます。環境インフラ海外展開プラットフォーム(JPRSI)を活用し、官民連携で環境インフラのトータルソリューションを海外に提供するとともに、「脱炭素インフライニシアティブ」の下、二国間クレジット制度(JCM)を通じて環境インフラの海外展開を一層強力に促進していきます。
再エネ水素の国際的なサプライチェーン構築を促進するため、再エネが豊富な第三国と協力し、再エネ由来水素の製造、島嶼(しょ)国等への輸送・利活用の実証事業を実施していきます。
海外での案件においても適切な環境配慮がなされるよう、我が国の環境影響評価に関する知見を活かした諸外国への協力支援や、国際協力機構(JICA)や国際協力銀行(JBIC)等の環境社会配慮に係るガイドラインを踏まえた取組を推進することによって、環境問題が改善に向かうよう努めます。
(2)地域/国際機関との連携・協力
相手国・組織に応じた戦略的な連携や協力を行います。具体的には、アジア諸国やG7を中心とした各国と、政策対話等を通じた連携・協力を深化させます。特に、G7各国とはG7富山環境大臣会合において合意されたG7協調行動計画に基づき、持続可能な開発目標(SDGs)の実施に向けた取組を進めます。ASEAN地域でのSDGs達成のため、「日ASEAN環境協力イニシアティブ」の下、環境分野での協力プロジェクトを促進します。特に、海洋プラスチックごみについては、ASEAN+3の枠組みで「ASEAN+3海洋プラスチックごみ協力アクション・イニシアティブ」に基づき、ASEAN各国及び中国、韓国との連携・協力を図り、東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)内に設立された「海洋プラスチックごみナレッジ・センター」等も活用しながら、海洋プラスチックごみ問題に対処していきます。また、気候変動分野においては、「日ASEAN気候変動アクション・アジェンダ2.0」に基づき、ASEAN諸国の脱炭素社会実現のため、協力を強化します。さらに、日中韓、ASEAN、東アジア首脳会議(EAS)等の地域間枠組みに基づく環境大臣会合に積極的に貢献するとともに、国連環境計画(UNEP)、経済協力開発機構(OECD)、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)、アジア開発銀行(ADB)、東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)等の国際機関等との連携を進めます。
2019年、G20で初めて開催された「持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」で我が国が議長国を務めた経験をもとに、2022年のインドネシア議長国下で開催されるG20での議論に貢献していきます。また、ドイツが議長国を務めるG7については、2023年に我が国が次期議長国となることも念頭に、議論に貢献していきます。
(3)多国間資金や民間資金の積極的活用
多国間資金については、特に、緑の気候基金(GCF)及び世界銀行、地球環境ファシリティ(GEF)に対する貢献を行うほか、ADBに設立された二国間クレジット制度(JCM)日本基金を活用して優れた脱炭素・低炭素技術の普及支援を行います。また、民間資金の動員を拡大するため、環境インフラやプロジェクトの投資に係るリスク緩和に向けた取組を支援します。
(4)国際的な各主体間のネットワークの充実・強化
ア 地方公共団体間の連携
大気の分野では、地方公共団体レベルでの行動を強化するため、我が国の地方公共団体が国際的に行う地方公共団体間の連携の取組を支援し、地方公共団体間の相互学習を通じた能力開発を促します。また、我が国の地方公共団体が有する経験・ノウハウを活用し、海外都市における脱炭素社会の構築に向けた制度構築支援や、二国間クレジット制度(JCM)設備補助事業につながる取組を支援します。
イ 市民レベルでの連携
持続可能な社会を形成していくためには、国や企業だけではなくNGO・NPOを含む市民社会とのパートナーシップの構築が重要です。このため、市民社会が有する情報・知見を共有し発信するような取組や環境保全活動に対する支援を引き続き実施します。
(5)国際的な枠組みにおける主導的役割
地球環境保全に係る国際的な枠組みにおいて主導的な役割を担います。具体的には、SDGsを中核とする持続可能な開発のための2030アジェンダに関する我が国の取組を国際的にも発信するに当たり、国際経済社会局(UNDESA)やアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)等に協力し、関連する国際会議等におけるSDGsのフォローアップ・レビューに貢献していきます。さらに、自由貿易と環境保全を相互支持的に達成させるため、経済連携協定等において環境への配慮が適切にされるよう努めるとともに、これらの協定締結国との間で我が国が強みを有する環境技術等の促進を図っていきます。加えて、パリ協定の実施指針等の策定に向けた交渉に積極的に参加します。このほか、水銀に関する水俣条約では実施・遵守委員会委員として条約の実施と遵守を推進するとともに水銀対策先進国として国際機関とも連携しつつ、我が国が持つ技術や知見を活用し、途上国を始めとする各国の条約実施に貢献します。そして、化学物質のライフサイクル全体を通じた環境リスクの最小化を目指すための国際戦略であるSAICM(サイカム)については、SAICM(サイカム)終了後の2020年以降の枠組みに関する国際的な議論を積極的にリードし、次期枠組みの採択に向け貢献します。2022年の国連環境総会再開セッションで開始が決定された、「化学物質・廃棄物の適正管理及び汚染の防止に関する政府間科学・政策パネル」の設置に向けた交渉にも積極的に参加します。海洋プラスチックごみ問題については、我が国は2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の提唱国として、今後の法的拘束力のある文書(条約)づくりに向けた政府間交渉委員会(INC)における国際交渉にも積極的に参加し、世界的な対策の推進に貢献します。
第5節 地域づくり・人づくりの推進
1 国民の参加による国土管理の推進
(1)多様な主体による国土の管理と継承の考え方に基づく取組
「国土形成計画」、その他の国土計画に関する法律に基づく計画を踏まえ、環境負荷を減らすのみならず、生物多様性等も保全されるような持続可能な国土管理に向けた施策を進めていきます。例えば、森林、農地、都市の緑地・水辺、河川、海等を有機的につなぐ生態系ネットワークの形成、森林の適切な整備・保全、集約型都市構造の実現、環境的に持続可能な交通システムの構築、生活排水処理施設や廃棄物処理施設を始めとする環境保全のためのインフラの維持・管理、気候変動への適応等に取り組みます。
特に、管理の担い手不足が懸念される農山漁村においては、持続的な農林水産業等の確立に向け、農地・森林・漁場の適切な整備・保全を図りつつ、経営規模の拡大や効率的な生産・加工・流通体制の整備、多角化・複合化等の6次産業化、人材育成等の必要な環境整備、有機農業を含む環境保全型農業の取組等を進めるとともに、森林、農地等における土地所有者等、NPO、事業者、コミュニティなど多様な主体に対して、環境負荷を減らすのみならず、生物多様性等も保全されるような国土管理への参画を促します。
ア 多様な主体による森林整備の促進
国、地方公共団体、森林所有者等の役割を明確化しつつ、地域が主導的役割を発揮でき、現場で使いやすく実効性の高い森林計画制度の定着を図ります。所有者の自助努力等では適正な整備が見込めない森林について、針広混交林化や公的な関与による整備を促進します。多様な主体による森林づくり活動の促進に向け、企業・NPO等と連携した普及啓発活動等に取り組みます。
イ 環境保全型農業の推進
第2章6節1を参照。
(2)国土管理の理念を浸透させるための意識啓発と参画の促進
国民全体が国土管理について自発的に考え、実践する社会を構築するため、持続可能な開発のための教育(ESD)の理念に基づいた環境教育等の教育を促進し、国民、事業者、NPO、民間団体等における持続可能な社会づくりに向けた教育と実践の機会を充実させます。
地域住民(団塊の世代や若者を含む。)、NPO、企業など多様な主体による国土管理への参画促進のため、「国土の国民的経営」の考え方の普及、地域活動の体験機会の提供のみならず、多様な主体間の情報共有のための環境整備、各主体の活動を支援する中間組織の育成環境の整備等を行います。
ア 森林づくり等への参画の促進
多様な主体による植樹など森林づくり活動の促進に向けて、企業・NPO等のネットワーク化、全国植樹祭等の開催を通じた普及啓発活動、森林づくり活動のフィールドや技術等の提供等を通じて多様な主体による「国民参加の森林づくり」を促進するとともに、身近な自然環境である里山林等を活用した森林体験活動等の機会提供、地域の森林資源の循環利用を通じた森林の適切な整備・保全につながる「木づかい運動」等を推進します。
イ 公園緑地等における意識啓発
公園緑地等において緑地の保全及び緑化に関する普及啓発の取組を展開します。
2 持続可能な地域づくりのための地域資源の活用と地域間の交流等の促進
持続可能な社会を構築するためには、各地域が持続可能になる必要があります。そのため、各地域がその特性を活かした強みを発揮し、地域ごとに異なる資源が循環する自立・分散型の社会を形成しつつ、それぞれの地域の特性に応じて近隣地域等と地域資源を補完し支え合う「地域循環共生圏」の構築を推進します。
(1)地域資源の活用と環境負荷の少ない社会資本の整備・維持管理
地方公共団体、事業者や地域住民が連携・協働して、地域の特性を的確に把握し、それを踏まえながら、地域に存在する資源を持続的に保全、活用する取組を促進します。また、こうした取組を通じ、地域のグリーン・イノベーションを加速化し、環境の保全管理による新たな産業の創出や都市の再生、地域の活性化も進めます。
ア 地域資源の保全・活用と地域間の交流等の促進
社会活動の基盤であるエネルギーの確保については、東日本大震災を経て自立・分散型エネルギーシステムの有効性が認識されたことを踏まえ、モデル事業の実施等を通じて、地域に賦存する再生可能エネルギーの活用、資源の循環利用を進めます。
都市基盤や交通ネットワーク、住宅を含む社会資本のストックについては、長期にわたって活用できるよう、高い環境性能等を備えた良質なストックの形成及び適切な維持・更新を推進します。緑地の保全及び緑化の推進について、市町村が定める「緑の基本計画」等に基づく地域の各主体の取組を引き続き支援していきます。
農山漁村が有する食料供給や国土保全の機能を損なわないような適切な土地・資源利用を確保しながら地域主導で再生可能エネルギーを供給する取組を推進するほか、持続可能な森林経営やそれを担う技術者等の育成、木質バイオマス等の森林資源の多様な利活用、農業者や地域住民が地域共同で農地・農業用水等の資源の保全管理を行う取組を支援します。
農産物等の地産地消やエコツーリズムなど、地域の文化、自然とふれあい、保全・活用する機会を増やすための取組を進めるとともに、都市と農山漁村など、地域間での交流や広域的なネットワークづくりも促進していきます。
イ 地域資源の保全・活用の促進のための基盤整備
地域循環共生圏の構築を促進するため、地方公共団体や民間企業、金融機関等の多様な主体が幅広く参画する「地域循環共生圏づくりプラットフォーム」を通して、パートナーシップによる地域の構想・計画の策定等を支援します。情報提供、制度整備、人材育成等の基盤整備にも取り組んでいきます。情報提供に関しては、多様な受け手のニーズに応じた技術情報、先進事例情報、地域情報等を分析・提供し、他省庁とも連携し、取組の展開を図ります。
制度整備に関しては、地域の計画策定促進のための基盤整備により、地域内の各主体に期待される役割の明確化、主体間の連携強化を推進するとともに、持続可能な地域づくりへの取組に伴って発生する制度的な課題の解決を図ります。また、地域の環境事業への投融資を促進するため、地域脱炭素投資促進ファンドからの出資による民間資金が十分に供給されていない脱炭素化プロジェクトへの支援や、グリーンボンド等による資金調達・投資の促進等を引き続き行っていきます。
人材育成に関しては、学校や社会におけるESDの理念に基づいた環境教育等の教育を通じて、持続可能な地域づくりに対する地域社会の意識の向上を図ります。また、NPO等の組織基盤の強化を図るとともに、地域づくりの政策立案の場への地域の専門家の登用、NPO等の参画促進、地域の大学等研究機関との連携強化等により、実行力ある担い手の確保を促進します。
ウ 森林資源の活用と人材育成
中大規模建築物等の木造化、住宅や公共建築物等への地域材の利活用、木質バイオマス資源の活用等による環境負荷の少ないまちづくりを推進します。また、地域の森林・林業を牽引する森林総合監理士(フォレスター)、林業経営上の新たな課題に対応する森林経営プランナー、施業集約化に向けた合意形成を図る森林施業プランナー、効率的な作業システムを運用できる現場技能者を育成します。
エ 災害に強い森林づくりの推進
豪雨や地震等により被災した荒廃山地の復旧対策・予防対策、流木による被害を防止・軽減するための効果的な治山対策、海岸防災林の整備・保全など、災害に強い森林づくりの推進により、地域の自然環境等を活用した生活環境の保全や社会資本の維持に貢献します。
オ 景観保全
景観に関する規制誘導策等の各種制度の連携・活用や、各種の施設整備の機会等の活用により、各地域の特性に応じ、自然環境との調和に配慮した良好な景観の保全や、個性豊かな景観形成を推進します。また、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、文化的景観の保護を推進します。
カ 歴史的環境の保全・活用
歴史的風土保存区域及び歴史的風土特別保存地区、史跡名勝天然記念物、重要文化的景観、風致地区、歴史的風致維持向上計画等の各種制度を活用し、歴史的なまちなみや自然環境と一体をなしている歴史的環境の保全・活用を図ります。
(2)地方環境事務所における取組
地域の行政・専門家・住民等と協働しながら、廃棄物・リサイクル対策、地球温暖化防止等の環境対策、東日本大震災からの被災地の復興・再生、国立公園保護管理等の自然環境の保全整備、希少種保護や外来種防除等の野生生物の保護管理について、機動的できめ細かな対応を行い、地域の実情に応じた環境保全施策の展開に努めます。
3 環境教育・環境学習等の推進と各主体をつなぐネットワークの構築・強化
(1)あらゆる年齢階層に対するあらゆる場・機会を通じた環境教育・環境学習等の推進
持続可能な社会づくりの担い手育成は、脱炭素社会、循環経済、分散・自然共生型社会への移行の取組を進める上で重要であるのみならず、社会全体でより良い環境、より良い未来を創っていこうとする資質・能力等を高める上でも重要です。このため、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育促進法)(平成15年法律第130号)や「我が国における『持続可能な開発のための教育(ESD)』に関する実施計画(第2期ESD国内実施計画)」(2021年5月決定)等を踏まえ、[1]学校教育においては、学習指導要領等に基づき、持続可能な社会の創り手として必要な資質・能力等を育成するため、環境教育等の取組を推進します。また、環境教育に関する内容は、理科、社会科、家庭科、総合的な学習の時間等、多様な教科等に関連があり、学校全体として、児童生徒の発達の段階に応じて教科等横断的な実践が可能となるよう、関係省庁が連携して、教員等に対する研修や資料の提供等に取り組みます。[2]家庭、地域、職場など学校以外での教育については、ESD活動支援センターを起点としたESD推進ネットワークを活用し、民間団体の取組を促進します。
(2)各主体をつなぐ組織・ネットワークの構築・強化
地域における協働取組の推進やその担い手を育成するためには、市民、政府、企業、NPO等のそれぞれのセクターが各自の役割を意識した連携が重要です。このため、全国8か所にある環境パートナーシップオフィス(EPO)等を活用して、地域における多様な主体による協働取組を推進します。
(3)環境研修の推進
従来は、研修の双方向性の確保、研修生間の交流の重視等の観点から、合宿制により集合研修を実施してきましたが、現時点ではその形式での研修実施が困難な状況であることから、集合研修の段階的再開に向けた検討・試行を行いつつ、集合研修再開までの暫定的取組として、オンライン等による「研修代替措置」を実施します。また、集合研修が再開された場合にオンライン等で対応可能な部分を組み合わせるなどの方策も検討していきます。
分析実習を伴う研修については、「遠隔参加型分析実習」を継続・拡充するとともに、オンラインによるライブ実習等の実現可能性を模索していきます。
第6節 環境情報の整備と提供・広報の充実
1 EBPM推進のための環境情報の整備
環境行政における証拠に基づく政策立案(EBPM)を着実に推進するため、国際機関、国、地方公共団体、事業者等が保有する環境・経済・社会に関する統計データ等を幅広く収集・整備するとともに、環境行政の政策立案に重要な統計情報を着実に整備します。
地理情報システム(GIS)を用いた「環境GIS」による環境の状況等の情報や環境研究・環境技術など環境に関する情報の整備を図り、「環境展望台」において提供します。
2 利用者ニーズに応じた情報の提供
国、地方公共団体、事業者等が保有する官民データの相互の利活用を促進するため、環境情報のオープンデータ化を推進します。そのため、2020年度に策定した「環境省データマネジメントポリシー」に基づき、環境省が保有するデータの全体像を把握し、相互連携・オープン化するデータの優先付けを行った上で、必要な情報システム・体制を確保し、データの標準化や品質向上を組織全体で図るなどの、データマネジメントの取組を進めます。また、国民一人一人、そして社会全体の行動変容に向けて、あらゆる主体の取組や持続可能なライフスタイルへの転換等を促進するため、情報の信頼性や正確性を確保しつつ、IT等を活用し、いつでも、どこでも、分かりやすい形で環境情報を入手できるよう、利用者のニーズに応じて適時に利用できる情報の提供を進めます。
第7節 環境影響評価
1 環境影響評価の総合的な取組の展開
事業に係る環境配慮が適正に確保されるよう、地方公共団体の環境影響評価条例と連携し環境影響評価法(平成9年法律第81号)を適正に施行するとともに、事業者の自主的な取組を推進し、環境影響評価制度の適正な運用に努めます。また、環境影響評価の実効性を確保するため、報告書手続等を活用し、環境大臣意見を述べた事業等について適切なフォローアップを行います。環境影響評価法の対象外の事業についても情報収集に努め、適正な環境配慮を確保するための必要な措置について検討します。
また、風力発電所の円滑な立地の促進のためには、適正な環境配慮の確保及び地域とのコミュニケーションの充実を図ることが重要であるところ、風力発電所の環境影響の程度が立地の状況に依拠する部分が大きいとの風力発電所の特性を踏まえ、効果的・効率的なアセスメント等の風力発電に係る適正な環境影響評価制度の検討を行います。
さらに、洋上風力発電については、その設置に伴う環境影響の予測・評価の不確実性が比較的高いという特性があることから、その特性を踏まえた環境保全措置について稼働に伴う環境影響を継続的に把握し、低減できる手法(順応的管理)等の実現に向けた技術実証事業を行います。環境影響評価等の合理化を図り導入促進に資するよう、洋上風力発電の導入が今後見込まれる海域において環境影響評価手続に必要な現地調査を実施し、取りまとめた情報を事業者や地方公共団体に提供する取組を進めます。
2 質が高く効率的な環境影響評価制度の実施
環境影響評価法に基づき、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について適切な審査の実施を通じた環境保全上の配慮の徹底を図ります。
環境影響評価の信頼性の確保や質の向上に資することを目的として、引き続き、調査・予測等に係る技術手法の情報収集・普及や必要な人材育成に引き続き取り組むとともに、国・地方公共団体等の環境影響評価事例や制度等の情報収集・提供を行います。また、「環境アセスメントデータベース“EADAS(イーダス)”」を通じた地域の環境情報の提供等に取り組みます。
既設の風力発電所や太陽光発電所における環境影響の実態を把握しつつ、風力発電や太陽光発電事業等に係る環境影響評価手続の合理化・迅速化の取組を継続します。
第8節 環境保健対策
1 放射線に係る住民の健康管理・健康不安対策
2015年2月に公表した「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議の中間取りまとめを踏まえた環境省における当面の施策の方向性」に基づき、引き続き、[1]事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進、[2]福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握、[3]福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実、[4]リスクコミュニケーション事業の継続・充実に関する施策を実施し、放射線に係る住民の健康管理・健康不安対策に取り組みます。
2 健康被害の補償・救済及び予防
(1)被害者の補償・救済
ア 公害健康被害の補償
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「公害健康被害補償法」という。)に基づき、汚染者負担の原則を踏まえつつ、認定患者に対する補償給付や公害保健福祉事業を安定的に行い、その迅速かつ公正な救済を図ります。
イ 水俣病対策の推進
水俣病対策については、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号)等に基づく救済措置のみで終わるものではなく、引き続き、その解決に向けて、公害健康被害補償法に基づく認定患者の方の補償に万全を期すとともに、高齢化が進む胎児性患者等やその家族の方等関係の方々が地域社会の中で安心して暮らしていけるよう、水俣病発生地域における医療・福祉対策の充実を図りつつ、水俣病問題解決のために地域のきずなを修復する再生・融和(もやい直し)や、環境保全を通じた地域の振興等の取組を加速させていきます。
ウ 石綿健康被害の救済
石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿健康被害救済法)(平成18年法律第4号)に基づき、被害者及びその遺族の迅速な救済を図ります。また、2016年12月に取りまとめられた中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会の報告書を踏まえ、石綿健康被害救済制度の運用に必要な調査や更なる制度周知等の措置を講じます。
(2)被害等の予防
大気汚染による健康被害の未然防止を図るため、環境保健サーベイランス調査を実施します。また、独立行政法人環境再生保全機構に設けられた基金により、調査研究等の公害健康被害予防事業を実施します。
さらに、環境を経由した健康影響を防止・軽減するため、熱中症、花粉症、黄砂、電磁界及び紫外線等について予防方法等の情報提供及び普及啓発を実施します。
第9節 公害紛争処理等及び環境犯罪対策
1 公害紛争処理等
(1)公害紛争処理
近年の公害紛争の多様化・増加に鑑み、公害に係る紛争の一層の迅速かつ適正な解決に努めるため、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)に基づき、あっせん、調停、仲裁及び裁定を適切に実施します。
(2)公害苦情処理
住民の生活環境を保全し、将来の公害紛争を未然に防止するため、公害紛争処理法に基づく地方公共団体の公害苦情処理が適切に運営されるよう、適切な処理のための指導や情報提供を行います。
2 環境犯罪対策
産業廃棄物の不法投棄を始めとする環境犯罪に対する適切な取締りに努めるとともに、社会情勢の変化に応じて法令の見直しを図るほか、環境犯罪を事前に抑止するための施策を推進します。
出典: 環境省