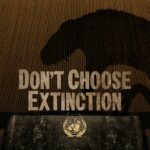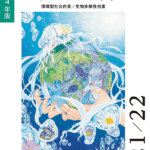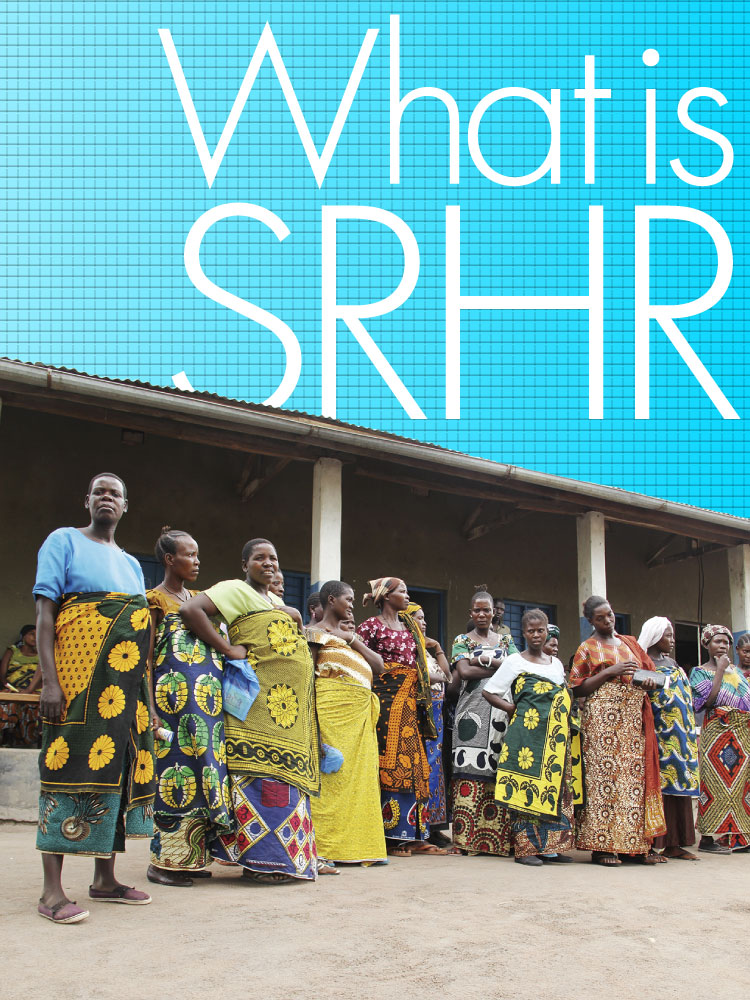
SRHR:性と生殖に関する健康と権利とは
「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(Sexual and Reproductive Health and Rights)」を略して「SRHR」と呼ばれます。
参考:Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) / WHO
SRHR(性と生殖に関する健康と権利)は、SDGsの目標5に出てきていますが、1994年に「国際人口・開発会議(ICPD)」で採択された「カイロ行動計画」で提唱された概念です。
WHO(世界保健機関)によると、リプロダクティブヘルスとは、「性と生殖に関する健康のこと」で、生殖の機能とそのプロセスに関連するすべての問題において、病気や不健康がないだけでなく、身体的・精神的・社会的に幸福な状態のことであり、人々が満足のいく安全な性生活を送ることができ、生殖能力と、生殖するかどうか、いつ、どのくらいの頻度で行うかを自由に決定できることを意味するとしています。性に関することや妊娠・出産といった生殖に関することを自分で決める権利があり、またこの権利が保障されるための情報やサービスにアクセスできる権利があるとしています。
リプロダクティブヘルス/ライツでは、すべてのカップル・個人には以下の権利があり社会的・政治的に左右されず自由に責任を持って決定できるとしています。
- 安全で満ち足りた性生活を営むことができること
- 本人の意思が尊重され、妊娠・出産について自らが選択し決定する権利
- 子どもを持つ、子どもを持たないことを決める権利
- 出産する子どもの人数、出産する間隔、出産する時期を選べる権利
- 安全に安心して妊娠・出産ができること
- 自分の身体に関することを自分で決定する権利
- 自分の性のあり方について自分で決定できる権利
- 自分の性に関して心身ともに満たされ、その状態を社会的にも認められていること
- 法に反しない出生調節の方法についての情報を得て利用する権利
- 差別・強制・暴力を受けることなく、生殖に関する決定を行える権利
- これらの権利を実現するために必要な情報やサービスへアクセスする権利及び受ける権利
世界では、望まない出産の中絶が制限されたり、強制婚や女性性器切除のような慣行があるなど、性と生殖に関することを自己決定する環境が整っていない国や地域が大半です。そのため、SRHRが叫ばれているのです。
性と生殖に関するヘルスケア
「SRHR」における情報へのアクセスやサービスを受けるために必要なことは、そのための環境が整っていることです。
150ヶ国以上の加盟協会からなるNGO(国際協力組織)の国際家族計画連盟によると、誰もが絶対に必要な性と生殖に関するヘルスケアサービスは、その権利を行使するために「サービスがあること、その受けやすさ、容認性、質の高さ」が保障されなければならない、としています。
そして、この必須サービスには次のようなものが含まれます。
- セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルスに関する正確な情報と、カウンセリングサービス。これにはエビデンスに基づいた包括的性教育(CSE)が含まれます
- 性機能と性的な満足に関する情報、カウンセリング、ケア
- 性暴力、ジェンダーに基づく暴力、性的強制の予防、発見、対策
- 安全で有効な避妊法の選択肢
- 安全で有効な産前、出産、産後のケア
- 安全で有効な中絶サービスとケア
- 不妊予防、対策、治療
- HIV を含む性感染症(STI)と生殖器系感染症予防、発見、治療
- 生殖器のがん予防、発見、治療
セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖の健康と権利:SRHR)の新定義 / 国際家族計画連盟(IPPF)
ja_ippf_technical_brief_SRHRすべての妊婦さんの知る権利
性と生殖に関するヘルスケアの「サービスがあること、その受けやすさ、容認性、質の高さ」というのは、出生前診断にも当てはまります。
お腹にいる赤ちゃんの病気や障害について調べる検査のことを「出生前診断」といいます。一般的なのは、妊婦さんが定期健診で受ける「エコー検査」ですが、出生前診断には色々な種類があり、妊婦さんの血液から胎児の染色体異常を調べる「新型出生前診断(NIPT)」もその一つです。
新型出生前診断は、日本では2013年に開始された比較的新しい検査で、需要の高まりもあり検査施設は年々増加しています。
出生前診断の本来の目的は、治療や育児の準備につなげるためのものですが、胎児の病気や障害を生まれる前に調べるという性質上「安易な中絶につながる恐れ」があるとされ、さらに「命の選別である」「障害のある人の差別や存在否定につながる」として賛否の議論がたえません。
そのため厚労省では、「胎児に疾患がある可能性を確率で示すものに過ぎないことなどから、医師は妊婦に対し本検査の情報を積極的に知らせる必要はなく、本検査を勧めるべきでもない」として、今までは情報提供について消極的な姿勢をとっていました。しかし現在は「正しい情報を求める妊婦の増加に対して、不安に寄り添った支援とはいえない」として、情報提供を行っていく方針で進んでいます。
すべての妊婦さんには
生活の福祉を向上するために情報やサービスを選択しアクセスする権利
自分の意思が尊重され、自分の身体に関することを自分自身で決められる権利
があり、正しい情報の元で自分で決断する権利があります。
出典:NIPT Japan