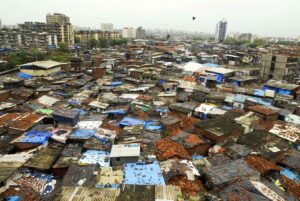海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっています。
こうした背景を踏まえ、第204回通常国会において、プラスチック使用製品の設計からプラスチック廃棄物の処理に至るまでの各段階において、あらゆる主体におけるプラスチック資源循環の取組(3R+Renewable)を促進するための措置を講じた「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)」が成立しました。
同法の政令委任事項及び施行期日等を定めるため、関係政令が2022年1月14日に閣議決定されました。
政令の概要
(1)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
1.プラスチック使用製品の設計調査
プラスチック使用製品製造事業者等が、プラスチック使用製品設計指針への適合性に係る技術的な調査を受ける際の「手数料の額」等を定めます。
2.特定プラスチック使用製品に係る指定及び当該製品に係る勧告等の対象
特定プラスチック使用製品の「対象製品」及び「対象業種」に、主としてプラスチック製の12品目(カトラリー・アメニティ等)及びこれらを無償で提供している小売業・飲食業等を指定するとともに、主務大臣の「勧告等の対象」を、当該製品を前年度5t以上提供した事業者とする要件等を定めます。3.プラスチック廃棄物の回収・リサイクルに係る業務の委託基準等
プラスチック廃棄物のリサイクル計画について、主務大臣の認定を受けた市町村又は事業者が、当該計画に係る業務を委託する場合の基準等を定めます。4.プラスチック使用製品産業廃棄物等に係る勧告等の対象
主務大臣の「勧告等の対象」を、プラスチック使用製品産業廃棄物等を前年度250t以上排出した事業者とする要件等を定めます。(2)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令
法の施行日を、令和4年4月1日と定めます。
以下、政令本文
第一 目的
この法律は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチ
ックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品
の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創設
等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするこ
と。(第一条関係)
第二 定義
- この法律において「プラスチック使用製品」とは、プラスチックが使用されている製品をいうものとすること。
- この法律において「使用済プラスチック使用製品」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたプラスチック使用製品であって、放射性物質によって汚染されていないものをいうものとすること。
- この法律において「プラスチック使用製品廃棄物」とは、使用済プラスチック使用製品が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物となったものをいうものとすること。
- この法律において「プラスチック副産物」とは、製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチックであって、放射性物質によって汚染されていないものをいうものとすること。
- この法律において「再資源化」とは、使用済プラスチック使用製品又はプラスチック副産物(以下「使用済プラスチック使用製品等」という。)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいうものとすること。
- この法律において「再資源化等」とは、再資源化及び使用済プラスチック使用製品等の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にすることをいうものとすること。
- この法律において「分別収集物」とは、市町村がプラスチック使用製品廃棄物について分別して収集すること(以下「分別収集」という。)により得られる物をいうものとすること。
- この法律において「再商品化」とは、次に掲げる行為をいうものとすること。
㈠分別収集物について、製品(燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。)の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
㈡分別収集物について、㈠に規定する製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。 - この法律において「排出事業者」とは、プラスチック使用製品廃棄物のうち廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物に該当するもの(分別収集物となったものを除く。)又はプラスチック副産物(以下「プラスチック使用製品産業廃棄物等」という。)を排出する事業者をいうものとすること。(第二条関係)
第三 基本方針
- 主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物の排出の抑制並びに回収及び再資源化等の促進(以下「プラスチックに係る資源循環の促進等」という。)を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとすること。
- 基本方針は、海洋環境の保全及び地球温暖化の防止を図るための施策に関する法律の規定による国の
方針との調和が保たれたものでなければならないものとすること。(第三条関係)
第四 事業者及び消費者の責務
事業者は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努め、消費者は、プラスチック使用製品廃棄物を分別して排出するよう努め、事業者及び消費者は、プラスチック使用製品をなるべく長期間使用すること、プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること等のプラスチック使用製品の使用の合理化により、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとともに、使用済プラスチック使用製品等の再資源化等により得られた物又はこれを使用した物を使用するよう努めなければならないものとすること。(第四条関係)
第五 国の責務
国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な資金の確保、プラスチックに係る資源循環の促進
等に関する情報の収集、整理及び活用、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずる
よう努めるとともに、教育活動、広報活動等を通じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する国
民の理解を深め、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならないものとすること。
(第五条関係)
第六 地方公共団体の責務
市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努め、都道府県は、市町村に対し、市町村の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるよう努め、都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第六条関係)
第七 プラスチック使用製品設計指針の策定等
- 主務大臣は、プラスチック使用製品の製造を業として行う者(その設計を行う者に限る。)及び専らプラスチック使用製品の設計を業として行う者(以下「プラスチック使用製品製造事業者等」という。)が設計するプラスチック使用製品についてプラスチックに係る資源循環の促進等を円滑に実施するためにプラスチック使用製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針(以下「プラスチック使用製品設計指針」という。)を定めるものとすること。
- プラスチック使用製品製造事業者等は、プラスチック使用製品設計指針が定められたときは、これに即してプラスチック使用製品を設計するよう努めなければならないものとすること。(第七条関係)
第八 プラスチック使用製品の設計の認定
- プラスチック使用製品製造事業者等は、その設計するプラスチック使用製品の設計について、主務大臣の認定(以下「設計認定」という。)を受けることができるものとすること。
- 主務大臣は、設計認定の申請があった場合において、当該申請に係るプラスチック使用製品の設計プラスチック使用製品設計指針に適合していると認めるときは、設計認定をするものとすること。
- 主務大臣は、設計認定のための審査に当たっては、申請に係るプラスチック使用製品の設計のプラチック使用製品設計指針への適合性についての技術的な調査を行うものとすること。
- 設計認定に係る設計の変更の認定等について所要の規定を設けること。(第八条及び第九条関係)
第九 認定プラスチック使用製品の調達についての配慮等
- 国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第六条第一項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に係るプラスチック使用製品(以下「認定プラスチック使用製品」という。)の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならないものとすること。
- 事業者及び消費者は、認定プラスチック使用製品を使用するよう努めなければならないものとすること。(第十条関係)
第十 指定調査機関
主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第八の三に規定する調査(第八の四に係るものを含む。)の全部又は一部を行わせることができることとし、指定調査機関について所要の規定を設けること。(第十一条から第二十七条まで関係)
第十一 特定プラスチック使用製品の使用の合理化
- 主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため、主務省令で、その事業において特定プラスチック使用製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「容器包装再商品化法」という。)第二条第一項に規定する容器包装を除く。)として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する事業者であって、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの(定型的な約款による契約に基づき、当該業種に属する事業を行う者に特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者を含む。以下「特定プラスチック使用製品提供事業者」という。)が特定プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するために取り組むべき措置に関し、当該特定プラスチック使用製品提供事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとすること。(第二十八条関係)
- 主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため必要があると認めるときは、特定プラスチック使用製品提供事業者に対し、一の判断の基準となるべき事項を勘案して、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制について必要な指導及び助言を、特定プラスチック使用製品多量提供事業者(特定プラスチック使用製品提供事業者であって、その事業において提供する特定プラスチック使用製品の量が政令で定める要件に該当するものをいう。)の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制の状況が一の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、その判断の根拠を示して、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関し必要な措置をとるべき旨の勧告等をすることができるものとすること。(第二十九条及び第三十条関係)
第十二 市町村の分別収集及び再商品化
- 市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集に当たっては、当該市町村の区域内においてプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準の策定等の措置を講ずるよう努め、市町村が分別の基準を定めたときは、当該市町村の区域内においてプラスチック使用製品廃棄物を排出する者は、当該分別の基準に従い、プラスチック使用製品廃棄物を適正に分別して排出しなければならないものとすること。(第三十一条関係)
- 市町村は、分別収集物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)の再商品化を、容器包装再商品化法第二十一条第一項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)に委託することができるものとすること。(第三十二条関係)
- 市町村は、単独で又は共同して、分別収集物の再商品化の実施に関する計画(以下「再商品化計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとし、再商品化計画の変更等について所要の規定を設けること。(第三十三条及び第三十四条関係)
- 認定に係る再商品化計画に記載されたプラスチック容器包装廃棄物(容器包装再商品化法第二条第四項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務省令で定めるものをいう。)については、これを容器包装再商品化法第二条第六項に規定する分別基準適合物とみなして、容器包装再商品化法の規定を適用するものとすること。(第三十五条関係)
- 指定法人等は、廃棄物処理法の規定にかかわらず、同法の規定による許可を受けないで、分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施することができることとし、所要の規定を設けること。
(第三十六条及び第三十七条関係) - 適用除外について、所要の規定を設けること。(第三十八条関係)
第十三 製造事業者等による自主回収及び再資源化
- 自らが製造し、若しくは販売し、又はその行う販売若しくは役務の提供に付随して提供するプラスチック使用製品が使用済プラスチック使用製品となったものの再資源化のための使用済プラスチック使用製品の収集、運搬及び処分の事業(以下「自主回収・再資源化事業」という。)を行おうとする者(以下「自主回収・再資源化事業者」という。)は、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画(以下「自主回収・再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとし、自主回収・再資源化事業計画の変更等について所要の規定を設けること。
(第三十九条及び第四十条関係) - 自主回収・再資源化事業計画の認定を受けた自主回収・再資源化事業者等は、廃棄物処理法の規定にかかわらず、同法の規定による許可を受けないで、認定に係る自主回収・再資源化事業計画(以下「認定自主回収・再資源化事業計画」という。)に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を業として実施することができることとし、所要の規定を設けること。
(第四十一条及び第四十二条関係) - 適用除外について、所要の規定を設けること。(第四十三条関係)
第十四 排出事業者による排出の抑制及び再資源化等
- 主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため、主務省令で、排出事業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者を除く。二において同じ。)がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置に関し、当該排出事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとすること。(第四十四条関係)
- 主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため必要があると認めるときは、排出事業者に対し、一の判断の基準となるべき事項を勘案して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等について必要な指導及び助言を、多量排出事業者(排出事業者であって、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が政令で定める要件に該当するものをいう。)のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況が一の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該多量排出事業者に対し、その判断の根拠を示して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告等をすることができるものとすること。(第四十五条及び第四十六条関係)
- 適用除外について、所要の規定を設けること。(第四十七条関係)
- 自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業(プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化のためのプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬及び処分の事業をいう。以下同じ。)を行おうとする排出事業者及び複数の排出事業者の委託を受けて、これらの者が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする者(以下「再資源化事業者」という。)は、再資源化事業の実施に関する計画(以下「再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとし、再資源化事業計画の変更等について所要の規定を設けること。(第四十八条及び第四十九条関係)
- 再資源化事業計画の認定を受けた再資源化事業者等は、廃棄物処理法の規定にかかわらず、同法の規定による許可を受けないで、認定に係る再資源化事業計画(以下「認定再資源化事業計画」という。)に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為を業として実施することができることとし、所要の規定を設けること。(第五十条から第五十二条まで関係)
- 六適用除外について、所要の規定を設けること。(第五十三条関係)
第十五 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、認定プラスチック使用製品の製造、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化及び認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証及び認定プラスチック使用製品、認定自主回収・再資源化事業計画及び認定再資源化事業計画に係る研究開発に必要な資金に充てるための助成金の交付に関する業務並びにこれに附帯する業務を行うことができるものとすること
(第五十四条関係)
第十六 報告の徴収、立入検査及び関係行政機関への照会等
- 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定プラスチック使用製品製造事業者等に対し、業務の状況等に関し報告をさせることができるものとすること。(第五十五条関係)
- 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定プラスチック使用製品製造事業者等の事務所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができるものとすること。
(第五十六条関係) - 主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができるものとすること。(第五十七条関係)
第十七 主務大臣等
この法律における主務大臣及び主務省令並びに権限の委任について定めるものとすること。
(第五十八条関係)
第十八 経過措置
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができるものとすること。(第五十九条関係)
第十九 罰則
罰則について所要の規定を設けること。(第六十条から第六十六条まで関係)
第二十 附則
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
- 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
- この法律の施行に関し、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の規定の整備を行うものとすること。(附則関係)
出典:経済産業省